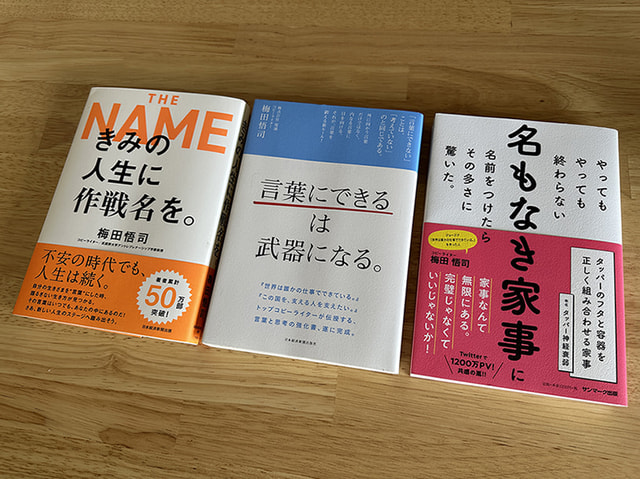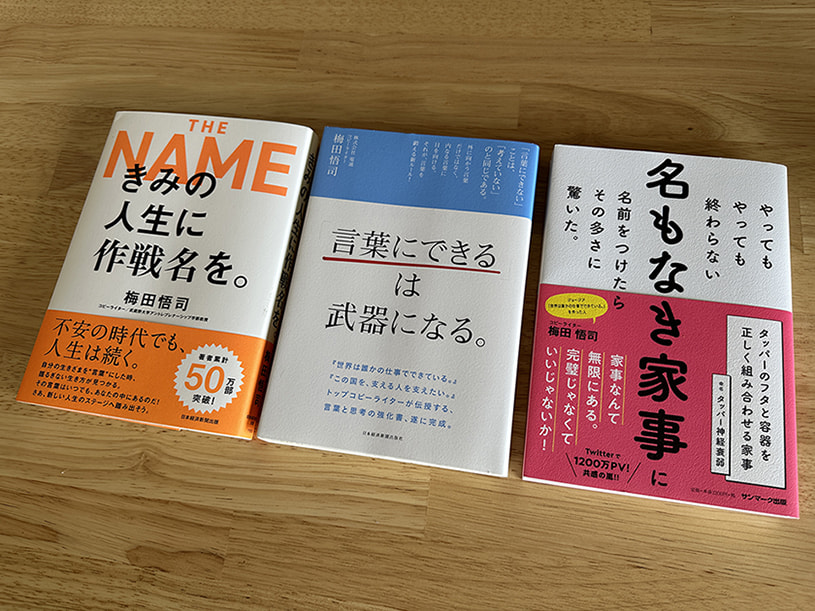コロナ禍で見えてきた組織コミュニケーションの差
―コロナ禍が明け、経済活動が元に戻ったように見えます。現在の状況について、どう思われますか。
梅田 組織の生産性へのスタンスの違いが明確に表れたと考えています。2020年4月の緊急事態宣言下では、出社を控えてください」と極端な状況に陥りました。「リモートワークになるのは仕方ないよね」以上の議論をしていない組織にとっては、リアルかリモートかの手段の話でしかありません。
一方、コロナ禍以前から生産性の向上を目的に、リモートワークを視野に入れていた組織では、その状況を自分たちへの後押しとしました。
当時、社会全体で、「どのような場所で働いても、生産性が上がれば問題ない」という風潮もあったので、コロナ禍に振り回されず、生産性という文脈で捉えられていた企業にとっては、チャンスだったのではないでしょうか。
社内の目線が合うように、きちんと説明がなされているか、もかなり重要です。背景や全体像を説明することによって、行動に意味が生まれます。その意味を共有しているか否か、理解しているか否かで、納得度が変わるんですね。コロナ禍が明けて、出社スタイルに戻ったとしても、そこに至るまでの議論や説明のプロセスこそが重要であると感じます。
会社から指令として通達されただけなのか。もしくは、リモートとリアルの良し悪しを経験した上で検証が行われ、説明と対話を行ったか。その両者では、社員の納得感は大きく異なります。たとえ経営層で生産性に対する議論がされていたとしても、それが社員に伝わっていなければ、みんなで力を出したいという空気は生まれにくいでしょう。要は丁寧なコミュニケーションや対話をしようとしているかどうか、です。
―説明と対話は確かに大切ですね。しかしリアルで集まる良さを体感している世代が、未経験の世代に伝えることは難しそうです。
梅田 世代によって、リアルネーティブか、リモートネーティブかに分かれますよね。僕を含めたおじさん世代、つまり、リアルネーティブの人たちは、実際にリモートをやってみて、「ここはリモートのほうがいいよね。でも、ここはリアルに軍配が上がるよね」という観点で、学びを得たはずです。
実は、コロナ禍で社会人になったリモートネーティブの若者世代が、リモートのコミュニケーションにこだわるというのは、リアルネーティブのおじさんたちがリアルにこだわるのと同じ構造に見えます。互いに相手のことを知らないわけですから。
リモートネーティブの人たちも一度リアルを経験し、そこで感じたことを議論すればいいわけです。「リアルはもうご免」という声もありますが、「リアルのほうが面倒な気がする」というのは想像や空想の話で、体感ではないこともあります。
どちらかしか知らない状態や、命令だから聞くという関係を超えて、お互いを知り、意見を交換することが大切でしょう。想像とやってみた結果とでは、実感が違います。当然、想像したとおり面倒なこともありますが、それが自分にとって心地いいか悪いかによって、全く違う感情が生まれる可能性もあるのです。
―まず「やってみる」ところに行き着くために、どう伝えればいいのでしょうか。
梅田 面倒臭がらずに、丁寧に伝えることです。一般的には、プレゼンテーションや会社の中期経営計画書などのように、わかりやすく数字や具体例を用いて簡潔にまとめるコミュニケーションスタイルがいいとされています。特にビジネスの場ではその傾向は強いですよね。
しかし、そこには「なぜその結論に至ったのか」という肝心なものが抜けています。なぜそう思うのか、その真意を共有できていないと、本当の合意は結べません。「合意」とは「合意形成」が前提にあるので、「これが経営陣での合意事項なので、社員は聞けばいい」というのでは、本来の意味での合意形成にはなりません。誰かが決めたものを無理やり飲まされているだけでは、合意は形成されませんよね。
―「合意させられた」ということでしょうか。
梅田 そうですね。だから合意形成は、プロセスにこそ重心を置くべきです。決定事項は端的に伝えたほうがいい場合もありますが、合意形成のプロセスにおいては真逆で、抽象的なことをグダグダと話さないと形成に至らないことも多いでしょう。そのレベルは、個人対個人から組織対組織まで、さまざまです。また、既に合意したことが、そこにほかの誰かが入ることによって変化することもあります。
しかし、決定事項を通達するだけの組織では、そうはいきません。例えば社員全体数の10%の新入社員が入ってきた場合、当然10%の新しい血が入ってくるので、何かが変わってもおかしくないわけです。しかし、多くの会社は変わらないことを是とします。そのような会社は、合意形成のプロセスを軽視しているようにも見えます。
面倒臭くて時間もかかるし、着地点も見えない。そのような不安に負けずに新しい合意をつくり続けようとする態度が重要で、それをやっている会社は強いと感じます。

―実際に、どういう会社がそれを実践されているのでしょうか。
梅田 比較的、若い会社に多い気がします。会社も経営者も若いため、自分の人生をこの会社にかけようとしてくれる人に対して応えたいという気持ちがあります。「君がいる会社と、君のいない会社が違って当然だよね」、ときちんと伝えています。
一般的に会社に新しく社員が入っても、その会社の経営方針やビジョンは変化しません。しかし、若い経営者たちは、自分の会社を社員が選んで来てくれたことに感謝し、「君が入ったことによって我が社がどんな違いを生み出せるのか、一緒に考えていこう」と伝えます。社員は力が出るし、会社はいい方向に変わりますよね。
その結果、社員は「自分はこの会社という器を通して、社会にどのような良いことができるのか」を本気で考えるようになるのです。「自分がこの会社の中で何をするのか」という小さな話ではなくて、「この会社がいい方向に変わっていくためには自分は何をすべきか」「この会社で新しい取り組みを始めることで社会をどう動かせるのか」です。そういった社員の意識付けができる会社は良い方向に変化します。
言葉の外側にある本質を探る
―しかし、その人の本来のものを出しやすくする環境をつくるのには、時間がかかりますよね。梅田さんがコピーライターとしてお仕事されてきた世界と異なるような気がしますが。
梅田 コピーは結果として端的なものになります。ただ、何の議論も情報もなく、わかりやすくてシンプルなものを伝えると、一般論に終始してしまうことは目に見えています。
その商品への意気込みや思い、これまで上手くいったことや失敗したことも含めて、「えも言われぬ何か」を内包させることによって、一般論を超えることができるのです。その会社らしい何かに近づけるということです。
例えば僕が経営者とお会いして、メッセージを2時間一緒に考えるとしたら、1時間半はずっと質問しながら議事録を取っています。「なるほど、なるほど」とずっと聞いているだけです。
時々、抽象的でわかりにくい部分があれば質問して、長々とお話しいただく。その内容をメモし続けます。すると「ああ、この方は言葉ではこう表現しているけれど、本当に言いたいことは別にあるんだな」という、言葉と気持ちの乖離に気づけるのです。人間って決して言葉どおりのことを言いたいわけじゃないですからね。
―本当は言葉どおりのことを言いたいわけじゃない、とは気づきませんでした。
梅田 その時に、そういう表現しか思いつかないからそう言っているだけです。そこには、「こんなわかりづらい話をしても、誰もわからないだろうから、捨象してわかりやすく表現したほうがいいかな」という諦めが含まれている場合が多いように感じます。
そのため、僕は自分や相手に対して、「本当は、そういうことを言いたいわけではないに違いない」ということを前提としています。端的な言葉の裏側にある複雑なことや、数字では測れないこと、公の場で言うのがはばかられる裏話などを全部含めて、わかりやすい言葉に表現する。端的な言葉はあくまでも結果に過ぎないのです。
頭のいい人たちが賢い議論をしていると、一般論にたどり着きがちです。これを僕は「一般論の罠」と呼んでいます。だいたいの会社が新しい事業開発をする際に出てくる、「高齢者向けのIoTを使ったデジタルツールをつくるべきだ」というアイデアのようなものです。
本質に基づいた「らしさ」は、抽象的でグダグダした、えも言われぬ何かのようなものにしか含まれない。そこを近道せず、あえて遠回りをして、一般論を超えたわかりやすいメッセージに落とし込んだ結果、端的だけど魅力的な言葉になっていくのです。
「シンプルでわかりやすいメッセージ」は、何の議論もしないほうが簡単につくれるのも事実です。でも、面倒な議論や時間をかけた話し合いを経たメッセージは、全く違うものになります。結局、シンプルでわかりやすいメッセージにはなるんですけどね。自分と相手が見えている世界の差に思いをはせて、敬意を持って話を聞いた結果に生まれてくる言葉は、重みも深みも厚みもあるんです。
―これまで何冊も著作を出されています。それらは、まだ100%表現しきれていないということでしょうか。もしくは、面倒臭いものを表現できたということでしょうか。
梅田 書き切ったからこそ、足りない部分に気づき、またそこから出発するという感じですね。頭の中が散らかっていて、自分が何を考えているかよくわからない状態ってありますよね。
本を執筆する際は、あるテーマに沿って自分の考えを、世間の人々の役に立つように構成し直すことを前提に、探索します。
そして一冊の本ができて初めて、「そうか、自分はこういうことを考えていたのか」と気づくのです。
頭の中にあるものが一式出たところで、また新しい空白が生まれます。そして、「こういう応用ができるかも?」とまた考えが始まり、新しいものを加えていきます。そのサイクルを自分でつくっている感じですね。
全部アウトプットすることで、まだ語られていないことや発展する余地に、自分で気づくのです。書いた後で、「こういうことを書いたほうがもっと役に立ったかも」という展望や反省といったものが生まれてくる感じです。
―コピーのように、結果として端的な言葉にすることと、本のように文字数が多いものを出すことに違いはありますか。
梅田 僕にとっては完全に延長線上です。コピーライティングの根本には、電通で学び、経験させてもらったことが詰まっています。バッターボックスに立つ機会を与えられたからこそ能力を伸ばし、また自分の中にある大切なことへの気づきを得られたという感謝の気持ちがあります。
先人たちによって築かれた会社への信頼に対して仕事を頂き、その寛大な力によって、僕はコピーライティングを任され、言葉の力を人よりも少し伸ばすことができたと認識しています。
著作に関しては、例えば広告会社でコピーライターにならなくても、20年間も言葉のことだけを考えて修練しなくても、多くの方が簡単に追体験できるような、言葉についての本を書きたいと思っています。自分が20年間、言葉のことしか考えていなかったから気づけたことってやっぱりあるんですよね。その20年間で学んだことを体系的に追体験できるように、約1,500円というパッケージに詰め込んでお渡ししていく。それが僕が会社に育ててもらったことに対する社会還元になるのかな、と思っています。
『「言葉にできる」は武器になる。』『きみの人生に作戦名を。』という著作は、個人を対象にしており、マーケティングの本ではありません。「あなたの中にある重要なものを言葉にして、自分の背骨にする。それによって、また新しい一歩を踏み出す力を内側から生み出していきましょう」という趣旨の本です。コピーライティングの方法論がベースとなりますが、対象が違うのです。
その一方、広告は、企業を対象として、商品広告を中心に、時には企業メッセージを一緒に考え、世の中に出します。今僕は、個人の中にあるものを表出させて、その人が自分を鼓舞できるツールとしての言葉を開発することを重視しているので、個人を対象にしています。
武蔵野大学のアントレプレナーシップ学部でいうと、やりたいことがあるのにどうすればいいかわからない、自分が社会に貢献するために何ができるのか真剣に悩んでいる、といった「小さな自分の大きな可能性」を見出そうとする若者に向き合うことにやり甲斐を感じます。
企業や商品のコミュニケーションではなく、個人の中のもやもやのようなものを自己認識した上で前に進むという、メンタリングや言語化支援を、狭く、深くやったほうが社会は良くなるだろう、という確信が含まれます。
カリスマ的存在をつくるのか、小さなリーダーを多く生むのか
―そのような考え方に至るまでには、何かきっかけがあったのでしょうか。
梅田 カリスマ的な存在をつくるか。もしくは、小さなリーダーをたくさんつくるか。最後はそういう話になるかもしれません。基本的に広告会社の仕事は、認知率80%のものを81%にするという、カリスマ的なものをつくることと言い換えることもできると考えています。そこに対して優秀な人たちが関わっていく。規模が大きく、日本人の多くが知るコミュニケーションをつくりたい、という意欲のある、大きな仕事をしたい人が集まります。
一方、僕は象徴的なカリスマよりは、何かをやろうとしているけど、辺境の地でグダグダと悩んでいる人のほうに興味があります。この人が自分のやるべきことを認識し、何か活動し始めると、周りが巻き込まれてチームが生まれる。もしかしたら社会を変えるかもしれない、と思える兆しを数多くつくっていったほうが、結果的に社会は良くなるのではないか、という仮説があるんです。
―広告会社を辞めた後、アントレプレナー支援の会社を経て、大学の世界に移られました。
梅田 広告の世界で、認知率80%のものを81%にするのも重要かつ難しい仕事です。表現の角度を変えるだけではなく、まだ誰も気づいていない新しい価値を見つけ出さなければならない。その領域で、クリエイティビティを発揮し、勝負している方も多くいらっしゃいます。僕も勝たなくてはいけないプレゼンに向かったことがあります。
しかし、キャンペーンといった短期的な取り組みではなく、もっと長期的な視点で見た場合、この育ててもらった自分の力を違う場面で使いたいな、と思うようになったのです。例えば、生活者一人ひとりに目を向けると、自分だけでは抱えきれない悩みや葛藤といった、小さな地獄を抱えながら生きているのが現実です。そのような、他人にはわかってもらえないと感じていた影に光を当て、思いを寄せていきたい。その全てを言葉に詰め込むための支援ですね。
―そのように詰め込むためには、何が必要なのでしょうか。
梅田 僕がコピーライティングの中で一番重要だと思っているのは、「何も捨てない」という姿勢です。クリエイションの過程では、削って磨くというのが一般的ではありますよね。では、何も捨てないために、何をしているのかというと、その人の生い立ちから仕事、家庭までを含めた人生まるごと、その先にある人生観に対して、説明可能な一本の軸をずっと探しているんです。要約でもなく、側面を切り取って強調するわけでもありません。ただ、その全てを説明可能な軸を探すだけです。
だから、僕のコピーはわかりやすくない。若干、説明的で文字数も多めですが、ある種、本当にそうだよね、と思える「1×N」みたいな世界をつくれてきたのかな、と思っています。
その中の一つが、日本コカ・コーラ社と手がけた「ジョージア」の「世界は誰かの仕事でできている。」かもしれません。これは、ジョージアがどうして誕生したのか、また自動販売機ネットワークを通して何を社会に提供しているのか、という背景に思いをはせることによって到達した言葉です。議論の中で、日本中で自分の仕事や、やるべきことを頑張っている人たちがいるから、彼らの休憩に寄り添うために自動販売機ネットワークを構築しているという真意に気づきました。
自動販売機ネットワークがあるということは、その商品が品切れしそうになったら補充してくれるボトラー社の方たちがいます。するとその方たちは、ただ飲料を補充しているのではなく、短い休憩を豊かなものにする手助けをしている、という文脈が生まれます。製品そのものや原材料であるコーヒー豆について話すだけでは、たどり着けない観点ですよね。
多くの人が、自分のやっている仕事なんて、誰でもできるんじゃないか、と感じている。しかし、この仕事を誰かがやらないと社会は回らない、とも感じている。その狭間で、葛藤しながら生きていると感じます。例えば、交通整理を担う方がいないと、事故が起きます。しかし、それは誰でもできる仕事と思われている。
そんな方にどんな言葉をかけるべきなのか。それこそが、ジョージアの社会への眼差しであり、優しさであり、存在意義であるという議論をしたことを今でも覚えています。あなたが頑張っていること、持ち場を守ることが社会をつくっていることになる、と実感できるメッセージ。それが、「世界は誰かの仕事でできている。」という言葉に集約された思いです。
現代の「タイパ」視点でみると、あり得ないくらい遠回りしているように感じられると思います。自動販売機は、数の差はあれど、さまざまな飲料ブランドが設置しています。そのため、そこに目をつけることは競争優位にはならないですよね、という話にもなり兼ねません。しかし、その自動販売機ネットワークについては、集中して議論するテーマであると確信していました。

―かなり時間をかけて合意形成に至ったのでしょうか。
梅田 そうですね。わかりづらいですから、すごく時間がかかりました。合意形成のレベルもさまざまで、確かに理解されやすい表現は、早めに合意形成の握手を交わすことができますが、その分、早く手を離すことにもつながります。その一方、一見飲み込みづらく、理解や共感を超えた深いレベルでの合意形成は、ロングスパンのキャンペーンにつながっていくのです。
それは心と心で結んだ合意形成なので、キャンペーンがじわじわと浸透するのを我慢できるし、1年間経ったから、何か新しいものを考えようか、とは誰も思いもしません。一つのことを長期に継続するので、ブランディングにもつながります。一定の緊張感を保ちながら、振り出しに戻らない関係性とでもいいましょうか。
僕が得意なのは、抽象的で面倒臭くて、グダグダとしているものに向き合うこと。そして、その全てを捨てることなく言葉にすることで、「この会社はそこまで考えているんだ」「信頼に足りうる企業なんじゃないか」という真実味を世間に醸成することです。僕自身、1億人が1回CMを見たらわかるような、ドカンとしたキャンペーンを打って商品もバカ売れ、というコピーライティングは苦手なので、それをご希望でしたら、どなたか得意な方をご紹介させていただきます、とお伝えしています(笑)。クリエイター一人ひとりがそれぞれの答えを持っているので、得意な方に任せたほうが絶対に上手くいきます。僕はわかりやすくてエッジが立ったものよりは、全人格的な広告コミュニケーションを志向していますので、はっきり線引きをしています。頭のいい人たちによる賢い議論によって到達する答えとは別の答えを出したい。自分が仕事の依頼を受ける際は、その点をはっきりお伝えしています。
自分らしい感情は、実感やグダグダとした話の中にある
―これからAIがどんどん言葉を習得して、最後は「人間らしさ、自分らしさって何?」というところに行き着くと思います。今後、言葉の力や本質はどうなっていくのでしょうか。
梅田 チャットGPTをはじめとするAIの活用は一般的になってくると思います。でも、大きな違いは、身体性と実感の有無だと感じます。走って汗をかいて、キツかったけど、気持ちよかった。おいしいレストランだと思ってわざわざ遠くに行ったのに、自分の舌に合わなくてがっかりした。こうした身体性に伴う実感は、AIにはない。感情ではなく、実感です。さらに言えば、感情は持ち始めているとすら思います。AIへの指示を、丁寧
語で行うか、命令語で行うかによって、アウトプットに差が出てくるともいわれています。僕も実験しましたが、確かに違いが生まれました。
実感は必ずしも線形ではありません。上手くいったから楽しい、ではなく、上手くいかなかったけど楽しかったという二律背反がありえる。例えば、子どもが将棋教室に通ってもルールが覚えられず上達しないと、親は違うことをやらせたほうがいいのでは、と思います。でも、本人はすごく楽しがっている。これが実感です。「こうに違いない」という推測は、論理の世界です。しかし、逆の実感が生まれてもおかしくないのです。
例えば、お金持ちになった人が、「貧乏だった時が一番楽しかった」という話もあります。お金持ちのほうが何でも自由にできそうなのに、貧乏な時代に狭い家で雑魚寝した日々が一番楽しかったというのも実感です。僕はこうした一見、二律背反するようなものが一番面白いと感じます。実感という複雑なものをデータベースにして、AIにそれを理解させてそれらしいものを吐き出させることはできるかもしれないですが、本当にそれが個
人の実感と整合しているか、が大切です。
嬉しい、悲しい、などの感情のレベルでは、すでにAIは取得していると思いますが、人間には理屈が通らないような心の機微があります。その一人ひとり異なる実感は、AIにはまだないのでは、と思っています。実感は一人ひとり違って最後まで一つになり得ないので最終的には、自分の実感に沿っているかという視点での選択かな、と思います。

―昨年度から大学の世界に移られました。これからやっていきたいことをお聞かせください。
梅田 コピーライティングやマーケティングの方法は教えられるので、続けていきます。ただ、生徒たちは、高校でプレゼンテーションの研修を受ける中で、みんな「わかりやすくて端的に伝えるべし」と言われ続けてきたのですね。実際プレゼンも上手いですよ。しかし、その中で捨象されてしまっているものを、もう一回思い出させることをやりたい。
生徒たちの、わかりづらくてグダグダした、抽象的な話をとにかく聞く。授業中の発言や、レポートも「わかりやすく書く必要はなく、グダグダ書いてください」「一文字でも多いほうが嬉しいです」と伝えています。端的ではなく、グダグダした、えも言われぬようなものを、僕の前では言えるような環境をちゃんとつくってあげたい。生徒たちは、これまで、親や学校の先生に「もっとわかりやすく説明しろ」と言われ続けているはずです。だからこそ、抽象的なことをグダグダ言っているのに対して、「ああ、そうなんだね、すごくよくわかった。ありがとう」って言ってあげることが、僕の役割です。
「もっとわかりやすく伝えよう。聞き手の時間を無駄にしないように」、そう言われ続けていたら、当然話さなくなりますよね。すると、忘れてしまうんです。自分の中で複雑性や多面性を抱えながら、でもこういうことをやりたい、みんなに伝えたい、と思っていた感情すら。大げさに言えば、それは人間性の喪失だと思います。僕の前で語ることで、とにかく思い出してもらいたい。「僕はその時を知らないけど、かつて先生や親に“何を言っているかわからない”と言われていた話を僕の前でしてほしい。大丈夫、僕は言葉のプロだから」って(笑)。

―心強いですね。生徒の自己肯定感も上がりますね。
梅田 僕は全部聞きますよ。本当は言葉のプロでも何でもないんですけどね。でも、「言葉のプロだから理解できるよ」と伝えることで、相手にもう一度言おう、という勇気が生まれる。
そして最後に、「ああそうか、こんなことを言っても伝わらないと思っていたけど、そうじゃないんだ」と気づいてほしいんです。
これは広告制作の現場で、担当者と向き合っているときも同じです。わかりづらくて抽象的で、グダグダしていることは、広告をつくる上では全く意味がない、むしろノイズになる可能性すらあるから、「クリエイターには黙っておけ」ということを上司から言われたりするわけですね。
でも、そんなことこそが重要なので、「とにかく今、考えていることを全て洗いざらい話してください」という場をつくって、僕はずっと聞いている。こちらから働きかけることによって、忘れていた感情があったことを思い出してもらえれば、だいたい上手くいきます。そのため、洗いざらい話したくなる場と空気をつくってあげられたら、と常に思っています。