ママ友と始めた小さな地域活動
—まず「こたえのない学校」という一般社団法人をつくられた経緯を教えてください。
藤原 経済的や社会的、身体的に困難や不自由な思いを抱える人のいる中で、誰もが幸せに生きられる社会を実現するにはどうすればいいのだろう。そういった思いが私の興味の出発点かもしれません。
大学で政治学を学び、卒業して政府系金融機関に勤め、その後、米国の大学院で公共政策を専攻しました。当初は国連職員としてのキャリアなども考えたのですが、周囲から「公的な領域で仕事をするにしても、ビジネスのことは知っておいたほうがいい」とのアドバイスもあって、ソニーに入社しました。
初めはエンターテインメント事業の本社経営企画管理部門に配属され、それからコーポレートディベロップメントなど企業戦略の部署に移り、海外・国内企業とのアライアンスを経験しました。
その後、出産を経て、ヘルスケア領域に特化したコンサルティング会社に勤務。その時に娘が通っていた保育園で、図らずも父母会長を務めることになります。当初は渋々ながらでしたが、いざやり始めるとこれが楽しく、ママ友の知り合いも増えていきました。そんな友人と金曜の夜、子どもたちを連れて近所の商用施設のフードコートで夕食を取りながら今後の学校教育への不安を話し合ううちに、「自分たちでも何かできないかな」という話になっていったのです。そこで仕事は続けながら、ライフワーク感覚で地域の子どもの学びの支援活動をスタート。後にその活動主体として設立したのが一般社団法人こたえのない学校です。
—壮大な計画に基づいたわけではなく、最初は仲間で小さく立ち上げたのですね。
藤原 そうです。当時、ママ友の中に新聞社で記者の経験があり、自身の会社も経営されていた林りん正じょん愛え さんがいて、主に彼女と2人、仲間のネットワークにも頼りながら、手弁当で自分たちの子どもを対象にした活動を、地元の公民館などを借りて始めました。
私は起業経験もなく、子どもたちが来てくれるか不安だったのですが、林さんが「いやいや、そんなものよ」といった感じで励ましてくれたことは、とても心強かったです。
探究する学びとの出会い
—こたえのない学校が始まってから、現在の方針の根幹をなす「探究する学び」には、どう結びついていったのでしょうか。
藤原 その頃、周りの親たちも「そもそも社会に出たら答えのないことだらけなのに、なぜ学校では答えのあることばかり教えるのだろう」とモヤモヤしていました。
一方で、多くの大人たちが、自分の仕事を子どもたちに伝えたいと感じていることもわかってきました。しかし子どももまだ保育園生。たとえ偉い人にレクチャーをしていただいたところで、子どもたちに伝わらないだろうということは明白でした。そこで「ワークショップ型で大人も子ども一緒に楽しめ、かつ子どもが広い世界に興味を持つようになるような手法はないものか」とリサーチを始めたところ、半年ほどして米国の教育学者リン・エリクソンの「概念型カリキュラム(Concept-Based Curriculum)」を活用した探究学習という考え方に出会ったのです。
—ということは先にプロジェクトが始まり、「探究」という概念は具体的な内容を模索する中で見つけたものでしたか。
藤原 はい。当初は教育については全くの素人でした。モンテッソーリやシュタイナーの本を少し読んだことがあったくらいです。
「概念型カリキュラム」を使うこの方法は、伝えたいコンセプトを中核に置き、それに則ってワークショプを構成していくもの。企業勤めの経験がある自分たちにとって、仕事でプロジェクトを立ち上げる際のフレームワークと重なり、馴染み深かったのです。
—実際のお子さんたちの反応はどうでしたか。最初から「わっ、楽しい」という感じだったのでしょうか。
藤原 コンセプトをベースに子どもたちが興味を持ってくれそうなアクティビティを入れていくことができるので、基本的には楽しくワークに参加してくれたと思います。当時まだ小学生だった子たちが高校生、大学生となり、「あのときのワークショップが今の活動や進路選択に決定的な影響を及ぼしている」などと言ってくれることも最近増えてきました。とても嬉しく思っています。
米国で学校教育の概念をアップデート
—藤原さんはお子さんとともに米国に滞在された経験もあります。当時の経験で印象深いことや、現在の考えに影響を与えていることについてお聞かせください。
藤原 米国に移ったのは娘の保育園の卒園後、こたえのない学校の立ち上げの時期でした。家族の仕事の事情で米国で生活することとなったのですが、娘はグレード1から3(日本の小学校の1~3年に相当)を米国で過ごすことになります。米国に行ったのは偶然ですが、結果的にとても貴重な経験となりました。
教育活動を始めてはいたものの、それまではわりと普通の母親でした。当時はオルタナティブスクールにも私学受験にも興味がなくて。自分が公立小学校を出ているので「娘も公立に行くに決まっているでしょう」といった程度の認識でした。
しかし、米国に行ってみると、子どもは月曜から金曜まで地元の学校に通い、土曜日だけ日本語補習校に行くわけです。するとまだ英語もできない娘は、週5日間は授業内容が何もわからない。知識を獲得するという側面からは、ほとんど意味をなしてないのですが、周りの子を見て真似をしてサバイブし、友達をつくり、英語を必死で習得しようとしていました。そこで非認知のコンピテンシーを力強く培っているように見えたのです。私は、学校には絶対行くべきだし、そうするものだと当たり前に思っていました。でも、娘は日本の学校でするような経験は全然していないけれども、きちんと学んでいるし成長しているではないか、と。だとすると「学校の形は今のままでなくてもいいのでは」と思い至るようになりました。
例えば米国の運動会はPTAがほぼ取り仕切っていて、先生たちはリハーサルもせず、当日は観客として楽しんでいます。点数が間違っても誰も気にしない。新学期にはロック音楽をかけ、生徒たちは机の上でガンガン踊ったり、「クレイジーヘアデイ」というものがあって、生徒たちは髪の色や服装を大胆にアレンジしてクレイジーさを競い合う日もありました。だからといって、人格が崩れてしまうわけではなく、むしろ伸び伸びと育っています。
そんな光景を目の当たりにして「日本のやり方でなくても、子どもは育つんだ」と実感しました。よくも悪くも「学校はこうじゃなきゃいけない」という固定観念が、私の中でガラガラと音を立てて崩れてしまったのです。

—いわゆる「読み書きそろばん」といった基礎的なことは、米国ではどのように教えているのですか。
藤原 米国にも日本の学習指導要領と同じような機能を持つ学習スタンダードはあります。私たちがアメリカにいた頃、連邦で統一した「コモンコア」というスタンダードが各州に広がり始めていたのですが、採用判断は州に委ねられていました。滞在先のテキサス州はそれを採用せず、州独自の基準に沿って授業が組まれていましたが、大きくコモンコアスタンダードから外れる内容ではないように思います。
例えば、小学校低学年の四則計算だと、チームに分かれておもちゃのコインを使って計算させ、できない子がいれば、わかる子が教えます。ピザを切り分けて分数の概念を学んだり、ミニカーを使って、車輪の数の計算をしていました。つまり、リアルな状況の中で数学の概念を学んでいくのです。
—日本では算数の勉強は「ドリルを1冊やりましょう」となりがちですが、リアルな生活経験の中で学ぶといろいろな応用が利きそうですね。
藤原 そうですね。例えば「植物の花弁や種の数を題材にフィボナッチ数列を学ぶ」などの授業をしてみてもいいかもしれません。理科や数学、生物、アートという垣根を越え、手も心も使いながら学んだほうが、本来は楽しめるはずですよね。
教える側から知ったアメリカ高校教育の課題
—藤原さんは一方で、米国で学生に教えた経験もあるとうかがいました。
藤原 教えたといっても大層なものではなく、現地のコミュニティカレッジで教職課程を履修し、サブスティチュートティーチャーという、いわゆる高校の代理教員の仕事をしました。教師が体調を崩したり、研修に参加するなど、さまざまな理由で休む際、地域の教育委員会のオンラインシステムで「ここを休みます」と申請すると、代理教員側に連絡が入るようになっているのです。
—日米の高校生の違いや印象的な出来事など、教える側の経験から感じたことはありますか。
藤原 私は初等教育までは、日本より自由に個性を伸ばす米国のほうがいいかな、と思うことも多いのですが、高校はかなり迷いますね。米国は高校も義務教育なので、私学を選ばない限り、基本は地域管轄の学校に行きます。日本の中学のような感じで、複数の小学校が統合されて学校規模も大きくなります。
高校はレベル別の授業です。すると一番レベルの高いAP(アドバンストプレイスメント)のクラスの子たちは課題さえ与えればどんどんと自ら学び、授業の必要がないほどです。一方で一番低いレベル1の授業では、誰も何も聞いてはいない。既に人生を半ば諦めているといった雰囲気が教室に漂っています。所得が低い家庭に育って落ちこぼれてしまった子は、高卒もしくは高校もドロップアウトして、その結果、一生涯低賃金の仕事しかつけなくなってしまう子も多いのです。
実際に家庭がすごく複雑な生徒が多く、自殺の危険などを察知できるように携帯番号を生徒に伝え、休日でもいつでも連絡を受け取れるようにしている先生もいました。クラスでは、パーカーを頭から被っていつもハサミを持ち歩いている子もいましたし、授業中に紙飛行機を飛ばし、授業をあからさまに馬鹿にする生徒もいました。米国は厳しい学歴社会なので、こうした状況からはい上がるのは至難の業です。そんな社会の闇のようなものを、高校で手伝いながら見ていましたね。
—多様性社会ならではの分断が、ますます顕著になっているようですね。
藤原 米国では幼い頃から「あなたは何でもできる」と言って子どもを育てますが、高校生ぐらいになると子どもたち自身が「何でもできるなんて嘘」「頑張っても報われないこともある」と気づきます。そして心を病む子も多い。食べつないでいくことに精いっぱいの層が、FOXチャンネルの視聴者になり、トランプの支持層になっていきます。そんなネガティブなスパイラルが続いているのも米国の現実。いい点も数々ありますが、決してそれだけではありません。
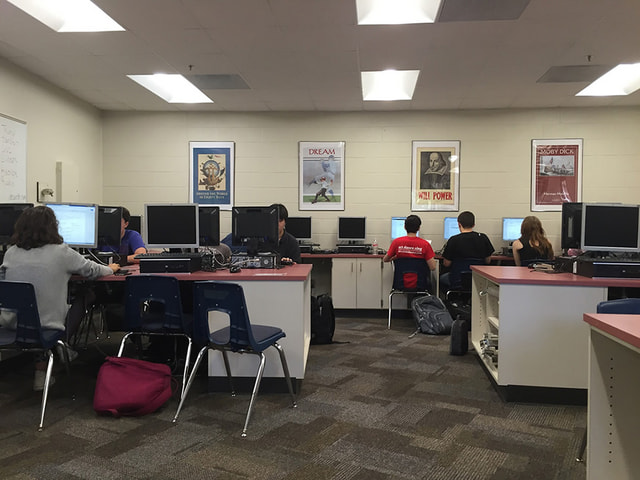
「ハイ・テック・ハイ」との出会い
—ところで著書で紹介されていた「ハイ・テック・ハイ」は公立で、生徒の約半数がスペイン語を話すヒスパニック系の家庭の子で、給食費の補助を受けています。それなのに学力面でも高い大学進学率を誇っているとのこと。この学校を知ったきっかけについて聞かせてください。
藤原 私が米国にいた2016年のある日、デジタルハリウッド大学大学院教授でEdTechが専門の佐藤昌宏先生から突然、「今度サウス・バイ・サウスウエスト(SXSW)というイベントで登壇してもらえないか」といったお誘いのメールを頂きました。
当時、米国の学校のことをいろいろブログに書いていたのですが、それを読まれた佐藤先生が、開催地オースティンからあまり遠くないヒューストン郊外に私が住んでいたこともあってか、お声がけくださったのです。そしてSXSW会場で会った方々の中に、教育領域のドキュメンタリー映画『Most Likely to Succeed』の日本上映に向けて活動していた竹村詠美さんがいらして、そこで映画を見せていただいたのです。この映画で紹介されていたのがハイ・テック・ハイでした。
—実際、現地のハイ・テック・ハイにも何度か行かれ、研修も受講されたそうですが、印象はいかがでしたか。
藤原 この学校の大きな特徴の一つが、プロジェクト型学習(以下PBL)です。PBLでは生徒たちが協働し、あるテーマのもとに成果物を作り上げます。特にハイ・テック・ハイのPBLでは、その過程での探究を通して、必要な知識のみならず、美的感覚や倫理観をも身につけていくところに特徴があります。ここでは、できる限り“美しい作品”を創造することに価値が置かれています。
学校を訪れてまず驚くのは、校内に素晴らしい成果物の数々が飾られ、美術館のようになっていることです。彼らは、成果物の展示、キュレーション、そして創作における批評の精神をとても大切にしています。
—ハイ・テック・ハイのPBLは具体的にはどのように行われるのですか。
藤原 例えば環境問題を扱うゴミプロジェクトでは「ゴミの大量廃棄は良くない」から始まるのではなく、まずは各家庭でどんなものを捨てているか、生徒にゴミを持って来てもらいます。そしてゴミの袋を開けたときの不快な臭いや中身を見たことで起きる感情の変化をポートレート写真に撮り、廊下に展示します。最終的には、プラスチックごみを使った巨大なインスタレーションを製作したり、その体験を演劇に仕立てたりします。その過程では、もちろんゴミに関するさまざまな科学的調査やゴミを減らすための地域とのディスカッション、政策立案なども行います。
—プログラムの中で行うアクティビティの内容は全て先生が考えるのですか。それとも子どもたちと一緒に練り上げていくのですか。
藤原 PBLにはさまざまな手法があるのですが、ハイ・テック・ハイでは、バックワードデザインを採用しています。よって、まずは先生が各プロジェクトのゴールとして、発表会や成果物のアウトプットのイメージを決めます。そこから逆算して途中に、例えばゴミ問題を扱うのであれば、ゴミ処理場に見学に行くなどのアクティビティを計画したり、このリサーチペーパーを教材にするとか、こういう分析のオプションを用意するなど全体を組み立てていくのです。もちろん子どもたちは思うとおりには動かないので、常に軌道修正が必要なのですが。
—終わりのイメージを持って、そこからバックキャスティングしていくということですね。
藤原 そうです。この方法だといわゆる学習スタンダードに沿って、基本となるコンテンツを埋め込みながら、楽しい学びを設計することが可能です。例えば、環境破壊に関するプログラムだったとしても、国語と組み合わせて関連する古典を読んだり、詩を作ったりすることができます。スタンダードに紐付けて大枠の設計をしつつも、子どもたちが自ら作品を創造していくといったイメージです。
単元が始まる前には、先生たちは実際に生徒たちに作らせるものを試作してみたり、見学場所を下見に行ったり、そこまで準備します。結構大変な仕事だと思いますよ。


—そのように優秀な先生たちが、公立の学校に集まっていることに驚きました。
藤原 ハイ・テック・ハイでは、多様な社会経験を持つ教員志望の人たちに、現場で経験を積みながら教員免許を取得してもらう、といったことを行っています。それこそ「元はエディターです」といった人が「国語の授業をやりたい」と入ってくることもあります。ただ、ハイ・テック・ハイというのはパブリックチャータースクールという仕組みを使っており、一般的な公立学校とは違って、学校独自の採用が可能なこと、創立から約20年が経って認知度も上がっていることも影響しているでしょう。「ぜひここで教えたい」という先生方が全米から集まってきています。
—藤原さんは、ハイ・テック・ハイのPBLにかかわらず、「探究する学び」の場づくりをされているとうかがっています。具体的には、どんなことをされているのでしょうか。
藤原 こたえのない学校は元々、小学生向けプログラムの開発と実施をしていたのですが、2016年から教育者向け研修(Learning Creator’s Lab)をスタートしました。
先ほどお話ししたように、概念型カリキュラムを活用した探究学習からスタートしましたが、探究学習にはさまざまな方法や理念があります。当法人では、ハイ・テック・ハイのPBL以外にも、国際バカロレア(IB)や、子ども哲学、日本の生活・総合学習、イエナプランなど、さまざまな探究の形を紹介しています。そして、その中でどれが正しいとか、より優れているなどと評価することはありません。一つ一つの探究には、それぞれの良さがあり、そのベースとなる共通の構造がありますので、教育者はそれを理解した上で、自分に最もフィットするものを見極め、授業で自在に実践したらいいのではないかと思っています。よって、一つの特定の手法を「教える」ということはしていません。私たちの研修は基本的にはすべて半年から8カ月程度の長期のもので、先生たちがチームを組んで、自らプロジェクトを生成し、そのプロセスの中でとことん探究することを求めています。現在年間100名ほど受け入れており、教育者コミュニティは400名近くになりました。

日本の学校の先生を取り巻く環境
—藤原さんから見て、日本の先生を取り巻く環境は改善されてきたと思われますか。
藤原 いえ、あまり良くなっているように見えません。むしろ、悪くなっていると思うことが多いかもしれません。現在、ニュースなどでもよく報道されていますが、特に公立学校で全国的に先生が足りない状態です。なり手も減っています。
この3年間、日本では新学習指導要領が導入され、新型コロナウイルスに翻弄されたほか、1人1台PCなど、ICTの対応も学校はしなければなりませんでした。大きく環境が変化する中で、不登校の子どもも増えています。先生たちは、とても忙しい中で頑張っていますので、さまざまな意味での支援が必要です。
—先生たちは、ICT教育を子どもたちの自律的な学びにうまくつなげられているのでしょうか。
藤原 ICTはまだ過渡期なので自治体によって差があります。導入当初はアプリの立ち上がりに長時間を要したり、先生と生徒のシステムが異なり、先生が子どもたちの学習結果を見られないなど、さまざまなことがありましたが、徐々に問題は解消されてきています。
しかし、まだまだICTの活用法は洗練されているとはいえません。逆に無理に使おうとしすぎているケースも散見されます。自然の中に出ていくとか、身体性を伴った学びはとても大切ですので、なんでもかんでもデジタルを使おうとする必要はないはずです。こればかりは、先生が日々の実践でそのバランスを見いだしていくしかありませんね。
探究する学びのこれから
—こたえのない学校の今後について、教えてください。
藤原 探究学習に関する世間の関心は高まっており、研修の依頼は増えていますので、引き続き今の事業を継続し、発展させていきますが、2年ほど前からインクルーシブ教育に力を入れています。重度の障害のある子たちも含めてのインクルージョンをPBLや探究学習を活用して、実現したいと考えています。障害のある子とない子が一緒に学ぶ場は、先生の負荷も大きく、なかなか実現しないのが現状です。
昨年夏、日本政府は国連の障害者権利委員会から勧告を受けました。具体的には、受け入れの体制が整っていないことを理由に、障害のある児童が地域の学校から受け入れを拒否されるなど、特別支援教育が通常学級と分離されていることなどが指摘されたのです。重い障害がある子どもは、特別支援学校を卒業した後には選択肢が極めて限られており、これは大きな問題だと思っています。
バリアフリー環境も徐々に整いつつありますが、重い障害のある子を持つ保護者に一番欲しいものを尋ねると「(息子や娘に)友達が欲しい」と返されるのです。同世代の障害のある子とない子が小さい頃から共に育つ環境があれば、障害のある子が一緒に生きる仲間だと当たり前に理解でき、現在のような分断は起きないのではないでしょうか。
少し視点を変えれば、だれしもに長所があり、等しく価値があります。今、勉強ができる子たちが得意なことはAIが代替していきます。本当に大切なことは何なのか、ということを問い直す時期に私たちは差し掛かっているように思います。勉強ができない子を社会的に無価値だと切り捨てるのではなく、だれしもが尊重され、幸せに生きられる社会をどうやったら構築できるのか。そんなふうに価値転換はできないのか、と考えます。とりわけ公正を重んじるべき公教育こそ、こうしたことに大いに取り組むべきではないかと思っています。今、さまざまな学校とパイロットプロジェクトを立ち上げており、今年の夏は、ノーマライゼーション発祥のデンマークにおけるインクルーシブ教育視察研修の計画などが進んでいます。

—藤原さん個人として、これからについて何か考えていらっしゃることはありますか。
藤原 個人としては、日本の学びの源泉を探っています。いま批判にさらされている日本の教育は、明治政府になって取り入れたプロイセン型の国家主義的教育の価値観ではないでしょうか。プロイセン型の教育とは、いわゆる強い国家のための義務教育で、国家がどんな子どもたちに育てたいかが最初にあり、そのために正しい知識や技能といったものを、効率よく習得させるためのカリキュラムが組まれます。
つまり国家が定めた、学習指導要領に載っているような見方・考え方に対して、的確にスピーディに正解を出せて、無難に振る舞う子どもが評価されてきたわけです。しかし、それが本当に日本の姿なのか、もう少し検証してみたい。それに抗うような活動は明治・大正時代にもいろいろと続いてきたし、江戸時代の私塾などでは、かなり自由闊達な教育が行われていたところもありました。そう考えると、私たちが現在、日本の教育として残念だと思っているものが、本当に私たちのルーツなのか。個人的にはそういった問いをテーマに、いろいろと考えを巡らせてみたいと思っています。
一般社団法人 こたえのない学校







