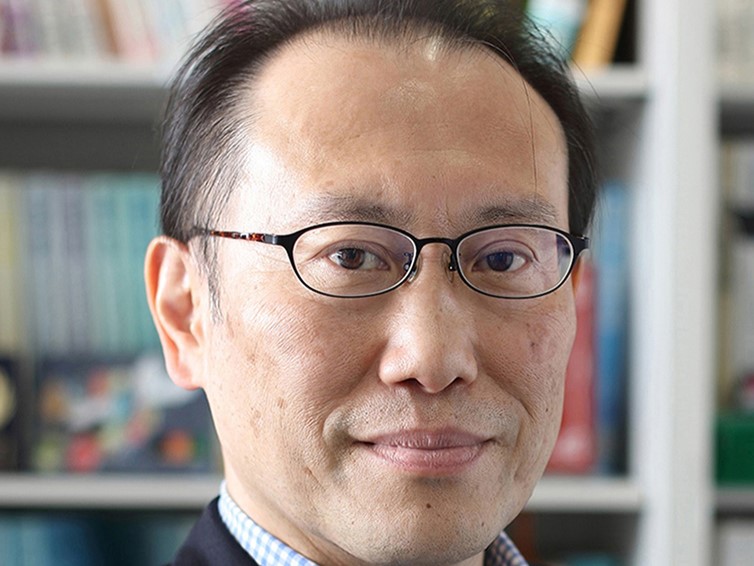コミュニティ・ベースのクリエイティブ・カンパニー
— 諏訪さんはクリエイティブ(広告制作)の世界で多くの実績を残されてきたとうかがいました。
諏訪 実は広告クリエイティブとしてのキャリアはあまり長くありません。大学卒業後、ラジオ局InterFMの設立に参画し、局のクリエイティブディレクターになり、そこからクリエイティブの世界に入りました。その後、1997年にNYに渡ってSchool of Visual Arts でデジタルアーツを学び、現地でデザイナーとして働き始めたのです。
当時はAmazonやGoogleが誕生したりと、インターネットがアメリカで劇的に勃興してきた時期。僕もWebのデザインなどを手がけていました。その頃に住んでいたのが、ニューヨークのブルックリンにあるDUMBO(ダンボ)という地区です。治安のよくない低所得層向けの住宅地域に、市がソーホーのような芸術家村をつくろうと計画し、古い建物にデザイナーやアーティストを優先して入居させていたのです。
私もその入居審査の担当者に「ポートフォリオを見せろ」と言われ、デジタルのデザインを見せました。すると「いいじゃないか」と評価してくれて入居できることに。そしておんぼろビルのワンフロアをあてがわれました。広すぎて、自分で床を塗り直すだけで2週間もかかってしまったのですが。
— ダンボにはどのような人たちがいたのでしょうか。
諏訪 僕の隣は、電気釜で宇宙船の焼き物をつくっているオランダ人の陶芸家でした。同じビルにはファッションデザイナーもいて、勝手にファッションショーをやったりしていました。ダンボには面白い人たちが集まっていて、独自のカルチャーがそこで生まれ始め、次第にそれを見に、週末になるとマンハッタンから人がやって来るようになっていったのです。
クリエイターが集まったことで、今まで荒廃していたエリアに文化が芽生え、少しずつ街ができていく。ダンボに2年ほどいて、そうしたアートやデザインの力をリアルに体験し、「これをインターネットでやれないかな」と考えるようになりました。
— それがロフトワーク設立につながったわけですね。
諏訪 はい、インターネット上では、ビジネス向けのアートやデザインはまだ流通していませんでした。ネットへの入り口としては、ヤフーなどの待ち受け画面からディレクトリに入っていくのが主流。個人のデザイナーのWebサイトへは到達手段がない。万一到達できても、流通の仕組みがなかったのです。
そこで当時、会社を辞めて米国・ボストン大学大学院に留学後、共同通信のニューヨーク支局に勤務していた友人、林千晶に「クリエイティブをネットで流通させる仕組みづくりを一緒にやらないか」と声をかけ、2人でloftwork.com(ロフトワーク)をつくったのです。これはクリエイターと企業をつなぐことを狙ってポートフォリオ機能を持たせ、デザイナーやアーティストを集めて各自の作品を紹介していく、クリエイティブのポータル的なサイトです。
ダンボでの経験があったので、ビジネスモデルなどはあまり考えず、「まずクリエイターのコミュニティをつくることからスタートしよう」という方針で始めました。サイトを立ち上げたのが1999年。ダンボの街でも営業して、みんなに登録してもらいました。結果的に1万人のクリエイターが登録してくれて。そこで「会社化しよう」という話になり、「アメリカより日本で」と考え、2000年に日本に戻って会社を設立したのです。サイトはバイリンガルでやっていたのですが、拠点を日本に移したことで、次第に日本人の登録者が増えていきました。
とはいえ、現在でも登録者の15%ぐらいは外国人のクリエイター*ですね。
— ビジネスを始める前に、「まずコミュニティありき」ということですか。
諏訪 それが我々の基本方針になっています。現在、ロフトワークのコミュニティの中にはクリエイターだけでなく、アカデミアや起業家の人たちもいて、一緒に仕事することも多いです。
クリエイティブの世界にプロジェクト・マネジメントを導入
— ロフトワークの立ち上げは順調だったのでしょうか。
諏訪 創業当時、クリエイティブの仕事は会社経由か、知り合い経由で来るか、どちらかという世界でした。オンラインでポートフォリオをつくったことで、そこにトランザクション(商取引)が発生し、クリエイターに直接仕事を依頼できるようになりました。その意味では、ビジネスとクリエイターの橋渡しをするという、創設時に考えていた機能は実現できたと思います。ただネット経由のクリエイティブビジネスは、なかなかうまくいかなかった。ほぼ必ず、仕事のことでもめてしまうのです。
双方ともまだネットでのやり取りに慣れていない上に、当時は回線の容量が少なく、画像を送るのが大変だったという事情がありました。お互いにテキストのみでやり取りしていたのです。でもデザインの仕事をするのに文字だけしか使えないのでは、仕事になりません。例えば、会社のロゴ製作の依頼があったとき、お客の側は「赤くて丸いもの」というような指示を出してきます。それを受けてクリエイターが自分の想像で“赤くて丸い”ロゴをつくるのですが、途中でラフデザインを見せて選んでもらうことも、感想を聞くこともできないのですから、うまくいくわけがない。お客の側が「こんなものにお金を払いたくない」とへそを曲げると、クリエイターの側は「そんなバカな、こっちは20日間これにかかりきりだったんだぞ」と反論。みんなこっちに文句が来るのです。
結局、僕らが企業とクリエイターの間に入るようになり、「どうすればうまくいくんだろう」と考えて、プロジェクトマネジメント(PM)の勉強をするようになりました。2001年の後半ぐらいのことで、日本ではまだPMの概念もなかった頃です。『PMBOK GUIDE』というPMの教本をアメリカから取り寄せ、それを読みながら、クリエイティブビジネスに当てはめていきました。
— そこからロフトワークが企業から注文を受け、作業内容をリストアップし、適任と思われるクリエイターに発注するというスタイルになったわけですね。
諏訪 ええ。既にデジタル関係のクリエイターのコミュニティはできていたので、企業側からするとワンストップで頼めて、直接クリエイターとやり取りする必要もなくなり、通常の広告代理店への発注の形態に近くなったわけです。ただ僕らは広告代理店とは違って、社内にクリエイターは置きませんでした。社内にいたほうがコミュニケーションは楽なのですが、「常にクリエイターのコミュニティとともにある」というのが、僕らの基本スタンスだからです。今に至るまで、ロフトワークではクリエイターは雇用していません。
— ロフトワーク社内にはどういった方が集まっているのですか。
諏訪 社内にいるのはPMを扱うメンバーです。クリエイティブが好きだけれども、クリエイターにはならなかったという人が集まってきました。
2007、8年頃に出版不況があり、出版社や編集プロダクションからかなり人が来てくれました。彼らは日頃、大量の情報をさばいて雑誌をコンスタントにつくり上げるといったプロジェクトを行ってきています。だからPMができるんですね。そうした人材が集まったことで、組織としてのPMの力も上がってきました。例えば「携帯ゲームがすぐに2,000個ほしい」という依頼を受け、それを400人のクリエイターと協働して一気につくるといったこともやりました。
— ネット経由でクリエイターのコミュニティとつながっていたことで、組織の中にクリエイターを抱えるよりも、規模が大きなプロジェクトを受けられるようになったと。
諏訪 ただその後は、クリエイティブ業界にはデジタル制作に特化した大きなプロダクションが出現してきて、ロフトワークにはWeb制作やクリエイティブの範疇を超えた、言語化が難しい依頼が寄せられるようになりました。「どんなものをつくればいいのか、よくわからないが、こういうことができないか」といったプロジェクトベースの相談が、企業から持ちかけられるケースが増えたのです。
そこで2009年頃から、企業向けのワークショップを行ったり、デザイン思考(Design Thinking)にシフトするようになりました。
— デザイン思考とは、ビジネス上の前例のない課題や未知の問題を解決するために、デザイナーやクリエイターが使う思考プロセスを活かしていくことですね。
諏訪 はい、完全には言語化されていないオーダーに対して、こちらでアイデアを考えてプロジェクトとしてまとめていくスタイルに変わっていきました。ロフトワークは今、200人ほどの体制ですが、PMとデザイン思考を結び付けられる人材が多くを占めています。
サーキュラーエコノミーは世界の潮流
— その後はどういった活動をされてきたのでしょうか。
諏訪 2010年代に入ってから、オフラインのクリエイティブコミュニティの拠点となる「FabCafe(ファブカフェ)」を世界各地に設けていきました。
FabCafeは“デジタルものづくりカフェ”で、米国・MITのニール・ガーシェンフェルド教授の提唱で始まった、世界的な「FAB運動」の流れを引くものです。カフェに3Dプリンタやレーザーカッターなどのデジタルものづくりマシンを置き、地域のクリエイターやアーティスト、企業と協力し、食、アート、バイオ、AI、教育などのラボ活動を行っています。
最初にオープンしたのが渋谷の「FabCafe Tokyo」で、今ではフランスや台湾など、世界13カ所にまで増えました。


— 林業の支援など、特集テーマのサーキュラーエコノミー(CE)に関わる活動も行ってらっしゃいます。
諏訪 飛騨市から林業や森林の課題を相談されたことをきっかけに、2015年には林千晶が代表取締役となって岐阜県飛騨市に「株式会社飛騨の森でクマは踊る(ヒダクマ)」を設立、翌年「FabCafe Hida」をオープンし、クリエイティブによる林業復興プロジェクトを行うようになりました。
現代の若い建築家の多くは「木を使いたい」と考えています。しかし木は生き物で、特に広葉樹は形がさまざま。普通の建築家は、曲がった木材を使った図面を描けません。
そこで飛騨市内の集材所・製材所に近い場所に、家の構造材としては使われない広葉樹を使った「森の端(もりのは)オフィス」という新たな拠点を設置。その中に作業所を設け、未利用資源の代表格である曲がった木を扱う「曲がり木センター」を開設しました。このオフィスを中心に若い建築家を集め、コミュニティをつくろうという構想です。今では100人近い建築家のコミュニティが生まれています。ヒダクマの広葉樹も、渋谷のミヤシタパークの待ち合わせエリアにオブジェとして置かれたり、ソニーコンピュータサイエンス研究所の京都研究室の家具に使われたりと、用途が広がってきました。
また最近では2022年に、「Saruya( サルヤ)Hostel」(https://saruya-hostel.com/)という古民家を改装した宿泊施設で知られるリノベーション会社DOSOの代表、八木毅さんと一緒に富士吉田に「FabCafe Fuji」をオープンしました。
日本国内では東京、京都、飛騨、名古屋に続く5拠点目のFabCafeです。
富士吉田は伝統的な絹織物産地で、テキスタイルの街。そこで「FabCafe Fuji」をベースに「FUJI TEXTILE WEEK」という、テキスタイルとアートを融合させ、テキスタイルの新たな「FabCafe」の1号店となる東京・渋谷の「FabCafeTokyo」(https://fabcafe.com/jp/tokyo/)。広々とした店内には3Dプリンタやレーザーカッターが設置され、電源とWi-Fiも無料で開放。充実した軽食・ドリンク類を楽しみながら、ワーキングペースとしても利用可能。デジタルなモノづくりに関するワークショップなど、イベントも多数開催される可能性を模索する布の芸術祭を開催しています。このイベントをきっかけにデザイナーやアーティストが富士吉田を訪れ、布を買うという動きが出てきて、こちらもコミュニティに育ちつつあります。

— スタートアップを対象としたピッチやアクセラレーション、アートやデザインのアワードにも関わっておられますね
諏訪 例えば、パナソニックが2018年に100周年を迎えるにあたり「次の100年をつくるイノベーティブな研究や人材を育てるプログラムをつくれないか」と相談され、「100BANCH」というプロジェクトを、施設の物件選びから担当して、5年間運営していました。
このプロジェクトでは古いビルの1階から3階を活動拠点として、「35歳未満のリーダー」という条件でアイデアを公募。各分野のトップランナーによるメンタリングなどを提供する「GARAGE Program(ガレージプログラム)」を実施しました。
こうした場合のピッチは普通、ファンドレイジングが目的ですが、100BANCHの場合は、「お金よりも人のつながりをつくろう」という考えで行い、結果としてここからいろいろな企業が生まれています。例えば知的障がい者の創作したアートを紹介する福祉実験カンパニー「ヘラルボニー」もその一つです。
— ヘラルボニーの展示会は、私も拝見したことがあります。
諏訪 100BANCHのガレージプログラムの対象にはほかにも、家庭用のバイオリアクターを開発し、家庭で藻類や微生物に食品やエネルギーを生成してもらうというユニークなものや、コオロギパウダーを使った「モリノエビチップス」を開発するプロジェクト、着なくなった古着をリメイクデザイン生成AIシステムを活用して仕立て直すプロジェクトなど、CEにつながるものも多数あります。
ほかでは「QWS STARTUP AWARD」を主催し、価値創造を加速させるオリジナルのプログラムを大学や研究機関をはじめとする幅広い領域のパートナーと連携し提供していく「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)」も、僕らが手がけたプロジェクトです。東急、JR東日本、東京メトロと一緒に、渋谷スクランブルスクエア15階にある会員制共創施設「SHIBUYAQWS」の運営を行っています。
loftwork.comも今では、テック系やデジタルクリエイターとの共創を促進するネット上のプラットフォーム「AWRD(アワード)」のベースになっています。これは「クリエイターに必要なのはお金だけではない」という考えからです。アワードには、審査員を務めるオーソリティのFame(名声)を、まだ無名の若いクリエイターに受け渡す機能がある。その世界の権威から認めてもらうことで、受賞者自身にも権威が与えられ、いい仕事を新たに得ることができるようになるんですね。
今はお休みしていますが、FabCafeでも2012年から、「YouFab Global Creative Awards」という、環境、社会、経済、政治などのさまざまな時事問題をデザインで表現するアワードの運営を手がけています。


— FabCafeが主催するアワードには「crQlr Awards(サーキュラー・アワード)」もあります。これはどういった経緯で立ち上がったものですか。
諏訪 FabCafe Globalのチーフコミュニティオフィサーとして世界のFabCafeを束ねてくれている、アメリカ人のケルシー・スチュワートがサステナビリティに強い関心を持っていて、彼女を中心としてエシカルなコミュニティが広がっていったのです。それを見て、「そんなに強いパッションがあるのなら、サステナビリティについてのグローバルなアワードをつくらないか」と提案しました。
結果、彼女がチェアマンとなり、循環型経済に必要な「サーキュラー・デザイン」を考えるコンソーシアム(共同体)である「crQl(r サーキュラー)」が創設され、サーキュラー・アワードが開催されることになったのです。サーキュラー・アワードはCEの実現に向けた大規模なプロジェクトから、計画中のアイデアまで幅広く選考対象としており、今年で3年目ですが、毎回、海外からも多くのプロジェクトが応募してくれます。
— 海外とのつながりは、どこから生まれたのでしょうか。
諏訪 まず、僕らは世界各国のFabCafeに集まるクリエイターと一緒に活動しているので、彼らが応募してくれるということがあります。またアワードに応募するプロジェクトについては、僕らからも世界中を探して声をかけています。
サーキュラー・アワードでは毎回10人近い、サステナビリティの世界トップレベルのオーソリティたちに審査員になってもらっており、そこからも新たなネットワークが生まれています。
昨年は、世界的に有名な建築家であるデイヴィッド・ベンジャミンも、審査員を快く引き受けてくれました。さらにそれだけでなく、「自分が教えているコロンビア大学の学生を連れて日本でサーキュラーデザインツアーをしたい」と希望され、僕がお手伝いをして、「ごみゼロの町」として世界的に有名な徳島県上勝町や、ヒダクマに連れていきました。
—「YouFab」やサーキュラー・アワードでは、これまでにどんなプロジェクトが受賞しているのですか。
諏訪 例えば「YouFab Global Creative Awards 2021」でグランプリを受賞した、「土を食べる」というアートがあります。
オランダのMasharu(マシャル) Studioによる、40カ国以上から集めた約500種の土食のサンプルやそれにまつわる情報をまとめた移動式博物館「the Museum of Edible Earth(食べられる地球のミュージアム)」です。
創設者のマシャルさんは受賞後、FabCafe TokyoとFabCafe Kyotoで展示とワークショップを行ったのですが、そこでは、サハラ砂漠の砂など、世界中の土や石が標本のように並べられ、参加者はそれを試食しました。毒のないものを選んであるのですが、そうはいっても土ですから当然、まずいです。全部まずいのだけれども、今までにない“味覚から見える景色”が感じられる、そういう企画です。
このような試みをどう評価すればいいのか難しいのですが、企業のCDO(チーフデザインオフィサー)クラスの人や審査員などは皆さん、非常に面白がりますね。「技術的にすごい」とか「新規事業にできる」というものではないけれども、「面白いから食べてみて」と言われて食べてみたら、そこから感じられる何かがある。そういう刺激は、企業内だけでは生まれようがないものです。
ほかにも「WoodSpirits(ウッドスピリッツ)」といって、「木からお酒を造る」という日本のユニークなプロジェクトや、イタリアのデザイナーとイギリスの研究チームによる「ペットボトルにも使われるプラスチックをバクテリアや酵素で分解、バニラエッセンスの化合物を生成し、それでアイスクリームをつくる」という研究などもあります。
ワークショップを企画して、木から造ったお酒とペットボトルからつくったアイスを並べ、企業の人に「食べてみませんか」と声をかけると、おそるおそるながら食べるでしょう。それによって彼らのサービスやプロダクトがどう影響されるのか。そんな楽しいアプローチもできるのではないかと思っています。

「t h e M u s e u m o f E d i b l e Earth」は、2021年のグローバ
ルクリエイティブアワード「YouFab」でグランプリを受賞。FabCafeでは、土食を通して無生物と人間との関係を考えるワークショップを開催

日本ならではのサーキュラー文化とは
— 御社の今後のビジョンや活動予定について、お聞かせください。
諏訪 そうですね。「常にクリエイティブなコミュニティとともにあって、そこからプロジェクトが広がっていく」というロフトワークのスタイルは、今後も変わらないと思います。
ロフトワークやFabCafeからは、今もいろいろな試みがグローバルに広がっているのですが、僕自身がコントロールしているわけではありません。ただその中で、サステナビリティは避けては通れない要素で、今携わっているプロジェクトもかなりの部分にそれが入っています。
— CEやSDGsといったコンセプトは海外から来たものですが、それ以前から日本ではリユースやリサイクルの理念、「もったいない」精神がありました。それからすると、日本独自のサーキュラー文化や、サステナブルな循環のやり方も考えられるのではと期待します。
諏訪 僕もそう思っています。どうも日本人は「自分たちは全然できていない」という自虐的な見方をする傾向があって、常に世界のトッププレイヤーと自分たちを比較してしまいがち。そして「日本はだめだ」となるのですが、僕などは「けっこう頑張っているじゃないか」と評価しています。ヒダクマの取り組みもそうですよね。
日本には100年以上続いている企業がたくさんある。そういう企業の経営者の大部分は、「さらにもう100年事業を続けるぞ」と努力しています。今年の数字、今現在の数字も大事だけれども、「自分たちはサステナブルである必要があり、時代に応じて変化していかなければならない」と考えているのです。
ただ日本企業は、自分たちがやっていることを世の中に伝達するのが下手。この点、海外の企業、例えばパタゴニアなどは、数字を挙げられるような定量的な活動はそれほどやっていないのに、エシカルな企業として世界的に有名です。それは「コトづくり」が上手だからだと思います。
— 既存の価値感からの転換や行動変容を促す、デザイン思考ならではの発想を挙げるとしたら、どんな言葉になるでしょうか。
諏訪 「Bricolage(ブリコラージュ)」という言葉があります。フランスの文化人類学者クロード・レヴィ・ストロースが提唱した、「手元にある所与のものを使って、新たなものをつくっていく」という概念です。
手元にリソースが何もないものについては、企業は手を出すことができません。ロフトワークが「半導体をつくりたい」と思っても、何のリソースもないので無理です。経営とは元来そういうもので、手持ちのリソースを組み合わせて新しいものをつくっていくのです。
そういう意味では、例えば障がい者を応援するようなプロジェクトを考えたとき、ヘラルボニーのような組織が近くにあって、必要があれば相談したり、組むことができるということは、それ自体に価値がある。
法人にも人格があって何を大切にするか、目標はそれぞれ違います。それぞれの企業にその会社がやりたいことがあり、ビジョンがあります。それを見つけて実現したり、未来への夢を語っていくことも、サステナビリティを広げていく上で大切なことではないでしょうか。
— 生活者もそうですが、企業がCEを実践しようとする場合、どうしても「○○せねばならない」という感覚にとらわれがちです。
諏訪 日本企業でよくないのは、何かにつけ数字で語れる定量的な結果を目指してしまいがちということです。 物事には定量的な面と定性的な面がありますが、日本企業の、特に中間管理職の人たちなどは、「数字が残るプロジェクトでなければ、会社としてやる意味がない」という思い込みがあるようです。
「CO2削減目標5%」というのは定量的な目標。これを達成しようとすると、コンサルティングファームなどの方たちが企業内のCO2発生源を調べ、「どこでどれだけ削減すればいいか」といった計画を立てるでしょう。しかし、僕らは定性的なアプローチを志向しています。例えば企業のCDOを飛騨の森の端オフィスに連れていって、森の木が木材として循環し、狭い範囲内で高い付加価値を獲得していく様子を見せたりします。すると皆さん喜んでくれますよ。
誤解されないよう付け加えると、僕は何も「定性的なものだけがいい」と言っているわけではない。定量的なアプローチも定性的なアプローチも、両方とも必要だということです。絶対的なCO2排出量の削減は、もちろん重要です。ただ、レギュレーションを追いかけるだけでは数字合わせになってしまう。サステナビリティ報告書をつくることが目的化してしまっている企業もあると聞きますが、それでは不毛でしょう。
— 企業や立場、人によっても感覚が違っているわけですね。
諏訪 2021年の「7Days Challenge」という積水ハウスのプロジェクトでは、エシカルをテーマに「7日間なんでも好きにしていい」という条件で、3組のクリエイターにモデルハウスに住んでもらい、それをみんなで見るという企画を立てました。
定量的な目標は何もありません。3組はリフォーム現場から出た廃材をアップサイクルして使ったり、古着をタマネギやアボカドの皮で染め直したりしました。このプロジェクトを見た人にアンケートを取ったら、ある、まじめなメーカーの担当の方などは、「全然定量化されていない。これでは何もわからない」と怒った様子で書いてこられました。一方で同じ会社の役員の方は「これはすごくいい。そうなんだよね、こういうのをやらなきゃだめなんだよ」などと書いていたりします。
日本企業でも経営陣には「自分たちは今後、どこに向かうべきなのか」という目線で会社を見ている人が少なくない。そういう視点からすると、日本には立派な経営者、立派な企業が多いと思いますよ。

〈註釈〉
*ポートフォリオサイト「loftwork.com」は現在ではAWRD(https://awrd.com/)に受け継がれている。