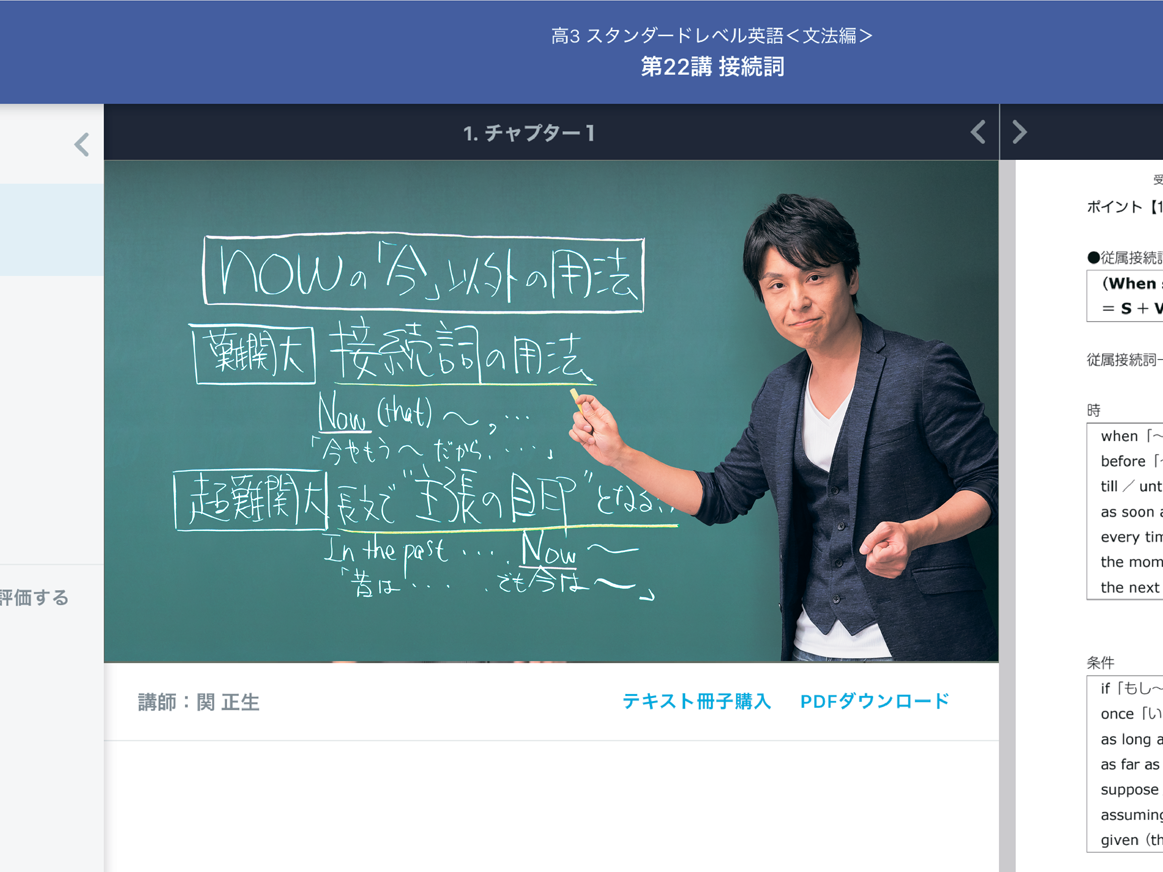センス・オブ・ワンダーを忘れない
― 福岡先生は研究者という「一生学び続ける」最たる職業に就かれています。そこに至る経緯やきっかけについて、改めて簡単にお聞かせください。
福岡 何か一つ好きなことがあって、それをずっと好きであり続けさえすれば、それが私を、あるいはその人をずっと一生、支え続けていくというふうに思うわけです。
これは私の著書の『ルリボシカミキリの青』という本のプロローグにも書いた「ナチュラリスト宣言」です。私は昭和の真ん中に生まれました。まだ携帯電話もインターネットもありませんでしたので、身の回りの自然に興味を持つようになりました。どちらかというと、あまり友達がいない内向的な少年で、いつも下ばかり見て歩いていて、地面にいる虫に興味を持つようになりました。私がもう少し外向的な少年でいつも上を向いて歩いていたら、天体少年になっていたと思います。
いずれにしても人間よりも自然に興味があったわけですね。自然の美しさとか、精妙さは、やっぱりデザインやイマジネーションの無限のリソース。人間の文化のリソースは自然にある、というふうに私は考えています。
そして私は「知ることよりも、まずは感じることのほうが大事だ」といつも言うのですが、それは「センス・オブ・ワンダー」という言葉で象徴されること。環境問題に最初に警鐘を鳴らしたアメリカの女性科学者で、1960年代に『沈黙の春』という本を書いたレイチェル・カーソンの言葉です。センス・オブ・ワンダー、つまり「自然の精妙さに驚く気持ちこそ、すべての子どもにとってのあらゆる出発点である」というふうに彼女は言っています。
私もそのとおりだなと思い、自分の子ども時代を振り返ってみると、まずは蝶々とか、カミキリムシの色の美しさというものに魅了されました。それから蝶々だったら、昨日まで芋虫だったものが急にさなぎになり、そのさなぎから10日もすると劇的な形で成虫の蝶が飛び出してくるという変化の精妙さ、そういうものから生命っていったい何だろうな、「What is life?」という素朴な疑問が心の中に芽生えました。その問いを、生物学者になった今も問い続けているのだと思います。
原点が新たに“かえる”
― しかし、学びの原点となるような体験をしても、その時の新鮮な感動を失わずにいることは、人によっては難しいかもしれません。先生はなぜ、ずっと持ち続けることができたのですか。
福岡 私にとって生命の問題を考えるのは、非常に小さくて細い穴をずっと掘っているようなもの。あるいは細い坂道を上り続けている、と言ってもいいかもしれません。自分の好きなこと、知りたいことについて、その穴を掘る。あるいは狭い道を上っていくと、上っていった場所でしか見えない次の疑問というか、次の風景、光景が見えてくる。新しい扉がそこで開かれるわけです。すると、またそこから上っていく、掘っていく。そういうふうに問いというのはその場所に到達すると、向こうからやってくる。そして、その問いをまた追いかけていく、というように次々と新しい扉を開いては進んできたと思うんですね。
それは結局、たやすい道でもなく、非常に孤独なのですが、私にとってはその道を進むしかできなかった。そしてこのようになりました。人間の人生を見てみますと、外部からさまざまな刺激を受け、子どももそのうち色気づき、楽しいことが周りにあふれてきます。特に今日はネットからあらゆる情報が得られますし、ゲームやほかの刺激も多いですから、そっちの方向に関心が向いてしまって、自分のセンス・オブ・ワンダーを忘れがちになってしまう。そんな文化的状況があるのは確かだと思います。けれどもやはり、自分が初めて興味を持ったことを大切にし、自分の原点は何か、いつも問い続けることが重要なのではないでしょうか。
― すると先生は、子どもの頃に虫を見てわくわくした経験が原点となり、そこにいつも立ち返っていらっしゃるのですか。
福岡 はい、まさにそれを心がけています。そしてその原点に返ると、またそこから“かえる”ものがある。原点に「返る」は「Return」ですが、もう一つの原点から「かえる」というのは卵がかえる、「Hatchする」というような意味です。成長するにしたがって自分の原点に戻ると、そこで新しいものがまたかえる、原点の卵が違う形で返ってくるのがわかるわけです。
原点に返るというと、少しノスタルジックというか、自己愛的な面ももちろんありますが、単に懐かしく振り返るわけではなく、原点に返ってこそ新たに生まれ出るものが、その時々であり得るというふうに私は思っています。
子ども時代こそ創造のベース
― 先生の子どもの頃の“観察のエピソード”が著作に度々登場するので、それが学びの原点かなと思っていましたが、原点がまた新しいものを生み出すHatchのような役割をしているとは驚きです。
福岡 子ども時代は「大人になるための準備期間」みたいによく言われますが、必ずしもそうではありません。準備期間というより、そのこと自体に意味があると私は思っています。
というのも、これほど長い子ども時代があるのは人間、ホモサピエンスだけなんです。子どもと大人の生物学的な違いは、それは非常に単純なことで生殖行動ができるかどうか、でしかないわけですね。だから生物は子ども時代、あるいは幼虫時代、幼獣時代から、生殖行動ができる大人に向けて一直線上に成長していきます。つまりエネルギーをどんどん取り込んで成虫や成獣になるわけです。
しかし私たちだけは長い十数年にわたる子ども時代があり、そのあと急に第2次性徴が起き、成熟します。子ども時代がフラットで長い生物は、ほかにいません。その理由を考えると、実は“子ども時代が長いがゆえに、ヒトはヒトになった”というふうに私は考えています。つまり、ヒトがつくる社会や文化は、すべて子ども時代の体験や経験に基づいてつくり出されているものだといえるのです。
大人になって、すべての行動が生殖に結びつくよう規制される状況に置かれると、すぐに世知辛い生存競争にさらされます。必ず縄張り争いが起きたり、雌をめぐる雄の争いが起きたり、食料の取り合いが始まります。
一方、子ども時代は生殖から切り離されているので、むしろ競争よりも遊び、闘争よりも発見や気づきのようなものが尊重される時代。誰もがとても個性的です。そのときに世界のことをどんどん知り得るわけです。
だから子ども時代は、大人よりもずっと五感が鋭くできている。よくものが見え、聞こえ、においにも敏感だし、あらゆる知覚が研ぎ澄まされています。そこで見いだした原点を、常にリファレンスに持っているということが、大人になった後、学びの上でも豊かな人生を過ごす上でも、とても大事なことじゃないかなと私は思っています。
プロセスの大切さ
― 子どもの頃、学校は先生にとってはどんな場だったのでしょうか。
福岡 私にとって学校は、あまり楽しい場所ではありませんでした、端的に言えば(笑)。というのも特に日本の学校には、先生が笛を吹いてみんなを整列させるみたいな、そういう古い盲動というのが、わりと残っていますよね。それは私のような孤独な昆虫少年にとっては、自分の行動や内心の自由を侵害したり、束縛したりするものが多かった。ですから、あまり楽しい思い出はありません。
ただ一方で、学校はこれまで人間が築いてきた文化を系統立てて学べる場でもあるわけです。だから勉強すること自体は楽しかったし、その場の一つに、例えば図書室があって、そこには自分の知らない本がぎっしり並んでいる。そういう意味のリソースとして、学校は私にとっても貴重でした。コミュニケーションを育む場所としては、どちらかというと苦手ではありましたが、これは私の特殊な傾向によるもの。あまり皆さんの参考にはならないかもしれないですね(笑)。
― コミュニケーションがあまり得意でないと言いながらも、先生の著書は生物学を軸に芸術や文学など、幅広い範囲に広がり、ファンも多くいらっしゃいます。自身の興味を深く掘り下げることから、ジャンルを超え、広く活動されるようになったのは、どのような理由からですか。
福岡 私は自分の好きな生物の謎の究明を続ける中で、個人的な営みとして研究や勉強、調べものなどを楽しんできたわけです。おかげで、引き出しがいっぱい増えました。そしてそこには、好きなものが一つずつ仕舞われています。私自身、忘れているようなものも数々ありますが、どれも少年時代からずっと読んできた本や、自然を観察してきたことで知り得たもの。ほかの人には石ころにしか見えなくても、私にとって宝物なのです。
それを時々取り出して楽しむ、というのが私の研究人生だったのですが、たまたま10年以上前に書いた『生物と無生物のあいだ』という本がありまして、これは生物学の科学史と自分の研究史、自分史を重ね合わせたような本ですが、これが著者の想像を超えてベストセラーになった。そのおかげで、いろいろな方がいろんな依頼をしてくださるようになり、そうして作家になったというか、世界が広がりました。私がこれまで学べてきたのは教育や社会のおかげでもあるので、ちょっとした恩返しのためにも、私の学びの体験をフィードバックするという意味で、執筆活動やメディア活動を行っています。
― 『生物と無生物のあいだ』は昨今、コロナ禍でまた再注目され、とても売れてますね。
福岡 そうなんですね。また重版がかかってしまいました(笑)。ポストコロナの生命哲学みたいな感じで、また読まれているのかなと思います。
― 先日も書店の目立つ場所に平積みで置かれていて10年以上前の本と思えない感じでした。読ませていただくと時代性というよりは、そもそも何を考えなくてはいけないかとか、何が大切なのかという点にすごく迫っていて。科学が苦手な人にもわかった気にさせてくれて、イメージが湧く本だなというふうに思いました。
福岡 それは著者としては、とてもうれしい感想です。
― ある経営者の方が、「『生物と無生物のあいだ』は経営を考える上で参考になる」とおっしゃっていました。またチーム運営のお手本として愛読されているサッカーの監督もいらっしゃっるなど、ジャンルを超えて多くの方に受け入れられています。専門的な内容を一般の人にもわかりやすく伝えるために、先生が執筆の際に意識されていることは何かあるのでしょうか。
福岡 あります。それは非常にシンプルなことで、先ほどから申し上げている“自分の原点を大切にする”ということなんです。つまり研究や学問を続けていくと時間とともに当然、知識が増え、見方も広がり、全体が見渡せるようになります。山の上に登って眺望が開け、いろんなことのつながりとか、風景がよく見えて全体の地図が頭の中に入るわけです。その高みに立って、ほかの人に語ろうとすると、文字どおり、どうしても上から目線になってしまう。
そんな著者が忘れてしまっているのは、自分が登ってきた道すじが何だったか、どうやって、このことを理解できたのか、これは実はこういうことだったんだ、といった学びのプロセスです。それを忘れて、つい、例えば「ミトコンドリアは細胞の中にあってエネルギーを生産している工場である」みたいな教科書的な定義や構造を優先して、語ってしまいがちなんですよね。
でもこれから学んでいく者にとっては、そういう定義からいきなり入ってこられても困るわけでして、まずは疑問があり、その疑問が段々に解かれていくプロセスがとても大事なのです。それは個人の学びの歴史であると同時に、人類全体の発見の歴史でもあるわけで、そういうプロセス、つまり自分が学んできた原点とその道筋を忘れないように努め、それに沿って書けば、それは普通の人にも自然と通じるようになる。
だから、いまの例で言うと「ミトコンドリアとはこれこれこういうものである」ではなく、「今から100年前に顕微鏡で細胞を見た人が細胞の中に、なぜか、わからないけれども糸くずのようなものが見えたので、それを糸という意味の『ミト』、それから粒子という意味の『コンドリア』から名前を付け、これは何だろうな、と思ったところから研究が始まった」というふうに書いていかなければ、読者と一緒に山を登っていくことはできないわけです。そういった書き方をいつも心がけています。
― 「プロセスを大事にしている」とおっしゃったのですが、そのために先生はまめに記録を取ったりされているのでしょうか。
福岡 そうですね。私はわりとメモをたくさん書きますし、日記というほどでもないですが、今日、何があったみたいな記録は付けています。そして何よりも自分が学んできた原点にいつも問いかけ、「あのときはこれをこういうふうに勉強したな」などと思い返しながら、行ったり来たりして物事を考える習慣ができている。だから自分が学んできたプロセスが、いつも自然と問い直されているように感じます。
― 時間の経緯を大切にされていることがよくわかりました。大学で授業を行う際も、わかるまでのプロセスや時間の経過というのを大事にされてらっしゃるのですか。
福岡 そのとおりです。学問にとって時間の経過は、学問の成果というよりも研究の歴史です。だから生物学を教えるなら、必ず生物学史を教えるようにしています。数学的なことを教えるときには数学の歴史、数学史を教えています。
例えば日本の学校では、微分積分とはこういうこと、方程式はこう解きます、とテクニカルなことをどうしても教えがちです。受験対応で演習形式になるのは仕方ない面もありますが、それはそれとして微分積分という考え方が生まれた17世紀には、居ても立ってもいられず、それを生み出さざるを得なかった人たちの切実な求めというか、希望、希求があったわけですね。
例えば、大砲を撃つと、それがいったいどの程度の距離を飛んでどこに落ちるか、計算で求めたいという需要から微分積分が、また土地の争いのとき、全部の距離がわからなくても一部の距離から正確な面積を割り出したいといった要求から三角関数が、それぞれ作り出されたわけです。つまり人間の文化史、社会史あるいは科学史を知らなければ、本当の学びはできません。
ですから知識をどんどんため込めば物知り博士にはなれますが、教養人になりたければ、自分の中に時間軸を持たなければ知識や学びは深まらない、というふうに私は考えます。
― 確かに、中には「これを学んで何の役に立つのだろう」と疑問を抱く学生もいると思います。しかし微分積分が、17世紀に自分の国が滅びるかどうかの瀬戸際に、必要に迫られ生まれたものだと知ると、学びへの姿勢もずいぶん変わるかもしれませんね。
福岡 そうなんです。「これを勉強して何の役に立つのか」という問いは、小学生から大学生まで、多くの人が持っています。それは操作ばかり教えるからなんです。微分積分や因数分解の方法や操作は、専門家、あるいは今はコンピュータに任せられる。だから操作自体を習熟する必要はないんですよ。
でも、そのアイデアが人間の歴史の中でなぜ生まれたのか、文化的・社会的背景については、経営者でもエキスパートでも、教養人である以上は知っておくべきです。でなければ、未来を切り拓いていく新しいことなど何もできない。そういう点で勉強はとても大切で、意味があるわけです。
アルゴリズム的から動的平衡へ
― 大雑把な質問で恐縮ですが、現在の教育や学びの状況において、先生が思うこと、違和感を感じていることなどあれば、ぜひお聞かせください。
福岡 私は「福岡博士」といわれているぐらいなので博士号を持っていて、博士号は英語ではPh.D.と書きます。Ph.はPhilosophy、つまりDoctor of Philosophyという意味なんです。Philosophyは哲学なので、すべての学問の基礎に哲学があるわけで、哲学を持たないことには、本当はどんな学びも成立しない。それほど哲学は大事で、すべての学問の背骨になっています。
また哲学というのは、その時代時代で求められる形が違ってきます。現在は、特にこのコロナウイルスが突然襲ってきて、世界中が大混乱して経済も止まり、本来、人間にとってとても重要だった密接な関係やコミュニケーション、あるいは移動の自由といったものが制限されている時代です。そんなとき、PCR検査も手を洗うことももちろん必要なのですが、一番求められているのは、実は「ポストコロナ時代の生命哲学だ」というふうに私は思うわけですね。
じゃあ、どういう哲学が必要かというと、これは結論がすでにあったり、手っ取り早く1、2行で言えることではありません。哲学というのは、それを求め、語るのに長い時間がかかるし、それぞれが考え、自分自身の言葉で言い直さなければ、本当に納得することはできないわけです。しかし大まかには、その方向性は次のように示せるのではと考えています。20世紀から21世紀にかけては、情報、あるいはアルゴリズム的なものが大変注目されてきた時代です。AIの進化などはまさにアルゴリズム的な考え方で「すべてを最適化していき、それに従って効率よくいきましょう」という社会理念みたいなものが、時代の哲学だったわけですね。
でも、それがコロナのようなある種の自然災害を目の当たりにして、もろくも崩れてしまった。それはつまり、「生命のあり方は、本当はアルゴリズムに従って最適解を求めていくような方法ではないのでは?」ということを、私たちに問いかけているように思うわけです。
じゃあ、何が大事なのかというと、自然全体のつながりやバランス、私の言葉で言うと「動的平衡」というもの。自然の中では、個々の生命体や違う種が生存競争をしているように見えるけれども、実は常に協調し共生的に存在し、あるいは互いに助け合う相補的な関係にあって、全体としてつながっているわけですね。
コロナウイルスも病気をもたらす危険性はありますが、自然の中の一員として存在価値があるからこそ、他の生物とこれまで共存してきたわけです。それは、遺伝子を水平に運ぶ“運び屋”としての役割です。普通の生殖だと親から子、子から孫と垂直にしか遺伝情報は伝わらないところ、ウイルスは横糸のように動けるため、進化の中で役に立ってきたのです。だからウイルスを世界から抹殺することなど不可能で、ある種のリスクを受容しながらも、共存していくしかない。そういうふうな生命の見方、自然観というのが求められています。これがまさに哲学なわけですね。
生命というのは利己的よりも利他的、つまりほかを利するように行動します。すべての生物は利己的に振る舞うのではなくて、必ず周りの生命体と協調したり、共生・共存したりしながら、自分のつくり出したもの、生み出したものの余剰を、常に他の生物に分け与えながら生存しているわけです。
その最たるものは例えば植物で、植物は葉を繁らせ、実や穀物を実らせますが、それは必要以上に生産してくれているわけですね。植物が自分に必要な分しかつくらなかったら他の動物を含め、あらゆる生物は生存できません。けれども植物が非常に利他的に、過剰に振る舞ってくれているので、他の生物が生存でき、そして他の生物もまた常に利他的に振る舞うことで、全体としてこの動的平衡の網目がより強靱になっているのです。だから私たち人間も、利他的に生きるということを改めて、考えなければならない。
利他的というのは「100持っているうちから10を寄付しなさい」といった、自己犠牲によったものではありません。90しかない人は、とりあえずは与えない。自分自身が精いっぱいなので与えなくていいんです。100ちょうどの人も与えなくていい。でも、たまたま110得られた場合は、その余剰分の10を誰かに与えましょう。何らかの工夫や技術の発展や幸運によって100以上得られる生命体は、必ずどこかにいます。そういった生命体が、自分の余剰を他の生命体に与えるわけです。
そして、誰かがずっと勝ち続けることはなく、いつも負け続けているわけでもない。常に利他的に振る舞えば自分が困ったときに、ほかから援助してもらうことができる。そういう成り立ちによって生命は存在しているのです。このように“利己的遺伝子から利他的共生”というふうに哲学も変化が求められてくる、と考えています。私もそれに基づき、この動的生命論という考え方、自分の生命観というのを、さらに深めていきたいなというふうに思っているわけです。
― 「生物は利他的関係性の上に成り立っている」という言葉から、以前聞いたお坊さんの話を思い出しました。
福岡 そうなんですよね。私はよくお坊さんに好かれるんです(笑)。仏教的な“袖振り合うも他生の縁”というか、縁起みたいな考え方は「それぞれの要素よりも、その関係性が大切だ」という、ある種の東洋思想であり、動的平衡の考え方も確かにそれに重なる部分があります。でも別に仏教をもとにしたわけではなく、キリスト教や他の宗教にも利他性というのはあるので、人類共通の原理だというふうに思っています。
― 最後に今後の先生の研究やコミュケーション活動について、差し障りのない範囲で教えていただけますか。
福岡 実は、2025年に開催される大阪・関西万博のプロデューサーの一人に選ばれました。そのテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。「テーマに沿ってパビリオンや展示を考えてほしい」と、日本国際博覧会協会からミッションを受けています。
そして、やはりここでも、ポストコロナの生命哲学というものが求められているんじゃないかなと感じており、その方向で提案をするつもりです。それは先ほどの繰り返しになりますが、20世紀のアルゴリズム的世界観や利己的遺伝子から、利他共生という生命観への転換です。
それも含めて、今後、さらに私の研究課題である「動的平衡論」を追求し深めることで、生命が互いに助け合って成り立つ関係性「利他」というイメージを、もう少し世界に広めていきたい。そのためにもいろいろな情報を、僭越ながら発信し続けられればと思うのです。