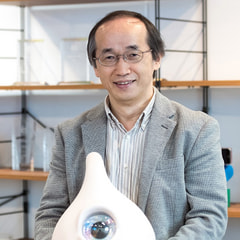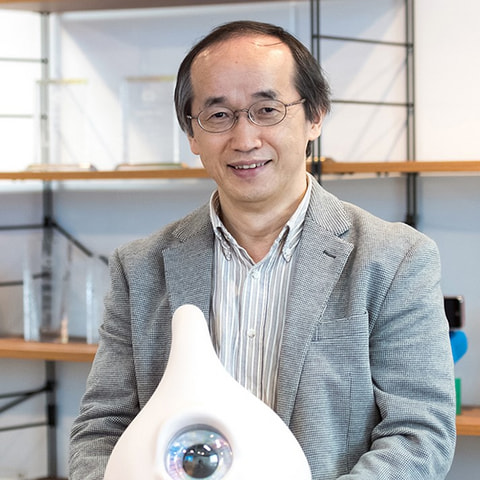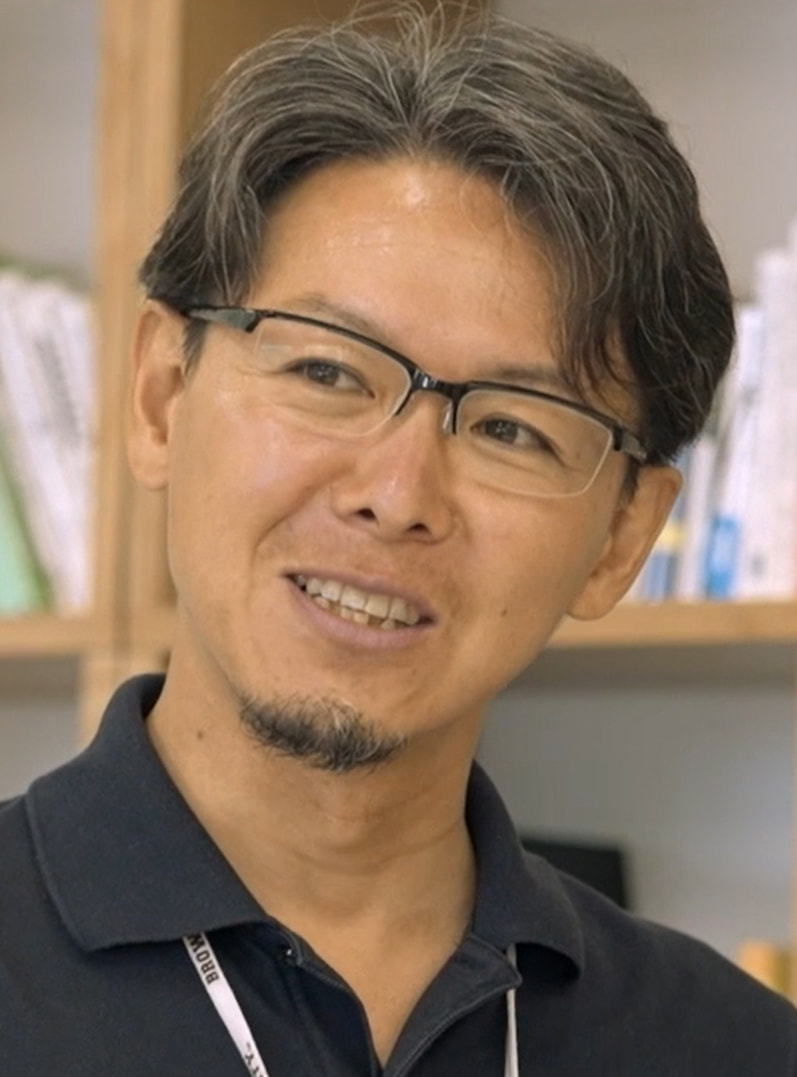わたしたちの「機械」に対するイメージとは、どのようなものか。「何も手を貸すことなく、すべてのことをやってくれるもの」と、そんな風に捉えられてきたように思う。洗濯機、食器洗い機、お掃除ロボットもしかり。厄介な仕事から解放してくれて、自分の時間が持てる。それはとても便利なことであり、わたしたちに幸せをもたらしてくれると。
そのためか、人は「もっと、もっと」と機械に高機能・高性能を求め、そうした期待を受け、多くの技術者、研究者は、その技術や機能の「隙間」を埋めようとしてきた。その意味で、従来の技術開発のスタイルの多くは、新たな機能を追加していく「足し算型のデザイン」であり、ドナルド・ノーマン(1)などにより「なし崩しの機能追加主義」と呼ばれてきた。
ただ、このところ、その風向きも少しずつ変わってきたように思う。多くのことを機械にやってもらうのもうれしい。けれども、自分の手を使い、手間を掛けることも意外に楽しい。大量の水と電力を浪費するくらいなら、食後のお皿くらいは自分の手で洗いたいもの。スーパーにあるセルフレジなども、まんまとレジを手伝わされているのだけれど、ピピッ、ピピッと応えてくれるレジとの連携は思いのほか心地いい。ファミレスの中でマゴマゴしている配膳ロボットや部屋の物陰で四苦八苦しているお掃除ロボットの姿などを目にすると、思わず手を貸してあげたくなる。床の上にある邪魔なものを退かせ、テーブルや椅子のレイアウトを変えてみる。一緒に部屋の中を片付けているような気分になって、ちょっとばかりうれしくなるのだ。
利便性だけではない、何か。ちょっと不完全なもの、周りに少し委ねたような、やや「隙間」のあるもの。そんな、ちょっとばかり「ゆるい」機械やロボットたちは、わたしたちの仕事を奪うというより、人の本来の役割や「強み」、そして優しさ、寛容さなどを引き出しているように思われる。これはどういうことなのだろう。
ここ20年ほど、筆者らは「ちょっと不完全だけれど、なんだかかわいい、放っておけない」ような“ 弱いロボット”の研究を進めてきた(2)(3)(4)。自らはゴミを拾えないものの、周りの子どもたちの手助けを上手に引き出しながら、ゴミを拾い集めてしまう〈ゴミ箱ロボット〉、街角で行き交う人にモジモジしながらティッシュを配ろうとする〈アイ・ボーンズ〉、言葉足らずな発話でなんとか今日のニュースを伝えようとする〈む~〉、子どもたちに昔話を語り聞かせようとするも、時々、大切な言葉を物忘れしてしまう〈トーキング・ボーンズ〉など、いずれも周りに機能の一部を開いた、「隙間」のあるロボットたちである。
本稿では、これら「引き算型のデザイン」によって構築された“ 弱いロボット”たちとの何げない関わりを手掛かりに、少しずつ「生き物らしさ」や「人らしさ」を備えつつある機械(=ソーシャルなロボット)と人との新たな関係のあり方について考えてみたい。
素朴な道具から高度に自律した機械へ
ハサミなどの素朴な道具は、いまも絶えることなく、わたしたちの身の回りで活躍している。高度な機械とは違い、こうした道具の面白さは自らの中で完結していないことだ。机の上に置かれたままでは、用をなさない。わたしたちの手の中にあって、初めて紙を切る、紐を断つなどの機能がたち現れてくる。ハサミが備える硬い鋼は、人の手の柔らかさを補うものだけれど、ハサミそのものは自在に動く柔らかな手の助けを必要とし、その柔らかさ(= 弱さ)をむしろ「強み」に変えてくれる。
こうした道具の使用にあっては熟練をも伴う。器用な手の動きにより、ハサミに新たな機能や役割が備わる。と同時に、それを巧みに使いこなす者として、使い手も新たに価値づけられる。このようにハサミは受動的でとても素朴な道具でありながら、それを使いこなす者と一緒に新たな価値を構成し合う、とても生成的なものといえそうだ。
このことはハサミなどの道具に限らず、マニュアル車の運転やカメラの操作などにも当てはまる。初めてクルマのハンドルを握り、アクセルを踏み込んだとき、とてもドキドキ、ワクワクした。すぐに自在に操れるようになり、ちょっとした有能感も覚えた。クルマはわたしたちの身体の一部となり、その機能を拡張してくれた。これはとても幸せなことであり、街と一体になった感覚はとても心地いいものだった。
では、このところの自動運転システムの場合はどうだろう。高速道路などで自分の手を休めようと自動運転モードのボタンを押してみる。すると、自分の身体の一部であったクルマは、そっと自分から離れていき、勝手に動き始める。もはやクルマを自在に操る感覚もなくなり、その操作が上達していくこともない。
自動運転システムの登場は、高齢者や障がいのある方々にとっては福音であり、必要不可欠なものとなるに違いない。交通事故の低減や渋滞の緩和につながることも期待されている。けれども、これまで培った経験や勘も生かせずに、システムの独りよがりな行動に付き合うことになる。ある意味で、わたしたち搭乗者は「荷物の一つ」にすぎない。利便性というモノサシから離れてみると、どこか残念なシステムに思えるのである。
どこでボタンの掛け違いをしてしまったのか。人は頼りにならない、時々、不注意もあればエラーもする。そんな当てにならないものを頼っていてはダメとばかりに、完全無欠な自動運転システムを目指そうとする。しかし、相手に対する信頼を欠いてしまうと、あらゆる事態を想定する必要があり、とかく高コストになりやすい。しなやかな連携も失われ、時々、そのもろさも露呈してしまうことも多い。
一方の搭乗者の心持ちは、どのようなものか。一般に「〇〇してくれるシステム」と「〇〇してもらう人」と、その役割の間に線を引いた途端に、相手に対する要求水準をエスカレートさせてしまう。お互いの間に距離が生まれ、相手への思いやりや共感性を失うためだ。もっと俊敏な動きはできないか、もっと静かに走れないか……。利便性の高いシステムは、わたしたちの傲慢さまでも引き出してしまう。システム側の些細なミスに対しても不寛容になりがちになる。
チキンラーメンの「くぼみ」の働き
上記の自動運転システムなどは、どんどん機能を追加していく「足し算型のデザイン」の典型例だろう。それに対して「引き算型のデザイン」とはどのようなものか。どのような効用をもたらすものなのか。ここでは、チキンラーメンの麺に施されている「くぼみ」の働きについて考えてみたい。
麺のところになぜ「くぼみ」があるのか、ご存じの方も多いだろう。正式には「Wたまごポケット」と呼ばれるもので、生卵を載せると黄身がポケットに収まり、周りの縁で白身をしっかりキャッチしてくれる。なかなかのアイデアなのである。
この「くぼみ」は一種の「ナッジ(nudge)」にすぎず、それをどう利用するかはわたしたちに委ねられている。生卵を載せるだけでなく、きざみノリやネギなど、ちょっとした工夫や手間をかけ、オリジナルな味を楽しむこともある。「今日のは、なんだかおいしい!」「コツもわかってきた!」など、ちょっとした有能感や達成感などを覚えることも。こうした、さまざまなトッピングを楽しんだり、その味をどんどんアップすることができるのも、チキンラーメンのベースにある、しっかりした味付けがあってのことだ。わたしたちの工夫と食品メーカーとの協働のなせる技なのである。
この「工夫したかいがあった!」「なんだか幸せ!」という、ちょっとした幸福感を生み出す上で、「くぼみ」の存在がカギとなっている。生卵やネギ、ノリなどをすべて提供しているわけではない。むしろ、わずかな手間や工夫する「余白」を残している。こうした配慮(=引き算型のデザイン)がわたしたちの潜在的な強みや工夫を引き出し、どこか生き生きとした幸せな状態をもたらすようなのである。
すべてを提供してもらう、あるいは完全に調理してもらうことで「利便性」を選ぶのか、それとも余白を残してもらい、「なんだか幸せ!」な気分に浸るのか。後者の価値観は、利便性や効率性に対して、「ウェルビーイング(well-being)」と呼ばれるものだ。先ほどの「自らの能力が十分に生かされ、生き生きと幸せな状態」も、その一つなのである。
ライアンとデシらの自己決定理論では、ウェルビーイングを支える構成要素として、「自律性」「有能感」「関係性」の3つの要素を挙げている(5)。チキンラーメンの「くぼみ」との関係で捉えるなら、その「くぼみ」を利用するかどうか、生卵を載せるかどうかは、わたしたちの判断に委ねられている(=自律性の担保)。さまざまなトッピングなどの工夫により有能感や達成感などを得ている。加えて、チキンラーメンの味付けとわたしたちの工夫とが相まって(= 関係性)、なんだか幸せな気持ち(=ウェルビーイング)をアップさせていたのだ。
“弱いロボット”の誕生
これまで筆者らは「コミュニケーション研究の道具として、ロボットが使えないものか」との思いで、幾つかのロボットと関わってきた。コミュニケーションの基底となる、わたしたちと同型な身体をロボットの身体に求めようとしたのである。
ロボット技術に関してはほとんど素人であり、これまで生み出してきたロボットは拙いものばかり。子どもたちのところに連れていったところ、その拙さにしびれを切らし、子どもたちがロボットを世話する光景をなんどか目にした。「あっ、弱さには積極的な意味があるのかも……」、こうした経験が“ 弱いロボット”を生み出すきっかけとなった。
さっそく子どもたちの遊ぶ広場に置いて、〈ゴミ箱ロボット〉を動作させてみた。ヨタヨタしながら、子どもたちの近くをうろうろする。にもかかわらず、「なんだコイツは?」「ゴミでも探してるんだろうか……」と、子どもたちの関心や手助けを上手に引き出し、結果としてゴミを拾い集めてしまったのである。
ロボットなどの研究開発では、「こんなことも、あんなこともできる!」と強がってしまうことが多い。ただロボットといえど、まだ不完全なところ、弱いところもたくさん残されている。その弱さを隠さずに、適度にさらしてみたらどうか。人のわずかな手助けがあれば、その可能性は格段に広がるように思われる。一方でロボットの不完全なところ(=「へこみ」)は、子どもたちの優しさや「強み」を引き出すものとなる。「へこみ」は、ほかとの関係性を生み出す「のりしろ」なのである。
社会的相互行為論によれば、他者との間で相互行為を組織するポイントは、「お互いの状態を他者からも参照可能なように社会的に表示し合うこと」という。ロボットに限らず、わたしたちも弱いところ、不完全なところはたくさんある。その弱さを受け入れることで、ロボット側の「強み」を引き出すことも多い。その意味で、人とロボットとの間でも、お互いの「弱さ」を補い、その「強み」を引き出すような、「しなやかな関係」を生み出せる可能性がある。まさに“ 弱いロボット”だからできること、なのではないだろうか。
当初は、他者の手助けを上手に引き出し、目的を果たす(=ゴミを拾い集めてしまう)ような、一種の関係論的な行為方略やその社会的なスキルに着目していた。しかし、フィールドでの観察を続けてみると、ロボットと関わろうとする子どもたちの振る舞いや表情なども見逃せない。「手伝ってあげるのも、まんざら悪い気はしない」と、子どもたちは満足そうに、その世話や手間を楽しんでいる。〈ゴミ箱ロボット〉の拙さ(=「へこみ」)は、子どもたちの「自らの能力が十分に生かされ、生き生きと幸せな状態」も生み出しているようなのである。
ここで、子どもたちは必ずしもゴミを拾うことを強いられているわけではない。それは子どもたちの判断に委ねられている。ゴミを拾ってあげると、ロボットはペコリとお礼のような仕草を返すのだけれど、「ロボットのために、ゴミを拾ってあげる!」という利他的な気持ちがどこまで働いているかはわからない。
新奇なロボットを相手に、ただ遊んでいるだけなのかもしれない。ただ、その姿からは「利他」を超えて、「わたしたち(we)」として一緒に何かを成し遂げようとしているように思われる。手伝えることの喜び(= 有能感、達成感)、ほかの仲間と一緒に貢献できることの喜びのようなもの(=つながり感、一体感)。これらも、子どもたちのウェルビーイングをアップさせるものなのだろう。
“弱いロボット”的思考のすすめ
ロボットに限らず、わたしたちも「一人でできるもん!」といいながら、「だれの助けも借りてはいけない」とばかりに肩ひじを張ってきたところがある。ただ、一人で勝手に歩いているようでも、何げない一歩はしっかり地面に支えられながら「歩く」という行為を形作っている。上手な字が書けるのも、本人の技量ばかりではない。紙と鉛筆の間にある摩擦がわたしたちに上手な字を書かせているのだ。
筆者らの“ 弱いロボット”たちの多くは、日常での何げない振る舞いをなぞろうとする中で生まれてきた。「おはよう!」との日常での何げない発話も、その相手が気づかずに通り過ぎていくなら、その意味は宙に浮いてしまい、挨拶としての意味をなさない。「対面的な相互行為は賭けを伴う」といわれるように、極めて脆弱なものなのである。
(a)ティッシュを配ろうとする〈アイ・ボーンズ〉
街角などで、そこを行き交う人にモジモジしながらティッシュを配ろうとする〈アイ・ボーンズ〉も、筆者らの“ 弱いロボット”の一つである。挨拶と同様に、ティッシュを配ろうとしても、その相手が受け取ってくれなければ、ティッシュを手渡すことにならない。人の動きは殊のほか俊敏で、なかなかタイミングが合わない。ティッシュを差し出そうとするも、うまくいかないとわかるとおずおずとその手を引っ込める。人が近づくのに合わせて、また手を差し出してみる。これを繰り返す姿は、どこかモジモジしているようにも映るのだ。
なんだかかわいそうに思ってなのか、おばあちゃんがそこに立ち止まり、ロボットの差し出すタイミングに合わせてくれた。「手渡す」というより、「受け取ってもらった」に近い。ようやく〈アイ・ボーンズ〉は、おばあちゃんの手を借りるようにして、ティッシュを手渡すことができたのである。
こうした些細なやり取りも、「自らの状態を他者から参照可能なように社会的に表示しておく」ことがポイントとなる。ただの機械ではなく、ヨタヨタと生き物らしさを備えており、ティッシュを配ろうとする意思も感じる。周りの人から「志向的な構え」を引き出すのだ。加えて、「懸命に配ろうとするも、なかなかうまくいかない」ことを隠さない。この愚直さが、周りの人の優しさや「上手にタイミングを合わせることができる」という人の「強み」を顕在化させる。思わず、ロボットとの共同行為に参加しようとしてしまう。
こんな時にも、とてもうれしく感じるものだ。ティッシュを受け渡しするときに、わずかだけれど心を一つにする瞬間がある。ゴールを共有しつつ、そのタイミングを調整し合う。「わたし(I)」と「あなた(you)」との関係ではなく、「わたしたち(we)」として、目的に向かって貢献し合う。これは「we-mode」と呼ばれるものだ。自分の工夫によって目的を果たせた、わずかだけれど心を通わすことができた(ように思える)。ここでの有能感、達成感、そしてつながり感、一体感なども、わたしたちのウェルビーイングをアップさせる要因となっているのだ。
(b)言葉足らずな発話で懸命にニュースを伝えようとする〈む~〉
小学校から帰ってきたばかりの子どもが、今日の楽しかった出来事を懸命に伝えようとする。「今日ね、いっぱい遊んだ!」(えっ、何して遊んだの?)、「お絵描きした!」(へー、そうなんだ。誰と遊んだの?)、「そらちゃん!」(あー、そう。楽しかった?)、「うん」……。
どこか不完全で、言葉足らずなところもあるけれど、聞き手の関心を上手に引き出しながら、一緒におしゃべりを続けてしまう。過不足なく、しっかりと話せる子どもの発話と比べても、むしろ豊かなコミュニケーションを生み出すようなのである。
この例も、自己完結した発話を目指そうとする「足し算型のデザイン」ではなく、むしろ不完全なまま聞き手に半ば委ねつつ、一緒にコミュニケーションを構築しようとする。これも「引き算型のデザイン」、そして“ 弱いロボット” 的な方略といえるだろう。
これまで「自分の伝えたいことは、ちゃんと言葉にしてから!」と教えられてきた。けれども、自己完結した発話は、一方的なものとなりやすく、聞き手の関心を置き去りにしてしまう。その一方で、言葉足らずな発話、「隙間」や「解釈の自由度」のある発話は、聞き手からの手助けに支えられつつも、聞き手の関心を上手に引き込むことができる。話し手の思いと聞き手の関心とが上手に絡まり合って、お互いの気持ちを共有し合うwe-modeの状態を作り上げるのである。
スマートスピーカからの応答は、過不足ないものだけれど、どこかよそよそしい。その発話は聞き手からの支えを予定して繰り出されたものではないようだ。では、もっと聞き手からの支えを予定してはどうか。そんな観点から生まれたのは、今日のニュースを言葉足らずな発話で懸命に伝えようとする〈む~〉である。ちょうど、小さな子どもたちが母親に今日の出来事を言葉足らずな発話で伝えようとする姿をなぞらえたものだ。
(c)大切な言葉を物忘れしてしまう〈トーキング・ボーンズ〉
言い直しや言い淀みを含んだような非流暢な発話、子どもたちの言葉足らずな発話などの可能性を議論する中で、もう一つの“ 弱いロボット” が生まれてきた。子どもたちに昔話を語り聞かせようとするも、大切な言葉を時々物忘れしてしまう〈トーキング・ボーンズ〉である。
「むかし、むかし、あるところにね、おじーさんとおばーさんがいました」「おじーさんは山に柴刈りに、おばーさんは川に……えっとー、何だっけ?」
ロボットが物忘れするというのも妙な話だろう。ただ、「あれっ……」「えっとー、何だっけ?」などと困った仕草をすると、周りの子どもたちは目を輝かせ始める。ある子どもからの「洗濯に行ったんじゃないの」との手助けに、「それだ!それそれ! 洗濯に行ったんだった」「それでね、おじーちゃんはね、川に洗濯に行きました」「すると川の中から、どんぶらこ、どんぶらこと…」「あれっ、えーと、何が流れてきたんだっけ」……。
なんだか頼りないロボットを目の前にして、子どもたちは懸命に助けになろうとする。「何に困っているのか」「何を思い出そうとしているのか」と、ロボットの志向を自らの中に住まわせて、「ああでもない、こうでもない」と考えを巡らす。一方的な語り聞かせに比べても、子どもとロボットとのコミュニケーションはとても豊かなものに思えるのである。
ロボットが淡々と昔話を語り聞かせるだけなら、子どもたちはすぐに退屈してしまうことだろう。このロボットの記憶の不完全なところ(=「へこみ」)が子どもたちの強みや優しさを引き出している。一方の子どもたちにとっても、昔話の中身はおぼろげなものでしかない。子どもたちと〈トーキング・ボーンズ〉とは、お互いの〈不完全なところ〉を補い合いながら、その〈得意なところ〉を引き出し合うような、持ちつ持たれつの関係を作り出すのである。
こうした関わりにあって、子どもたちはとても生き生きしており、幸せそうだ。ロボットを手助けできたこと、一緒になって昔話を思い出せたことを喜んでいたのだろう。
おわりに
「ちょっと弱音を吐くくらいの自動運転システムはどうか」。ある自動車メーカーの技術者に提案したけれど、即座に却下されてしまった。クルマというのは、その機能のみならず、信頼感や安心感を売り物にしており、クルマが弱音を吐いたのでは商売そのものが成り立たないのだ。
ただ、勝手に運転してくれる自動運転システムの素性はよくわからない。高度に自律した機械なのか、それとも生き物のように意思を持った存在なのか。ハンドルから手を離して、自分の命をシステムに預けようとするとき、まだドキドキしてしまう。急に減速をするも、その意図するところが理解できない。いつも強がるだけでなく、自信のないときには、そっと教えてくれてもいい。「じゃ、ここは自分でハンドルを持つよ!」と、その連携もスムーズに行えることだろう。
先に触れたように、他者との間で相互行為を組織するコツは、お互いの状態を他者からも参照可能なように社会的に表示し合うことだ。加えて、自らの弱さを受容し、それを開示する度量を持つこと。完全無欠を目指す自動運転システムに欠けていることの一つだろう。
そうした背景もあって、筆者らの研究グループでは、屋内で動き回る子ども向けのパーソナルビークル〈RunRu〉の開発を進めている(4)。「自動運転システムを一種の“ソーシャルなロボット”にしてはどうか」「いっそのこと、“ 弱いロボット”にしてはどうか」というわけである。ポイントとなるのは、自らの状態を社会的に表示するためのデバイス〈NAMIDA〉、そして自らの中に機能を自己完結するのではなく、むしろ外に開くことで、周りからの手助けを引き出し、一緒に目的を果たしていく「関係論的な行為方略」の導入である。
この〈RunRu〉は、周囲の環境を味方につけ、障害物を避けながら、縦横に動き回ることができる。けれども、「自らの意思を持つ」という点で、その主体性はやや弱い。一方の搭乗者である子どもは、自らの意思を持ちつつも、周りの環境に丁寧に目を配ることはしない。ここで、お互いの「弱さ」を補いつつ、それらの「強み」を引き出し合うことができれば、「人馬一体」と呼べるような、もっと「しなやかな」システムを生み出せる可能性もあるのだ。
人と機械との間で、もっと関係性を回復させてみたらどうか。本稿では、自己完結することなく、むしろ他者との関わりを志向する“ 弱いロボット”たちを手掛かりに、人と機械との新たな関係のあり方を考えてきた。「一人でできるもん!」から、相手に半ば委ねつつ、支え合う関係へ。「あなた(you)」と「わたし(I)」から、「わたしたち(we)」の関係へ。わたしたちとして、一緒に達成できる、貢献し合うことを喜べる、ウェルビーイングを志向し合う関係へ。これらは人と機械との関わりに限らず、いま、わたしたち人と人との関わりに求められていることなのかもしれない。
〈参考文献〉
(1) ドナルド・A・ノーマン(野島久雄訳):『誰のためのデザイン? 認知科学者のデザイン原論』、新曜社( 1990)
(2)岡田美智男:『弱いロボット(シリーズ ケアをひらく)』、医学書院( 2012)
(3)岡田美智男:『〈弱いロボット〉の思考 わたし・身体・コミュニケーション』、講談社現代新書( 2017)
(4) 岡田美智男:『ロボット 共生に向けたインタラクション』、東京大学出版会( 2022).
(5) ラファエル・A・カルヴォ、ドリアン・ピーターズ(渡邊淳司、ドミニク・チェン監訳):『ウェルビーイングの設計論 人がよりよく生きるための情報技術』、ビー・エヌ・エヌ( 2017).
(6) 三宅泰亮、山地雄土、大島直樹、デシルバ・ラビンドラ、岡田美智男:「Sociable Trash Box:子どもたちはゴミ箱ロボットとどのように関わるのか」、人工知能学会論文誌 28( 2), 197-209( 2013).