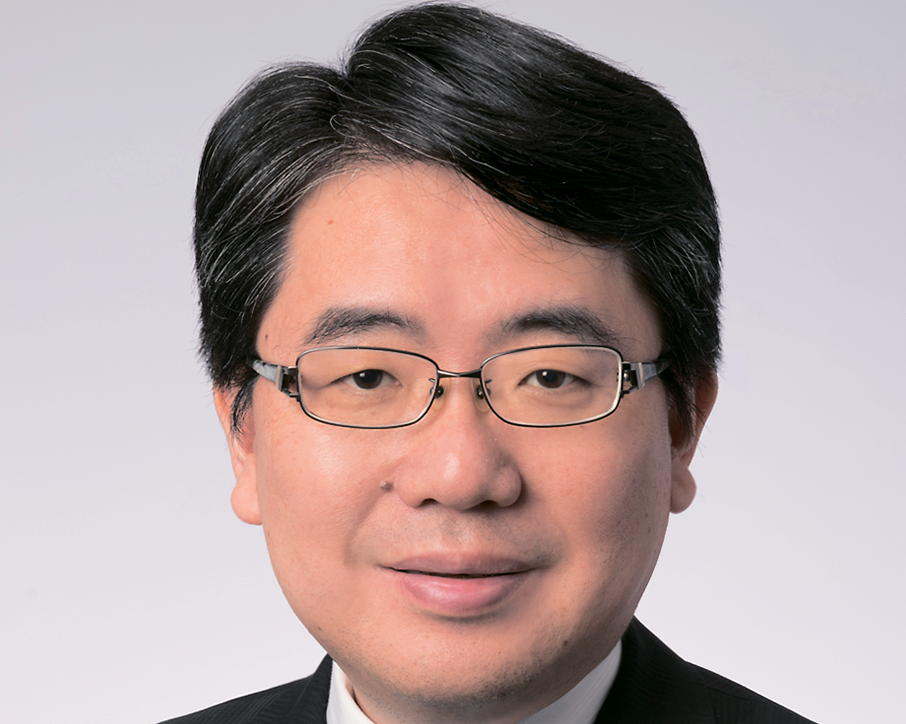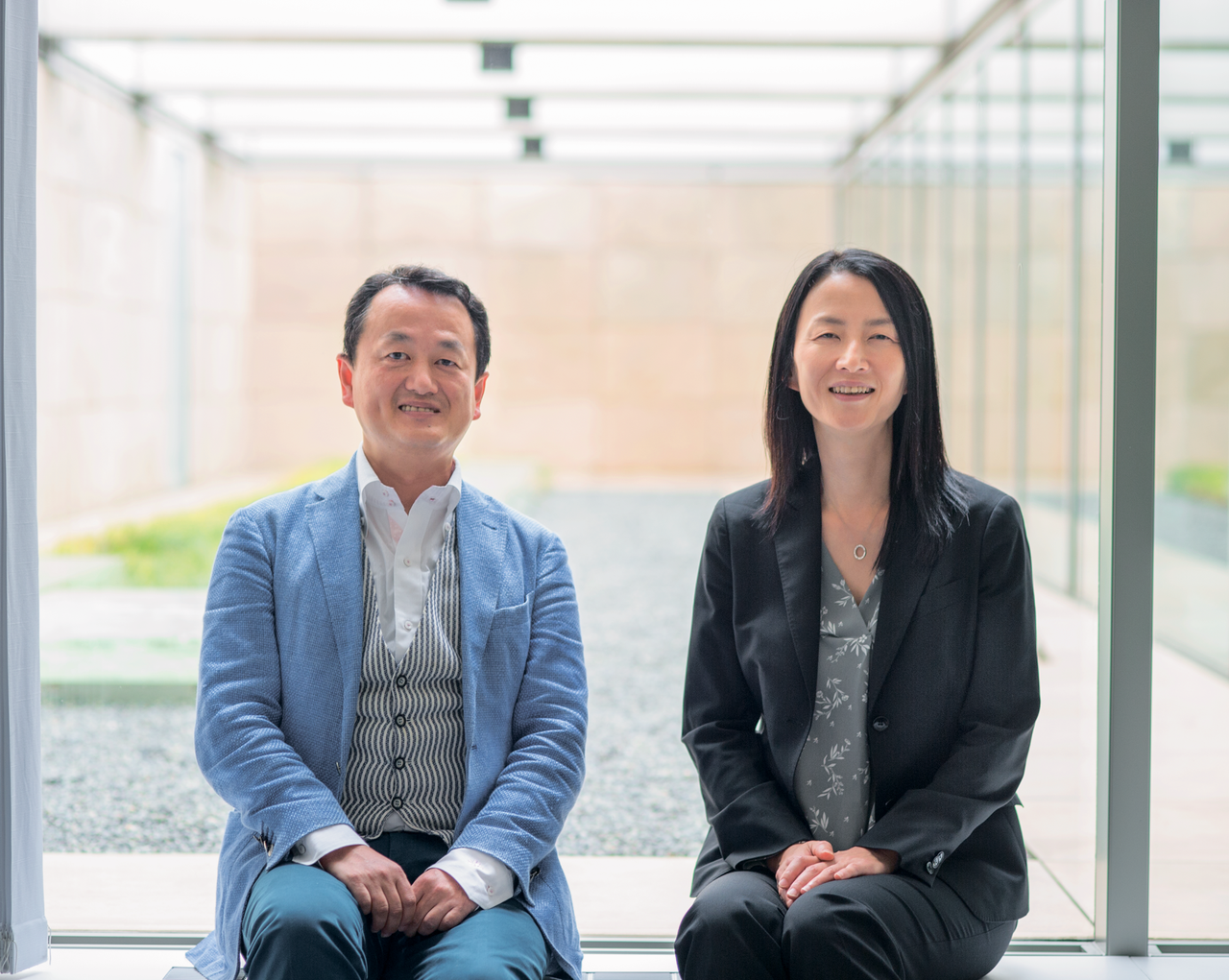デジタル地域通貨でお金を“地産地消”する
― 現在、デジタル地域通貨はどの程度普及していますか。
川田 日本で地域通貨が注目されたのは、2000年前後の地域振興券が最初でしょう。消費税が3%から5%に上がったタイミングで、全国約600の自治体が商品券を配りました。紙ベースでしたが、これは地域限定なので地域通貨の一種といっていいと思います。ただ、結局は地域の経済振興にあまりつながらないまま終わりました。紙ベースは運営コストが約20%かかります。また広告宣伝にもコストがかかる。そのため国の補助金なしでは継続が難しいのです。
いったん下火になった地域通貨が再び注目を集め始めたのは、ここ1~2年でしょう。まずスマートフォンが普及して、デジタルの地域通貨を発行できる環境が整いました。デジタルなら、運用コストの負担は大きく軽減できます。そこに昨今のフィンテックやブロックチェーンのブームが加わって、実際に独自にデジタル通貨を発行する地域が現れ始めたという流れです。
ただ、まだ数は多くありません。いま実際に商用で使える形で動いているのは、私たちが関わっている岐阜県飛騨高山地域の「さるぼぼコイン」と千葉県木更津市の「アクアコイン」。実証実験段階のものだと、トラストバンクの埼玉県深谷市「negi(ネギー)」、JR東日本のベンチャー支援でやっている宮城県塩釜市「竈コイン」あたりでしょうか。
いまはまだ多くの方に認知をしていただくフェーズですが、地域における関心は非常に高いと思います。地域は高齢化や人口減少のスピードが速くて、どうすればいいのかという危機感を持っています。その流れを変えるきっかけになるかもしれないという思いで、私たちのところに問い合わせをされる自治体は少なくありません。
― 地域が抱えている課題について教えてください。
川田 地域にお金が落ちないのです。まずAmazonなどアメリカ資本のサイトでショッピングする人が増えてきました。そしてリアルの店舗も、新しくできるのは東京資本のチェーン店ばかりです。チェーン店が進出すれば雇用は生まれます。しかし、超過利益は東京の本社に行ってしまう。それが地域に再投資されればいいのですが、一部は世界中の株主に配当されて流出します。
地元のお店で買い物するとしても、決済手段が問題になります。例えばクレジットカードで決済すると、東京や海外のカード会社が決済手数料として3~5%くらいを持っていきます。このままキャッシュレス決済が普及すればするほど、地域で回るお金がますます少なくなる構造なのです。
地域でお金を使い、そのお金がまた地域に回っていく、お金の“地産地消”の仕組みをどうすれば作れるのか。そのソリューションとして、デジタル地域通貨への関心が高まっているのです。
― 地域の経済振興策として期待されているのですね。
川田 はい。お金に加えて、決済データの地産地消も進むと期待しています。全国規模のキャッシュレス決済手段を使うと、決済に付随するデータも東京の会社が握ることになります。決済データは、マーケティングの宝の山です。ところが現在、地域の会社は東京の会社にウン億円支払わなければそのデータを活用できません。一方、デジタル地域通貨の運用主体は、地域の金融機関や自治体が中心。決済データでビジネスをしようとしているわけではないので、地域の会社にとっては非常に使いやすいと思います。
またお金についても、狙っているのはフローだけではありません。実はいま高齢化の影響で、地域にストックされるお金が増え続けています。人口は減っているのに、地域の金融機関の預金額は逆に増えている状況です。ところが、ストックのうち、地域に回るお金は半分以下。多くは、国債など地域外に投資されています。このお金も地域で回せるようになれば地域振興に大きく貢献するはずです。
― デジタル地域通貨ならストックを地域に投資しやすくなるのでしょうか。
川田 いま私たちも試行錯誤している段階ですが、事例としてわかりやすいのは寄付でしょうか。昨年夏、台風で線路が流されて鉄道が不通になる被害が高山でありました。その義援金を、さるぼぼコインとクラウドファンディングの両方で募ったところ、件数や額が多く集まったのは、さるぼぼコインのほうでした。
クラウドファンディングで寄付しようとすると、カードの登録など幾つかの初期手続きが必要になります。一方、地域の方々はさるぼぼコインを使い慣れていて、通常の支払いと同じ感覚で寄付ができます。義援金用口座のQRコードを新聞に掲載したのですが、それを読み込んで金額を入力すれば、それで寄付完了です。さらに、さるぼぼコインを使っているのは何かしら高山に関係がある人です。全国から寄付を募るクラウドファンディングと比べて、ユーザーに刺さりやすかった面もあると思います。
木更津でも、アクアコインを使った寄付の取り組みを始めようとしています。いま木更津では、市長のリーダーシップで、地元の農家の方が作った無農薬のお米を学校給食に出す「オーガニック米プロジェクト」が進められています。このプロジェクトに寄付することで自分事にしてもらうという狙いだそうです。
これまでご紹介した取り組みは、投資ではなく寄付です。しかし今後は寄付の延長線上で、地域振興につながるプロジェクトや企業にストックを投資する流れが出てくるでしょう。江戸末期や明治の日本では、地域のみんなでお金を出し合って優秀な子どもをヨーロッパ留学させたりしていました。山口県萩市ではその仕組みを復活させて、中学生を東京に数日間送り込んで会社訪問させるプログラムを行っています。これは素晴らしい人材投資です。萩市はデジタル地域通貨を発行していませんが、親和性は高いので、こうした投資と絡めても面白いと思います。
ちなみに日本の個人の決済総額は年300兆円です。それに対して、個人の資産は1,600兆円もあります。ストックされたお金が地域に流れるようになれば、日本経済にもいいインパクトを与えられると考えています。
東京と同じ基準だと、地域では普及しない
― デジタル地域通貨の課題を教えてください。例えば地方は高齢者が多く、高齢者はスマートフォンの普及率も低いといわれています。決済のインフラとして普及するのでしょうか。
川田 高齢者はスマートフォンを使わないイメージがあるかもしれませんが、60代で過半数がすでにスマートフォンを使っています。デジタル地域通貨についても、高齢者だから敬遠するという状況にはなっていないと思います。実際、さるぼぼコインを使ってくださるユーザーの7割近くは女性。年代でいうと、最も使う金額が大きいのは60代。一見、ITリテラシーが低いと思われがちな層によく利用されています。
実は私は前職で、高齢女性向けにタブレット端末を販売したことがあります。発行20万部の通販雑誌に2カ月広告を出して、売れたのは5台だけでした。「やはり高齢者は新しいものが苦手なのか」と私も思いました。しかし、貸し会議室や喫茶店を借りて半日の勉強会とセットにして、倍くらいの価格で販売したところ、数百台売れました。お客様に話を聞いたら、「子どもに教えてもらうのは癪だけど、優しく教えてくれる先生になら」とのことでした。
皆さん新しいものに興味はお持ちなのです。大切なのは、どのようにサポートするか。全国規模のキャッシュレス決済は、セグメントを絞ってWeb中心に効率よくマーケティングしています。一方、デジタル地域通貨は、キャッシュレス事業者大手が目を向けない層に対して、リアルの接点で泥臭いマーケティングを行えることが強みです。地域に高齢の方が多いことは障壁にならないと考えています。
― 実際の普及率はどの程度でしょうか。
川田 さるぼぼコインは飛騨市、高山市、白川村で使えます。これらのエリアの人口は11万人。それに対して、アプリのダウンロード数は約2割。コインを1円以上持っているのは1割強です。エリアの人口に対する普及率でいえば、いまのところPayPayさんより使われています。高山でうまくいったのは、地域の大きなスーパーが導入してくれたから。高齢女性のユーザー比率が高いのも、スーパーで利用できることが大きく関係していると思います。
一方、アクアコインは現時点でダウンロード率が7~8%で、コインを保有している人の割合はその半分にとどまっています。地域のスーパーにアプローチしきれていないことが大きいですが、そもそも運用が始まったのはさるぼぼコインより1年2カ月遅れ。まだ1年しか経っていないので、普及はこれからです。今回のキャッシュレス還元事業で利用者は増えていくでしょう。
― 飛騨高山や木更津は、御社のプラットフォーム「MoneyEasy」を活用してデジタル地域通貨を導入しました。どのような経緯で、このツールを開発されたのでしょうか。
川田 以前、バスの乗車アプリ「BUS PAY」を開発したことがありました。アプリ上でバスを予約して支払い、有効化すると30分間は定期券のように見せるだけで乗り降りできるサービスです。このアプリを開発したのは、小さなバス会社にはSuicaのシステムを入れる余裕がないからです。Suicaを読み取る機械は安いんです。しかし裏側でバスの運行システムと連携する必要があり、その投資コストが馬鹿になりません。キャッシュレス決済を導入したくても、地域は東京と同じ基準でやるのは困難。コストの桁を2つ3つ落とさないと運用できないのが現実です。
そのような経験があったので、飛驒信用組合のデジタル地域通貨コンペでは、低コストで導入できるプラットフォームをベースにしたシステムを提案しました。最低限の機能はプラットフォームで提供して、追加でやりたい機能があればオプションや個別開発で上乗せします。これなら予算に応じて導入が可能です。
こだわったのは、スマートフォンアプリということ。地域に行くと、先ほどの議論のように「スマホを持ってない高齢者はどうするのか」という話が出てきて、FeliCaと併用できるシステムになりがちです。しかし、それが高コストを招き、結局は普及の妨げになってしまう。本気で普及させたいなら、アプリを絶対条件にして、スマートフォンを持っていない人には配るくらいのつもりで進めたほうがいい。
フィンテック業界は、どちらかというとテクノロジードリブンです。しかし、先進的なテクノロジーが必ずしもユーザーのためになるとは限りません。デジタル通貨の世界はブロックチェーンをやりたい人が多いのですが、そこもこだわる必要はない。私たちはユースシーンを大事にして開発しています。
アプリは地域で最も利用される情報インフラに
― 実際にデジタル地域通貨を導入した地域では、どのような変化が起きたでしょうか。
川田 まだ始まったばかりなので、経済効果はこれからでしょう。1、2年では見えづらいので、数年単位で仕込んでいくことになります。ただ、目に見える変化もすでに現れ始めています。高山の例でいうと、PR効果が大きかったと聞いています。金融業界は古くて保守的なイメージがありますが、小さな信用組合が日本初の新しい取り組みをしたということで、さまざまなメディアで取り上げられて、地元での評判が上がりました。評判を聞いて、UターンやJターンする若い人も増えています。飛驒信用組合は地元の高校を出た方を中心に採用していますが、最近は東京の大学からも応募があるようですよ。
一方、木更津ではアクアコインでボランティアポイントを付与する仕組みが始まりました。これらの取り組み自体が興味深いのですが、変化という観点では、市役所で組織横断的な取り組みが始まったことが大きい。一般的に大きな組織は縦割りになりがちです。しかし、木更津市役所では市民活動支援課や収税対策室、会計室など複数の部署が絡んで、昔の日産のクロスファンクショナルチームのような形でこれらのプロジェクトを進めています。新しい取り組みを始めると「仕事を増やしやがって」という話になることが珍しくありませんが、木更津では、前向きな議論につながっている実感があります。
― ボランティアポイントについて教えてください。デジタル地域通貨ならではの活用法のように思えます。
川田 木更津は「オーガニックなまちづくり」を推進しています。例えば、体に良い食材を扱うイベントを毎月行っており、そこにマイバッグとマイ食器を持ってくると、100ポイントが付与されます。環境への配慮を促すための施策の一つですが、付与されたポイントが買い物や寄付を通してまた地域に落ちれば美しいですよね。
このようにデジタル地域通貨を活用して地域の活動を盛り上げていく動きは、今後さらに活発になっていくでしょう。例えば朝、子どもの通学路で旗を持って見守りをしてくれる方に地域通貨が付与されたら、経済的価値以上の励みになるのではないでしょうか。
中国のある都市では、市民の活動をスコアリングしてポイントをつけたところ、モラルが向上して行儀のいい市民が増えたといいます。また、ドイツでも自動車のいい運転をしている人にポイントを付与する事例があります。同じやり方が日本になじむかどうかわかりませんが、コンセプトは学ぶべきところが大きい。地域に貢献するほどデジタル地域通貨が増える仕組みを、私たちも試行錯誤していきたいと思います。
― デジタル地域通貨は、単に地域でお金を回すためだけのツールではないのですね。
川田 はい。実はデジタル地域通貨のアプリには、情報インフラとしての価値もあると考えています。この夏、台風15号が千葉に大きな被害をもたらしましたが、木更津では炊き出しやブルーシートの配布など、災害に対する情報をアプリでプッシュ通知しました。また普段から登録のメールアドレスにメールマガジンを送り、市の広報メディアとしての役割も果たしています。
自治体が情報アプリを単体で出しても、おそらくデジタル地域通貨アプリほどダウンロードされないでしょう。決済手段として機能するから地域の方々を含めた関係人口に普及して、普及しているから情報インフラとしても機能するわけです。
ゆくゆくは、情報発信のレイヤーだけでなく、ボランティアに参加した人が情報交換するなど、コミュニティづくりをしたり、地域愛を醸成できる場になれば面白い。デジタル地域通貨アプリには、それだけの可能性があると考えています。
― 今後、デジタル地域通貨を導入する地域はどれくらい増えていくでしょうか。最後にビジョンを教えてください。
川田 全国で約1,750の自治体がありますが、すべてが導入する未来は描きづらいですね。導入には首長の強い思いが必要で、いわゆる調整型のリーダーでは難しい。そう考えると実際に導入して活用できるのは、100~200ほど、全体の10%程度ではないでしょうか。思いの強い自治体が少しでも増えるように、私も引き続き情報発信していきたいと思います。