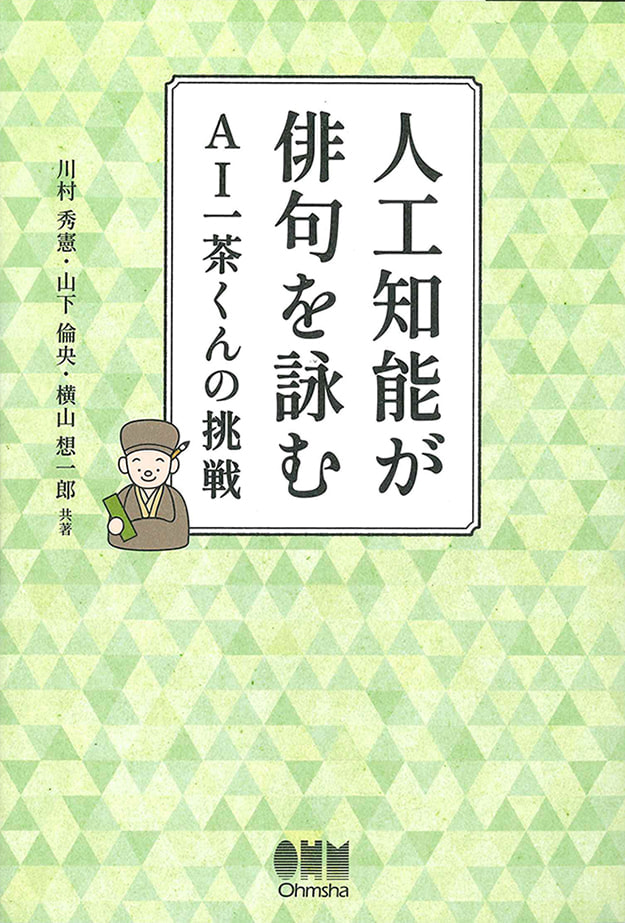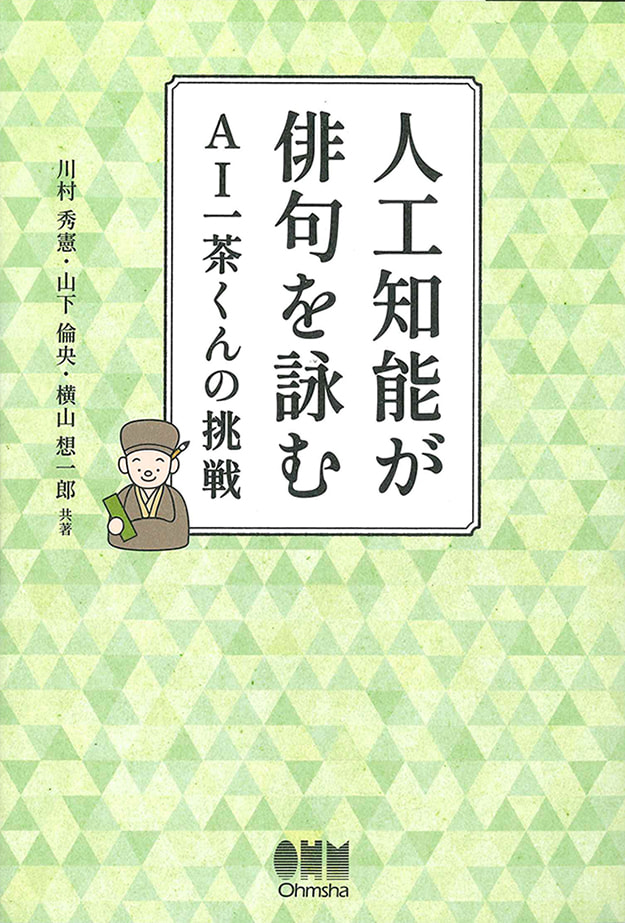4,000人との名刺交換
―川村先生が人工知能(AI)の研究を始められたきっかけは何だったのですか。
川村 私の学生時代はちょうどインターネットが普及し始めた頃。海外の知人とチャットして感激したりして「自分も何かインターネット周りで面白いことができないかな」と思ったことが一つあります。
もう一つのきっかけは当時、IBMのコンピュータ「ディープブルー」がチェスの世界チャンピオンを負かしたことでした。当時は「人間が機械に負けた」という悲観的な論調が多かったのですが、機械といっても人が作ったプログラム。つまりチェスでは世界チャンピオンよりはるかに弱い人たちが作ったプログラムが、最強のトップに勝ったわけです。そこで「AIを活用し進歩していくことで、人間の限界を超えていけるはず。これは人類にとっての明るい希望じゃないか。そういう研究をしたい」と強く思い、今の研究室に入りました。
その後は同じ研究室で博士課程から助手、教授まで進み、30年近く一貫してAIの研究を続けています。
―先生の研究室では、外部との共同研究に積極的に取り組んでおられますね。
川村 はい、その理由の一つは研究資金を得るためです。大学での研究費用は主に文部科学省の科学技術研究費(科研費)を充てることが多いですが、採択率は申請数の30%ほど。プロポーザルを毎年出し続け、運よくそれが“当たる”と研究を進められる。私は「自分たちの研究活動がそんな他人任せである状況はいかがなものか」と思い、補助金以外に研究資金を得る方法を探し、企業との共同研究に行き着きました。
今は常時5、6件、多いときで10件ぐらいの共同研究を行っています。それによって、補助金頼りのときより格段に安定した研究室運営ができていると思います。
もう一つ、AIという世界的に競争の激しい分野で、大学の中で研究しているだけでは、Googleなど世界最先端の研究者たちが集まる研究機関には勝てません。AIの場合、研究成果はソースコードまで公開されていることも多く、私たちもGoogleの作ったディープラーニングのプラットフォームをダウンロードして使っています。そして大学には自前のビッグデータはないので、研究用の公開データを使うことも多くなります。そうすると結局オープンなソフトとオープンなデータを使って、そこに少しだけ自分たちの味付けをするという研究になってしまうのです。
大学は現場を持っていませんが、企業には現場があり、困っている課題があります。
私は「これからAIの研究はどんどん社会やビジネスに応用されていくはず」と予想していたので、企業と共同研究することで、そこからテーマとデータを得てはどうかと考えました。研究成果を企業に返せば、きっとそれを使ってくれるでしょう。
大学の研究では学会発表や論文発表がゴールですが、それにプラスして社会実装を一緒にやっていく。そうすることで社会の役に立つと同時に、研究にもオリジナリティを出していく。そういう構想の下に、戦略的に企業との共同研究を進めていきました。
―企業との接点をどうつくっていったのでしょうか。
川村 共同研究への流れを考えると、お互い全く知らないところから「お金を出すのでAIでこれを研究してください」となることはありません。まず戦略的に研究室を“売っていく”ことを考えました。
一般の人は大学の研究室で何をやっているのかなど知りません。研究室側も情報発信に不熱心です。有名な研究室でも、何年も前に学生が作ったホームページをそのままにしていたりします。“ 補助金を当てる”のに関係ないからです。
しかし企業と共同研究をするには、企業の人に研究室を見つけてもらい、そこで何をやっているかを知ってもらう必要があります。
そのためにうちの研究室では専門のスタッフを雇って、研究情報をホームページに集約し、それをメルマガで伝えたり、研究室紹介のパンフレットも制作したりしています。
ベンチャーの場合は経営者に直接会って「それじゃ何かやろうよ」で話が進むのですが、大企業はそうはいきません。直接会った人が「面白い」と思ってくれても、会社に持ち帰って上司に了解を得なければならない。でも又聞きではなかなか面白さが伝わりません。そこでホームページやパンフレットを見てもらえれば、「面白いことをやっている研究室だな」と感じてもらえる。説得のための武器になるのです。
私自身も積極的に講演したり、取材を受けたり、メディアに記事を書いたり、できるだけ大学の外に出て大学関係以外の人、分野違いの人たちと交流して、人脈をつくることを心がけてきました。
研究室でメルマガを送るのは主に会って名刺交換をした人たちで、累計で4,000人ぐらいになります。メルマガをきっかけに「今度取材したい」とか「共同研究をお願いできないか」とか、時には「寄附したい」というお話を頂き、それによってスタッフを雇って情報発信しても“もと”が取れます。要は“ 投資して回収する”ということですね。
私は幾つかベンチャーの社外役員をやっていることもあり、研究室の運営も経営者目線で考えています。一般の大学の先生でそういう視点を持っている人は少ないかもしれません。
元々は面倒くさがりな性格ですが、あえて外に出て、新型コロナ前まで年間700~800枚の名刺交換をしていました。その人たちを会員登録してメルマガを送るのですが、その中から「一緒に何かやろう」となるのは年に数人、100人に1人以下です。だからこそ多くの人に会わなければなりません。
100万人にインパクトを
—最近では「研究は世の中の何の役に立つのか」が問われることが多く、大学も社会との連携が求められるようになっていますね。
川村 大学では「どんな論文を出したか」が評価につながるので、みんな論文を重視するのですが、私は正直、論文発表だけを追求することには興味はありません。工学はエンジニアリングであり、「世の中を良くすること」が出発点。そのためには、やはり学外に向けて活動の幅を広げていくべきだと考えます。学生諸君には「100万人に影響を与えられるような研究をしよう」と言っています。
研究が製品に採用され、その商品がたくさん売れたとか、サービスとして広く使われるようになったとか、ゴールはどんな形でもいい。人知れずやっていた研究が100万人の目に触れたら、若い人も「自分の研究が世の中の役に立っている」という実感を持てると思うのです。「そういう規模感で社会にインパクトを与えることを目指そう」ということです。
面白いもので、周りの評価を気にせずにやっているうちに、いつの間にか時代が私たちに追いついてきた感じですね。
―AIに俳句をつくらせる「AI 一茶くん」は、広くメディアに取り上げられました。
川村 これは純粋にAIの研究を進めるために「人工知能に俳句を詠ませることはできるか」という課題から始まった研究です。共同研究ではありません。学生諸君がアルゴリズムを作っています。初期の頃には日本語として意味不明な文字列にすぎませんでしたが、今では人のつくったものと見分けがつかないレベルになり、Twitterで俳句をつぶやいたりしています。そこから派生して、「AIで川柳をつくる」という研究もやりました。これはNHKからオファーがあったものです。
NHKで開発した「ニュースのヨミ子さん」という、音声合成で原稿を読み上げるプログラムがあります。人造アナウンサーという設定で画像も制作され、ニュース番組の中に「ヨミ子のコーナー」が設けられていたのです。彼女はただ原稿を読むだけで、AIとして自ら情報発信する機能はありません。「ヨミ子さんにAIがつくった情報を発信させたい」ということで、「ヨミ子さんが今週の時事ネタから、川柳を一つ披露する」という企画が立てられ、2019年3月から1年間、私たちのAIが川柳を提供しました。
NHK 総合で全国に流れるニュースですから、1年間でそれを見た人は100万人どころではなかったでしょう。ただ川柳は俳句より難しくて、AIのつくった句のレベルは「それなり」でした(笑)。
人の感性を取り込むAI
―アパレルメーカーとの共同研究で「かわいい」など、人の感性の数値化にも取り組まれています。
川村 これは「現在、直感のような非科学的な根拠しかないファッション商品の設計を、データに基づいてできないか」という、アパレルメーカーが持っていた課題からスタートしたものです。研究室と、私が技術顧問を務めるIT ベンチャー「INSIGHT LAB」が共同で対応しています。
アパレル企業のデータベースは「この商品はいつ何着作った」「どこの店舗に在庫が幾つある」といった数値データだけで、「それがどういった商品なのか」という定性的な情報はありません。この研究ではAIが各商品の画像を分析して「かわいい」「春らしい」といったタグをつけられるようにして、これまで感覚的にしかできなかった商品作りや経営戦略に、科学的な管理手法を導入しようと計画しました。
AI が学習できるように、まずは「『かわいい』とは何か」を決めるところから始め、「一定以上の割合の人がかわいいと回答したファッションがあれば、それをかわいいと見なす」と定義することにしました。「かわいい」という答えが3%しかなかったら、そのファッションは「かわいくない」ということで、90%が「かわいい」と答えたら、「それはかわいいのだ」と考えるわけです。
服飾専門学校の生徒50人に協力を依頼し、2万点の洋服の画像を見て、そのイメージに応じて「かわいい」「大人っぽい」「スポーティ」といった言葉を選んでタグ付けしてもらいました。それを教師データとしてAIに画像認識させて学習させたところ、ほぼ人間と同じような判断ができるようになりました。
ただ、この共同研究は先方の企業の担当者が会社を辞めることになり、共同研究としては終わってしまいました。可能性を感じる研究だったので、研究そのものは今も継続しています。感性的な情報が使えると、例えば商品をECサイトで販売する場合も、従来とは全く違ったコメントやレコメンドができます。今のECのレコメンドエンジンは、「購買履歴があなたと似ている別の人がこれを買ったから」という理由で推薦してきます。しかしそれぞれの買い手の好みが数値化できれば、「あなたはこういうファッションが好みでしょう」という推薦ができるようになります。
またAIの自動作文機能を利用すれば、商品のお勧めコメントも買い手ごとに変えて作れます。「これはガーリーでかわいくて、あなたの好みにぴったりです」といった感性的でカスタマイズされた推薦がECサイトでできるわけです。
―AIが記事まで書いてしまうのですか。
川村 書けますよ。記事の自動生成については、競輪の車券投票サイト「チャリロト」さんとも共同研究をしました。
投票サイトでは過去データからお勧めの車券をAIで予測するのですが、「2-3」「4-5」といった数字だけでは無味乾燥なので、レースの予測記事を自動作文してみたのです。過去数年分のレース結果と選手情報からAIが予想を行い、「この選手はこう、この選手はこうなので、こういう展開になるのではないか」といった内容の短文を生成します。
競輪は地方自治体主催で、毎日あちこちの地方で開催されているので、記者がついて回って記事に起こすのが難しいという問題がありました。AIの記事が人の書いた記事にかなうかというと難しいのですが、それまでオッズしかなかったところに短くても文章がつくと、初心者でも随分とっつきやすくなります。
人間的で面白いケースとしては、たまたま私の研究室を訪ねてきた女性起業家が始めた「Ail(l エール)」というベンチャーがあります。ここは「Aill goen」という婚活アプリを扱う会社です。
出会い系のサービスがいろいろある中、彼女は「もう少し社会的にきちんとしたものを作りたい」ということで来られたのですね。男女がアプリにログインするとAIでマッチングされ、会話ができるというのが基本ですが、ありがちな「あとは当事者同士でどうぞ」ではなく、「次はこういうことを訊いてみたらどうか」というように、双方にAIがアドバイスするサービスがついています。
この手のサービスで、恋愛慣れしていない人がよく陥る失敗があります。例えば男性ばかりがすごく盛り上がって、告白したのはいいけれども、女性には全然その気はなくて、「ごめんなさい」でフラれてしまう。これがお見合いだと、間に立った世話人がそれぞれに「どう思う?」と感想を訊いてくれるので、直接行って玉砕することはないわけです。そこで世話人の代わりにAIが間に入って、それぞれの好感度や雰囲気をチェックし、「今だったらもうデートに誘ってもオッケーもらえるよ」とか「いや、まだやめとけ」というようなアドバイスをするのです。
このサービスは大手企業の福利厚生に採用してもらっており、すでに800社近くで使われています。会社としても社員のプライベートが充実して、安定した相手と結婚もしてもらったほうが、離職率も下がって望ましいわけです。でも現実には結婚相手を斡旋する手段もないので、福利厚生としてこのサービスを採用し、会社が利用料を払う形で婚活の後押しをする仕組みです。
加盟している企業の社員しか利用できないことになっていて、今の加盟企業は一部上場やそれに近い企業と、そのグループ会社。マッチングされる相手もそういう会社の社員ということで、安心感があります。おかげさまで非常に好評です。
人とAIが調和する世界
—先生の研究室の名前「調和系工学」には、どのような意味が込められているのでしょうか。
川村 私ではなく先代の教授が付けた名前なのですが、そのまま使っています。うちの研究室には「人とAIが調和する世界をつくる」というテーマがあるのです。
「AIは人間の脅威」とか「AIが人間の仕事を奪ってしまう」という偏見は根強くあります。以前にGoogle 傘下のディープマインドが制作した「AlphaGo(アルファ碁)」というAIが各国の囲碁のチャンピオンを総なめにしたときも、チェスのときと同様、「人間が機械に負かされた」と騒がれました。
その延長で、例えばAIと人が部品を検査して、「AIのほうが成績が良かった」となると、すぐ「人の仕事が奪われる」という話になってしまう。俳句にしても、テレビなどは人がつくっている俳句にAIのつくった俳句を並べて、「どちらが優秀か」という企画をやりたがります。何かと対決構図にしたがるのです。
その気持ちもわからないでもないですが、俳句は本来、勝ち負けなどないし、そもそも人が「良かった」とか「面白い」と思ってくれて初めて意味がある。人間が関係しない俳句なんて、何の意味もありません。実際に世の中の多くの課題は、人がいないと生じないのではないでしょうか。今お話しした婚活アプリなども、まさにそういう課題ですね。
人だけだとうまくいかないときに、AIが「頑張れ」とサポートして、人と人とをうまく結びつけていく。私はAIはなんでもできる万能の存在ではないし、そうである必要もないと思っています。協力企業から相談を受けたとき、私がよく言うのは「別にすべてAIでやらなくてもいいんじゃないですか」ということです。
例えば、電話の問い合わせに応えるAI、チャットボットをコールセンター用に作るとします。チャットボットの応対は現状でも7割ぐらいはうまくいくのですが、残り3割は過去に例のない問い合わせだったりして、うまく対応できません。もし完全に人の代わりをAIにやらせようとしたら、あと5年や10年は研究しないとだめでしょう。
でも「考えてみれば、人の7割でいいじゃないか。残り3割は人がやればいいんだから」ということです。よくある質問だったらAIが前さばきして、過去に例がない質問が来たら人に回せばいい。質問している側から見れば、答えてくれるのは人でもAIでもいいわけですから。サービスをつくるときも「AIと人がチームを組んで対応するのだ」と思えば、AIに完璧を求める必要はなくなります。
何年か前に中国で、マイクロソフトが作ったチャットボットの「XiaoIce(シャオアイス)」に対して、自分の彼女だと思ってアプリで毎日メッセージを送る人が出て、社会問題になったという話がありました。
それは少し極端ですが、人間は思ったことを吐き出さずに溜めていると心の健康に良くないので、テニスの壁打ちのように話を聞いてくれて、溜まっているものを吐き出しやすい環境をつくるだけでも全然違うはずなのです。
シャオアイスは日本では「りんな」というサービスになっていて、LINEでつながって話せるようになっています。私も試してみましたが、人と同じように会話できるまではまだまだだと感じました。でも壁打ちの相手であれば、別に人のふりをしなくても、ロボットでもゲームのキャラでもいいわけです。そういうゆるい感じで考えたほうが、AIの応用範囲が広がります。
―先生のお話を伺っていると、人とAIの関係をポジティブにイメージできます。
川村 もう一つ考えるべきなのは、「何を人がやり、何をAIがサポートすべきか」という人とAIの役割分担ですね。
AIで俳句をやってみると、出来がいいかどうかは別にして、俳句をつくらせること自体は割と簡単にできるんですよ。私たちもスパコンを回して1億以上の俳句をつくっています。それだけつくれば、中には良い句もあるわけです。しかしそこから1つを選ぶには、人間と同じセンスがないと難しい。AIには難しいのです。
今はどうしているかというと、人に頼んでいます。研究チームは誰も俳句をやらないので、私たちが選ぶとけちょんけちょんに言われてしまう。そこで俳人の方に選んでもらっているんです。高浜虚子が「選は創作なり」という言葉を残していますが、「選ぶのも創作活動の一つである」ということですね。
テレビでは「AIがつくった俳句」ということになっていても、選ぶところには人の手を借りている。実際はAIと人の共作なんです。
別にAIがすべてやれるようにするのがゴールというわけでもありません。2019年から松山市で、「俳句チャンピオン決定戦 恋の選句王大会」と題して、AIでつくった恋愛に関する大量の俳句の中から、人間が優れた俳句を選ぶ、選句の大会をやっています。
AI 作の俳句を参加者に1人100句ずつぐらい配り、その中からいいと思う句を選んでもらい、それぞれが選んだ句の出来を競う。「誰が俳句の目利きか」を競う競技です。
これが人がつくった俳句だと作者がいるので、「これにケチをつけるな。偉い先生の句だから」とか「この句は知っている」とか、いろいろ問題があるわけです。でもAIオリジナルの句であれば問題がない。ちょうど麻雀やトランプのように、配られたカードに応じて競うというゲームで、大量の句をつくれるAIがないとできないイベントでしょう。そんなふうに「AIがあるから面白いことができる」ということも、今後はどんどん増えていくと思います。
人とAIの役割分担としては、物事の決定や価値判断もAIではできない領域です。私たちはよく「パレート最適」(どのように資源配分の変更を行っても、誰かの犠牲なしでは、誰の満足も増すことができない状態)と言うのですが、こちらを立てればあちらが立たずという状況になったときに、何を選ぶのかは人が決めるしかありません。
例えば新型コロナで経済を回すのが優先なのか、命を守るのが優先なのかといったら、これはAIでは決められない。それぞれの人の価値観によって、どちらを選ぶのかが違う。AIは人のお手伝いまではできますが、最後の決定は人間がやらなくてはいけません。
AIで地方創生
―先生は「SAPPORO AI LAB(札幌AIラボ)」というプロジェクトにも関わっておられますね。
川村 私がラボ長を務めています。これには背景がありまして、札幌を中心とした北海道は、IT 系の産業では「ニアショア」と言われているんです。
海外に仕事を出すことを「オフショア」と言いますが、北海道は東京に比べれば人件費が安く、日本語が通じるので、IT 開発の下請け仕事が流れてくる。それが北海道のIT産業の中心で、年間4,000億円ほどの市場規模があります。でも下請けでは儲からないし、この先伸びるのかというと難しい。
「今後IT産業の中でAIの比重が大きくなっていくときに、北海道も独自のブランドを持てないか」と考えて話をしたら、行政の人たちも乗ってくれて、「AIを軸にさまざまな活動をして、産業をサポートする機能を持ったコミュニティをつくろう」ということになったのです。
札幌AIラボを中心に、大学も含めて地域のIT産業をブランディング。結果、下請けではなく、きちんと自分たちの名前で仕事ができるような体制にしていく。そういうコミュニティがあると、行政もAIの開発事例のある会社を集めて展示会を開いたり、資金をサポートしてくれたりします。
またそれとは別に、「AIを開発する会社を地元につくりましょう」ということで、私の研究室からも「調和技研」というAIのロジックづくりを行うベンチャーを立ち上げました。私たちの研究成果を社会に実装していくことが設立目的の一つで、研究室で初めてのAIスタートアップです。当初は4~5名が研究室で活動しているだけでしたが、設立して12年になり、今では60名近いメンバーがいて、東京や海外でも活動しています。
研究室発のベンチャーは全部で4社あって、その中の「AWL(アウル)」という、ディープラーニングなどAI 技術を応用する会社も、ベンチャーキャピタルなどから20億円を調達しています。
―理想的な地方創生のように感じます。
川村 私の目標は、自分が好きでやっていることが世の中に出て、皆さんに便利に使われるということ。大学の先生というポジションにこだわりはありませんが、もちろん大学教授という職が嫌いなわけでもありません。私が大学にいて、大企業の人やベンチャーの人と組むと、それぞれ人脈もケイパビリティも違う。お互いが全然違う価値観とチャンネルと能力を持っているので、同じ方向に向かってまとまったとき、大きなチーム力が発揮されるのです。
いろいろな仲間と一緒にやっていると、ある分野が得意な人がいたり、「あそこなら知っているから紹介してあげるよ」といった形で、一人ではとても無理だった世界が広がっていきます。そこに参加して感じるのは、メンバーの一員として大学の研究者も必要とされているということです。チームメイトに大学教授が一人いると、それが強みになるわけですね。
私は北海道出身で、風土や食べ物など北海道が好きなので、地元の行政の方とも共同でいろいろ企画しています。行政の人たちとしても、私のような者が大学にいると、何かと便利なことがあるようです。ですから私が今、大学の先生をやっているのは、自分のためというより、私をうまく使ってくれる多くの仲間のためという感覚ですね。
日本の大学は、昔に比べて研究環境が厳しくなっています。「産学連携とはいえ、そんな論文にならない活動に時間を取られるのは……」という雰囲気がある。産学連携をうまく機能させるには、大学の先生にとってもそれに協力していくことが、自身の業績評価につながるような仕組みが必要だと思います。直接的な金銭的メリットもあったほうがいいでしょう。「ボランティアでやってください」では続かないので。
今後、そういった産学連携のルールや環境を整えることで、日本も大学・企業・社会の「三方よし」になっていくのではないでしょうか。