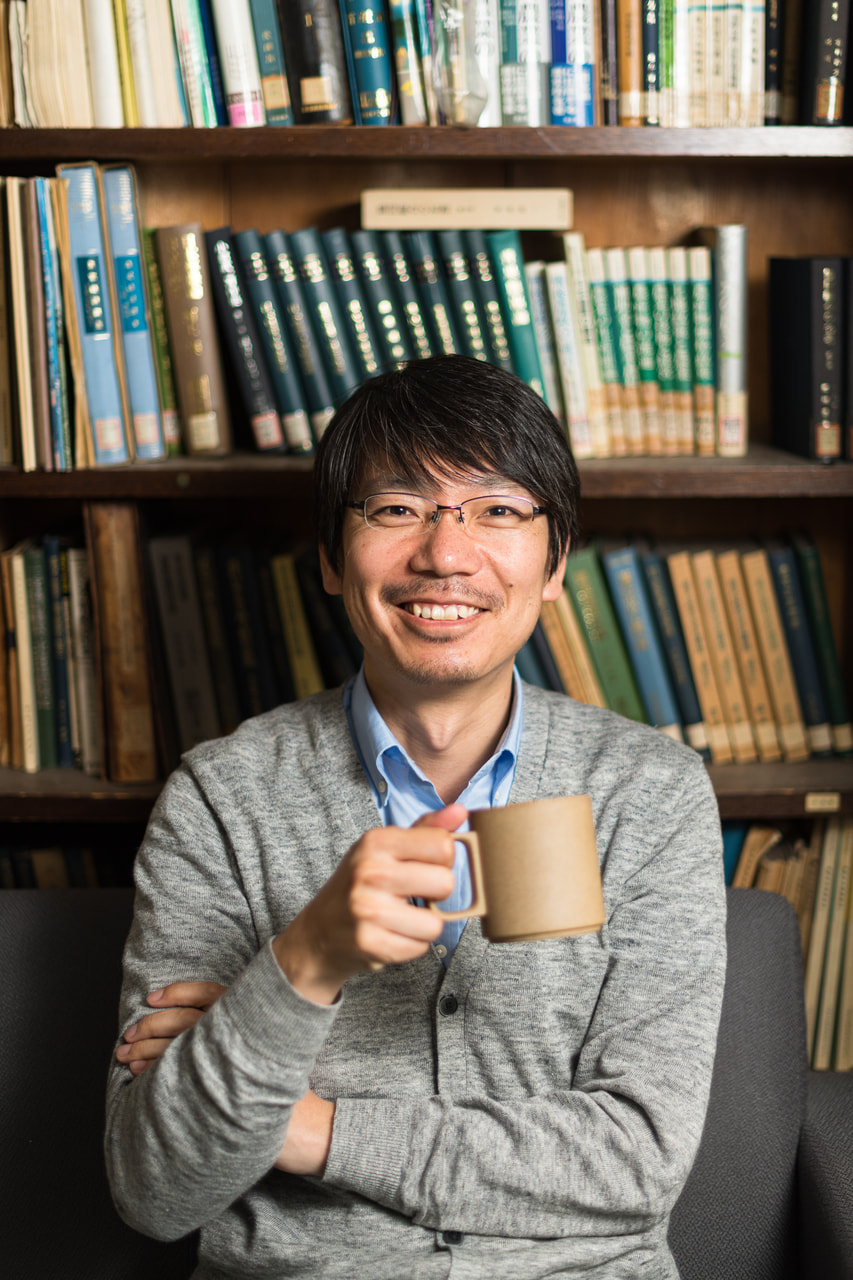「食創為世」の精神で
― 日清食品さんというと麺製品のイメージが強いのですが、培養肉の開発に取り組んだのは、どういったきっかけからでしょうか。
仲村 「日清食品で培養肉を研究している」というと、よく「カップヌードルに入っている『謎肉』に使うんですか」と言われるんですが、そうではありません(笑)。食糧問題の解決に向けての研究なんです。
世界では人口の増加や生活水準の向上にともない、食肉需要が拡大しています。しかし畜産は生産効率が低く、牛肉1kgを生産するために、飼料およそ11kg、水は20t以上も必要になります。これが今後も果たして維持可能なのか。近い将来、食肉が十分確保できなくなる可能性もあります。いわゆる「タンパク質クライシス」で、我々食品メーカーにとっても大きな問題です。そこで新たな選択肢として、家畜に頼らずに食肉をつくることを思い立ったわけです。
動物細胞を体外で培養することで得られる培養肉は、厳密な衛生管理が可能です。また家畜を肥育させる畜産と比べて、広い土地や飼料や水といった資源を必要とせず、温室効果ガスの排出量も少ないなど、地球環境への負荷が小さいという利点があります。そのため、製品化が実現すれば、弊社グループの環境戦略「EARTH FOOD CHALLENGE 2030」に掲げる環境目標の達成にも貢献します。
― こうした基礎研究を大企業が主体となって行うのは珍しいですね。
仲村 培養肉の開発をしている会社は世界中にたくさんありますが、ほとんどがスタートアップやベンチャーで、おっしゃるとおり、大企業が自ら研究開発まで手がけているケースは珍しいです。本業と直接関係ない新しい分野の研究をやらせてもらえることには、私自身、会社の懐の深さを感じています。
日清食品の創業者・安藤百福は、世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」、さらに世界初のカップ麺「カップヌードル」を発明するなど、ベンチャー精神の旺盛な人物でした。我々も創業者の想いを受け継いで、「まだ世の中にない、新たなものを創り出す」ことに強い意欲を持っています。社内にも「Beyond Instant Foods」、つまり「即席食品の価値を超えた、新たな『食文化』への挑戦をせよ。」というスローガンがあります。その意味で日清食品グループには、今もベンチャー精神が流れていると思います。
4つの創業者精神「食足世平」「食創為世」「美健賢食」「食為聖職」は、それぞれ「食が足りてこそ世の中が平和になる」「世の中のために新たな食文化を創造する」「美しく健康な体は賢い食生活から」「食の仕事は聖職である」という意味で、培養肉の開発はこのうちの「食足世平」「食創為世」の精神に合致すると考え、取り組んでいます。
代替肉の4つのレベル
― 最近はコンビニにも大豆ミートのコーナーが設けられるなど、代替肉が大きな注目を浴びています。
仲村 代替肉には幾つか種類があり、市販されているものとまだのものがあります。開発の難しさという視点からは、大きく4つのレベルに分けられると考えています。
レベル1は、豆腐ステーキや精進料理などで使われる植物性の「肉もどき」で、昔からあるものですね。
レベル2は、最近の技術を用い、大豆など植物性の原料を使って肉の味や質感に似せた「植物肉」です。これは市販が始まっていて、スーパーなどで買えるのもこちらです。
レベル3は、動物の細胞を培養してつくる培養肉のうち、ミンチ肉と呼ばれるものです。動物細胞ではあるけれども、細胞の塊の段階にとどまっていて、本物の肉のような筋組織を持ってはいません。
2013年に、オランダのマーストリヒト大学のマーク・ポスト教授(医学博士)が培養したミンチ肉を使ったハンバーガーの試食会が英国・ロンドンで開かれ、注目を集めました。ただそのとき「ハンバーガー1個をつくるのに、研究費を含めて3,000万円以上もかかった」というエピソードが話題になったほどで、コストが高すぎてまだ市販には至っていません。
レベル4は、同様に動物の細胞を培養しつつ、きちんと筋繊維の組織が形成され、本物の食肉と同じ内部構造を持ち、厚みのある肉です。わかりやすく「ステーキ肉」と呼んでいます。こちらは構造も食感も本物の肉と同じ、まさにリアルミートと呼ぶべきものです。ただ培養ミンチ肉と比べてもさらに飛躍的な培養技術のブレイクスルーが必要で、本物と同じ大きさのステーキ肉の培養には、世界でまだ誰も成功していません。
今市販されているのは、レベル2の植物由来の代替肉までです。我々の研究も今のところは基礎技術の開発段階で、商品化はもう少し先の話になりそうです。
最新の情報では、近々、チキンの培養ミンチ肉と植物由来の代替肉のハイブリッドのミートが市販されるのではないかという話があり、我々も注目しているところです。アメリカのケンタッキーフライドチキンが、ロシアの「3Dバイオプリンティング・ソリューションズ」というバイオベンチャー企業と協力して、ニワトリの培養ミンチ肉を使ったチキンナゲットを販売するというニュースが伝えられているんです。
広がる産学連携の輪
― 培養ステーキ肉の研究は、産学連携で進めていると聞きました。
仲村 はい、弊社では2017年8月から、東京大学生産技術研究所の竹内昌治先生と共同で研究を進めてきました。
竹内先生はそれまで、再生医療の分野で役立てようと、3次元の細胞組織を形成するためのデバイスを開発されていたんです。先生が開発した培養細胞でできた筋肉は、その時点ですでに創薬のテストモデルや次世代ロボットの研究など幅広い分野で利用されており、先生には「この技術を応用すれば『培養ステーキ肉』を必ずつくれる」という確信があったそうです。ただ周囲の理解が得られなくて、研究を進められないでいたんですね。
弊社の中で情報収集を担当する部門の者がたまたま、「竹内先生が『培養肉をやりたい』と言っているらしい」という噂を聞きつけまして、弊社としてもともと興味を持っていたテーマだったので、先生にコンタクトを取らせていただきました。そういう背景もあり、我々が打診すると、すぐに共同研究を始めることに。最初はどんな種類の食肉をターゲットにするかも決まっていなくて、そこからディスカッションを始めて、「牛のステーキ肉を目指しましょう」ということになったわけです。
2019年3月には、当面の目標であった約1㎝角のサイコロステーキサイズの培養肉を完成させ、発表しています。これだけの厚みを伴う培養肉の開発は、世界で初めてのことでした。
― 東大以外の大学とも連携されていると伺っていますが、どちらでしょうか。
仲村 竹内先生は細胞組織を立体にしていく技術に長けておられるのですが、細胞培養については筑波大学の石川博先生に協力していただいています。また培養肉の認知の問題については、社会心理学を専攻されている弘前大学の日比野愛子先生にお力を借りています。
竹内先生を研究開発代表者とする我々研究チームの「3次元組織工学による次世代食肉生産技術の創出」は、2018年度から国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の「未来社会創造事業」の探索研究課題として採択され、助成を頂いてきましたが、2020年4月に、同じ年度に採択されていた59件の探索研究課題の先頭を切って、JSTの「本格研究課題」へ移行しました。最初にJSTの探索研究課題に選ばれた段階では、東京女子医科大学・早稲田大学を中心とする産学共同チームなど、ほかにも幾つかのグループが培養肉の開発でエントリーしていたんです。
しかし2020年に本格研究課題に移行した際、そうしたグループがひとまとめになって、オールジャパン体制になりました。その結果、今では私たちも東京女子医科大学先端生命医科学研究所の清水達也先生や、早稲田大学の坂口勝久先生、大阪大学大学院工学研究科の松崎典弥先生など、都合6つの大学と連携しています。
食卓に上がるステーキ肉を目指して
― 形状が1cm角のサイコロ状になるまでは成功したとのことですが、実際に食べられたことはまだないのですか。
仲村 まだないです。今のところ完全な肉の味には到達していないと思います。現状では筋肉細胞だけで組織をつくっていますが、食肉として味わうには、筋肉だけではなく脂肪も必要になってきますから。脂肪は舌触りや噛み応えといった食肉のテクスチャにも、また味や香りにも関係しているんです。
― 次の目標は何でしょうか。
仲村 2024年度中には培養ステーキ肉の基礎技術を確立し、7㎝×7㎝×2㎝のステーキ肉を完成させることを目指しています。
実用化に向けての今後の課題としては、まず技術的には、味や食感を本物の肉に近づけ、おいしくすること。今後は筋肉組織に脂肪細胞も一体化させていき、さらに血液成分なども入れ込むことで、味をより本物の肉に近づけていく予定です。牛の脂肪細胞の培養については、大阪大学の松崎先生が研究されています。
また生産面については、培養肉の大型化、量産化を進め、コストダウンしていくことが課題です。現在の筋組織に電気刺激を加えるなどして筋収縮させ、さらに成熟させるといった試みも行っています。これは基本的には自宅でトレーニングする機器に使われているNMES(神経筋電気刺激)と同じ原理です。
― 「環境に優しい」と謳うためには、培養液にどんな原料を使うかも課題になってきそうです。
仲村 現状ではまだ実験段階ですので、アミノ酸やビタミン、ミネラルなどが配合された、研究用の細胞培養液を使っています。食用として生産する場合、当面の原料としては大豆の分解物などが候補になってきますね。
それだけでも通常の畜産より生産効率は高くなると思いますが、まだ完全に持続可能な循環とは言い切れません。将来的には培養液も、藻類を育てて光合成させることで得られるようにし、完全循環型モデルを完成させようと計画しています。これについては、東京女子医科大学の清水先生が研究中です。
― 培養ステーキ肉は、今の牛肉の代わりになることを目指しているのでしょうか。
仲村 完全に代替するということは考えていません。今後、人々の嗜好が多様化していく中で、リアルな肉を求める人もいれば、植物由来の代替ミートを選ぶ人も出てくるでしょう。その中で、そのどちらとも違う、「環境に優しく、味はこれまで通りの肉の味がする培養肉」という、新たな選択肢を提供することが我々の目標です。
商品の形としては、スーパーで売っているような生のステーキ肉として提供する可能性もありますし、調理加工したレトルトや、インスタントフードの原料という形で市場に出ることも考えられます。
課題は社会に受け入れてもらうこと
仲村 そして培養肉はこれまでにない新しい食品ですので、もう1つの課題は、「どうやって世の中に受け入れていただくか」ということです。
そこで必要になってくるのが、食用のための細胞培養についてのルールづくりと、社会における認知度・受容性の向上です。ルールづくりについては、農林水産省が2020年10月に発足させた「フードテック官民協議会」という場があり、我々もその中のワーキングチームである「細胞農業研究会」に参画し、関係官庁との協議を進めていきます。
認知度と受容性については、弘前大学の日比野先生のご協力で、2019年に20歳から59歳までの男女2,000人を対象に、培養肉に関する日本初の大規模意識調査を行いました。結果、「培養肉を食べてみたい」と回答した方は3割弱にとどまったのですが、培養肉が食糧危機の解決につながったり、動物愛護に貢献したりといった可能性があることを伝えた上で、培養肉について聞いたことがある人に同じ質問をすると、「食べてみたい」割合が半数まで増えることがわかりました。社会に受け入れられるには、皆さんに培養肉がいいものだと知ってもらうことが大切ということですね。
― 私たちからすると、日清食品さんにはカップ麺などで日常的にお世話になっていて、親しみ深い印象があります。「日清食品が出すものなら、きっとおいしくて安全なものなんだろうな」と思ってしまいます。
仲村 ありがとうございます。そうですね、会社として、とにかく「おいしさ」には徹底したこだわりがありますから。私も、いくら社会的課題の解決のためといっても、おいしくなかったら絶対商品化してもらえないだろうなと思っています。
私個人としては、社会の容認を得る上での一つのキーポイントは、「名前をどうするか」ではないかと思っています。今は「培養肉」と呼んでいますが、「培養」という言葉自体、あまり親しみがないという問題もありますし、そもそも法律上「肉」と名乗っていいのかどうかも、まだ決まっていないんです。
― 海外での開発状況はどうでしょう。
仲村 培養肉については、日本では弊社と、独自の細胞培養システムを使って研究開発を行っているバイオベンチャー企業のインテグリカルチャーさん、そしてそこに出資している日本ハムさんなど、数社が開発をオープンにしているぐらいです。一方、海外では乱立といっていいほど多くの企業が開発中です。ただし、どこもレベル3のミンチ肉止まりで、公式に「ステーキ肉を開発中」と宣言しているのは、世界中を見渡しても弊社と、イスラエルの「アレフ・ファームズ」ぐらいです。
ステーキ肉からミンチ肉をつくることは簡単ですが、その逆はできません。そして食肉の売上のうち、ミンチ肉の割合はわずかで、87%はブロック肉という記事もあるので、本格的に食肉を代替しようとすれば、やはりステーキ肉をつくらないと始まらないと、我々としては考えています。
― 日清食品ホールディングスでは、培養肉のほかにもフードテック関連の計画はあるのでしょうか。
仲村 はい、具体的なことはお話しできないのですが、培養肉だけでなく、「世の中のために新たな食文化を創造する」という「食創為世」の創業精神の下、「おーっ」と驚くようなものを開発中です。ご期待ください。
― それは楽しみですね。培養ステーキ肉も息子さんから、「早くつくって」と言われているとか。
仲村 そうなんです。カップ麺を食べながら頑張っています(笑)。