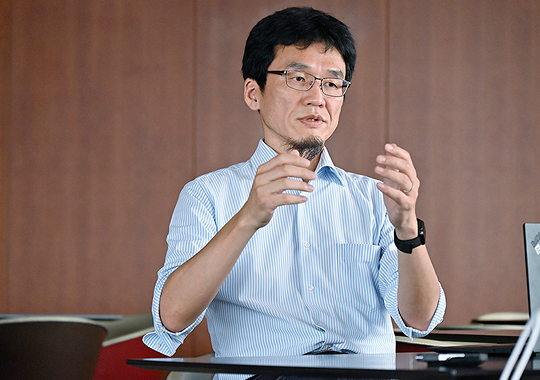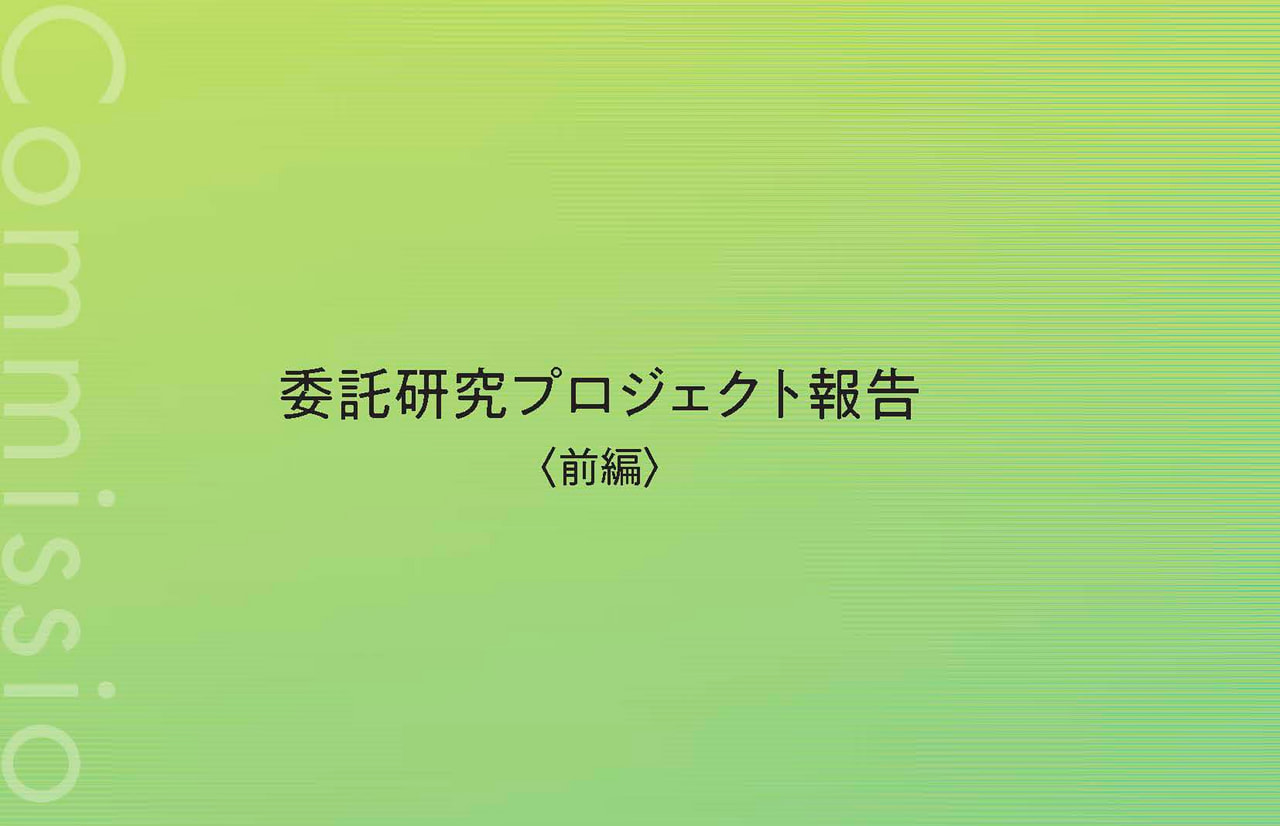産業と文化とをつなぐ
— 岩本さんは学生時代の2018年にTeaRoomを創業し、日本茶に関する事業を国内外で展開されていますが、最初に手掛けたのはお茶の生産だったそうですね。茶道家が第一次産業に携わるのは珍しいと思いますが、背景をお聞かせください。
岩本 私は幼少期に裏千家に入門してお茶を始めました。家元ではありませんが、裏千家より準教授の許状を受け、岩本宗涼という茶名も拝命しています。
21歳でTeaRoomを設立したときに、静岡県本山地域で廃業が決まっていた茶畑と工場を譲り受け、お茶の生産に乗り出しました。理由は、茶道家としてお茶づくりの知識をきちんと持つことが大事だと考えたからです。
一般的に茶道家は思想を重視する傾向にあるので、お茶の銘柄やお茶を詰めた茶舗の名はよく知っていても、産地や製法など技術的な部分にはあまり踏み込まない傾向があります。例えば、日本人に最もよく飲まれている煎茶と、抹茶の原料である碾茶(てんちゃ)とでは、栽培・製造過程にどのような違いがあるのか。そのことについての知識を持つのは、一部の限られた方々かもしれません。
一方で、お茶の生産者側も、「茶道」に対する関心はあまり高くない印象があります。であれば、茶道家である私が茶室の外に出て、両者の接点をつくれないだろうかという思いから、生産部門の事業を立ち上げました。企業の目的は、産業と文化をつなげること。会社名である「TeaRoom」は、「T」と「R」が大文字で1単語になっています。英語表記の場合、「Tea room」と2語に分かれるのが普通ですが、プロダクトとカルチャーが1つに結び付く姿を描きたいという思いを込めています。
— 日本茶の消費量が減少する中、茶産業を持続可能なものにする上でも大事な取り組みですね。
岩本 そう思っています。スタートアップでお茶のブランドを立ち上げて、販売に特化したビジネスを展開することも、方法としてはあるでしょう。ただ、それでは根本の課題は解決できません。
自分たちで生産部門を持たずに販売だけを行う場合、お茶の原価をできるだけ抑えるため、安く買いたたくようなことになりがちです。当社は企業理念に「対立のない優しい世界を目指して」を掲げています。買い手優位の状態では、生産者は適正な利益を得ることはできません。社内に生産部門を持つことで、原価に見合った販売価格をどう設定するかといった建設的な議論が生まれます。ですから、茶産業における垂直統合(生産から製品の販売に至るまでのサプライチェーンにおいて、2つ以上のプロセスを1つの企業内にまとめること)は、起業する際に最初に取り組まなければならないことだと考えていました。
文化とは、未来を耕すもの
— 起業から5年後の2023年、新たに「一般社団法人文化資本研究所」を設立されました。どのような動機だったのでしょうか。
岩本 実は、お茶の生産を始めたものの、最初は利益を出すのが大変難しく、苦しい日々が続きました。どうしようかと悩んでいたときに、タピオカブーム(第3次)が起き、茶葉を使ったドリンクが注目され、需要が高まりました。これを機に、茶の湯が本来持っている意味や意義を再度問い直し、文化資本として社会に提供することに、より真剣に取り組む必要があると考えるようになりました。おいしいお茶をつくるだけでなく、お茶を楽しめる社会をつくること、茶の湯の場をつくるだけでなく、その文化を育む社会の土壌そのものをつくることが使命だと捉えたのです。
一方で、私は「文化」という言葉が、過去に固定化された伝統を想起させる点に違和感を抱いてきました。英語の「Culture」には「耕す」(Cultivate)という意味もあります。明日を耕す、明日を豊かに生きるという未来志向の視点がカルチャーの根源的な意味であるとするならば、文化の持つ社会的な意義は、過去に固定化された伝統的価値だけでなく、未来を耕す、変化を許容する動的な思想にこそあるのではないでしょうか。私たちは茶の湯の思想を通じて、社会が豊かになるための新たな価値を提供したい。そのために、多くの企業の方々とお茶の価値が伝わる接点をつくる活動をしています。
そうした中で、資生堂の元会長・福原義春氏が著した『文化資本の経営』という本に出会いました。今から20年以上も前に、人や文化、歴史といった見えない資産を活用する「文化資本」に基づく経営の重要性を唱えられていたことを知り、自分の考えは間違いではないのだと確信しました。そして、まさにいまこそ文化資本に基づいた経営が求められる時代だと考え、「文化資本研究所」を立ち上げました。さまざまな文化や社会活動の中に潜在的に存在する「文化資本」を探索・深化し、社会に実装していくこと、またそのプロセスを「文化資本経営」の方法論として確立させる活動を行っています。
今の有限資源をめぐる経済成長の追求は、世界に対立と競争を生み、社会は衰退の一途をたどっていると感じています。日本の文化の深層に潜む「文化資本」は、世界の豊かな未来をつくる1つの解になり得るでしょう。
「文化資本」への投資の中長期的メリット
—「文化資本」に基づく経営とは、具体的にはどのようなものなのでしょうか。
岩本 例えばTeaRoomの事業の場合、お茶の生産を手掛ける「Tea事業」と「文化事業」などがあります。「文化事業」では、茶の湯の本質的な思想を社会に伝えるアプローチを行っています。
生産者としておいしいお茶をつくり、プロダクトとして市場流通させるだけでは、お茶の真価を社会に届けるには不十分。「お茶の本当の価値を届けられる社会との接点」を、新たに創出することが必要なのです。そのためには、業界の垣根を越えてさまざまな企業と協業することが重要になります。
一例として、デベロッパーの東京建物さんたちと組んで、オフィスビルにお茶のサーバーを設置し、急須で淹れたお茶と同等の風味と香りを楽しめる高品質なお茶をワンタッチで手軽に購入できるサービスを開始しました。健康経営やウェルビーイング経営に取り組む企業が増えていますが、お茶を通じてオフィスにおける新たな生活習慣を創出することで、働く人たちの心身の健康やコミュニケーション活性化などにも貢献できます。多額の広告費を投じて需要を喚起する施策とは異なり、まずお茶文化の価値を知ってもらう接点をつくること、そういった社会づくりによって、広告に頼らずともお茶を飲んでもらえるような世の中をどうつくっていくのかが、大事な論点になります。
— 文化資本に投資し、社会を変えていくアプローチで、需要を喚起するということですね。近年、改めて注目が集まっている銭湯においては、企業のスポンサード事例も見られます。これも文化資本と捉えることができるのでしょうか。
岩本 そうですね。ご存じのように、銭湯は衰退産業といわれる程、どんどん数が減っています。しかし、銭湯は単に体をきれいにするだけでなく、老若男女が交流できるコミュニティの場でもあり、今でいうソーシャルキャピタル(社会関係資本)と同じような考え方で、福祉や防災、地域振興の場としての機能も併せ持っているのです。
この共有財としての銭湯という文化をどう残し、有効活用していくのかを考えたときに、企業が文化資本という視点を持ち、銭湯の価値を理解し、ともに育むような取り組みを行うのが重要です。実際に、企業が銭湯で自社製品を提供し、ユーザーに試してもらうことで、企業の価値観や商品の魅力を伝えるような動きも出てきていますね。それがきっかけとなり、中長期にわたって自社商品を使う人が増えれば、LTV(顧客生涯価値)を上げることも期待できます。
銭湯というのは、各企業単独では所有できない社会の共有財です。社会インフラとして捉えて投資することで、会社と消費者の新たな接点をどんどん増やしていくことができます。企業単体のBS(貸借対照表)やPL(損益計算書)にすぐさま反映されることはないでしょうが、単独の企業でマーケティング活動するだけではなく、社会の共有財に共同投資して文化を創造することで、各企業も中長期的な利益を得ることが可能になるのです。
— 文化資本への投資が、従来の広告マーケティングとは異なる価値を企業にもたらす大きな可能性を感じます。
岩本 社会に対してのインパクトも強く、かつ自社のLTVを高くし、マーケティングコストも下げられるような文化形成の施策を打つ。多額の広告投資で需要を生み出し、供給を増やしていくというサイクルではなく、文化を土壌とした需要に対して供給していくというサイクルに切り替える。そういった発想の転換が大切です。そうでなければ、日本企業のお金はひたすら広告費に消えていき、自社のプロダクトをただ供給するだけになってしまいます。巨額のマーケティングコストがあるのならば、それを文化資本への投資に割くことで、社会の共有財が維持され、自社のプロダクトも売れるという好循環が生まれます。
『文化資本の経営』の中では、銀座の事例が紹介されています。資生堂が銀座という街に「美の文化」を築き上げたことで、美しく装う人々や、美しくありたいと願う人々が自然と集まる場となっていきました。しかし、その実現には資生堂単独の投資だけでなく、同社が旗振り役となり、銀座に根差すさまざまな企業の協力を得ることが不可欠でした。こうした取り組みを通じて、銀座という「場」そのものの価値やブランド力が高まり、文化の象徴として確立されることで、銀座で事業を営むすべての企業が恩恵を受ける構造が生まれたのです。
地方創生とグローバル展開
— 場所の価値と企業活動は密接に結び付いているわけですね。
岩本 そのとおりです。これは東京に限った話ではありません。日本各地にはそれぞれ固有の文化や魅力が存在します。その価値をさらに高めるためには、地域の企業が連携し、地域の資源や文化に投資していくことが欠かせません。こうした取り組みは、移住者や観光客を呼び込み、結果として地域経済を活性化させ、地方創生につながっていきます。
その一例が、当社が幹事企業をつとめる「一般社団法人和栗協議会」です。「うなぎパイ」を製造・販売する春華堂が中心となり、静岡県内の有力企業が集まって立ち上げた組織で、当初は「遠州・和栗」の魅力を世界に届けるプロジェクトとして始まりました。やがてその活動は県全体に広がり、広範なネットワークの構築や、官民が連携する取り組みへと発展しています。地域の価値が高まれば、移住者や旅行者が増え、観光や物産の売り上げが伸びるだけでなく、地域全体のブランド力が向上します。逆に魅力が失われれば、人口流出や経済縮小を招きます。だからこそ、地域の企業が公共財としての文化やインフラに投資し、人々が暮らしやすく、訪れやすい環境を整えることは、最終的にすべての企業の利益につながるのです。
地方創生の現場では、「旗振り役となる企業が見当たらない」「スポンサーが集まらない」といった課題が語られることがあります。しかし、それは文化資本や共有財への投資の意味や長期的なリターンが、十分に理解されていないためではないでしょうか。地域に利益をもたらす企業が率先して先行投資し、投資規模が大きい場合は複数社で分担する──その仕組みを整えることが重要です。
現状では、都会から移住した若い世代がクラウドファンディングでブランドを立ち上げ、ネットで販売するといった動きにとどまりがちです。それでは地域経済の持続的な活性化には結びつきません。必要なのは、一過性のプロジェクトではなく、その土地の文化資本を基盤とした投資を企業活動と連動させ、長期的に地域を育てる視点です。これが、これからの地方創生において欠かせないアプローチだと考えます。
— 御社は国内にとどまらず、グローバルにも事業展開されていますね。
岩本 当社は、日本で培った他企業との共創ビジネスモデルを、グローバル市場でも積極的に展開しています。
米国では、日本を代表する鮨の名店「すし匠」ニューヨーク店において、お茶の点前の監修や道具の調達を担当しました。タイでは、音楽・アート・ライフスタイル・自然をテーマにした同国最大級の音楽・ウェルネスイベント「Wonderfruit 2024」に、京都のアートコレクティブOchill(オチル)と共同出展。「茶香(吸うお茶)」を用いた新感覚の「Tea Ceremony」を開催し、茶の湯の思想を軸にしたウェルネス分野への新たな提案を行いました。
この他にもアジアや欧州で茶室のプロジェクトを進めており、こうしたグローバルな取り組みは、日本茶輸出部門の成長にも大きく寄与しています。
— 御社のそうした活動範囲の広がりは、岩本さんが茶道における「型」を守ることにとどまらず、その先を探求されていったことと関係しているように感じますが、いかがですか。
岩本 私は茶道を通じて長く「型」を学んできましたが、その過程で多くのことを考えさせられました。
およそ450年前、戦国時代に千利休が茶の湯を大成し、その思想や型を口伝と点前のみで伝えました。型を保存する仕組みだけが整えられ、後世の弟子や周囲の人々がその思想を解釈し、物語として書き記していったのです。これはキリスト教や仏教などの宗教とも共通しており、キリストやブッダも自ら文字を残さず、弟子たちの手によって教えが体系化されました。
茶道には現在、約100の流派が存在し、それぞれに独自の型があります。その型を保存・普及するための制度が「家元」であり、弟子たちは流派の型を学び、ライセンスを得て、茶道教室を通じてその型を広めていく仕組みです。しかし、型は固定されたものではありません。様式や道具、客人によって変化し、時代の流れとともに増えてきました。例えば明治初期には、外国人を迎えるために椅子を用いた「立礼式(りゅうれいしき)」という点前が生まれました。
よく知られる型に「茶碗をまわす作法」があります。裏千家では、茶碗の正面を避けるために2回まわしていただきます。ですが私は、単に従うのではなく、「なぜ2回まわすのか」という意味を考えることが重要だと考えています。もちろん、その背景には茶碗や茶席の亭主、そしてこの時間や環境への感謝の気持ちが込められています。ですが、その感謝を伝える手段として2回まわすことが唯一の方法なのか。特に海外の方に伝えるとき、どのように説明すればその精神が理解されるのか。常に、その本質を問い直すようにしています。
— 確かに、作法に込められたものを的確に伝えるのは難しそうですね。
岩本 外国の方に説明する際には、「これは茶碗の正面を避けるための所作です」とお伝えするようにしています。茶の湯には、亭主と客が心を合わせて場を創り上げる「主客一体」の精神があります。亭主が心を込めて点てたお茶を、この精神の下でいただくにはどうすべきか。その答えの1つが茶碗をまわす作法です。正面を避けて端からいただくことで、自らを少しへりくだらせ、茶碗や亭主への敬意を表す様式となるのです。
流派によって型は異なりますが、重要なのは、一般の方々がその背後にある思想を理解し、実感できることだと思います。私は、型の「理由」や「背景」を深掘ることで、それぞれの流派や開祖の思想がどのように形成されたのかを探り続けてきました。
茶の統合力が世界を救う
— 御社は「対立のない優しい世界を目指して」を理念に掲げ、岩本さんも「分断の解消」ということをおっしゃっていますね。
岩本 茶の文化は、産業と文化、文化と文化、宗教と宗教、さらには国と国といった対立を和らげるためのソリューションになり得ると考えています。
茶室は小さな空間ながら、思想を共有し、表現し、調和を生み出す普遍的な力を宿しています。茶会という儀式には多くの制約がありますが、その制約があるからこそ、自由な発想や独自の創造性が育まれます。これらは、日本独自の「設え(しつらえ)」という思想のもとに培われてきたものです。「設える」とは、空間や文脈、思想を理解し、そこに必要な人や物を揃え、1つの体験として提供することを意味します。茶の湯では、同じ作家や窯元の道具を複数使うと平坦な取り合わせになってしまうため、あえて異なる産地・作家・時代の道具を取り合わせて設えることが理想とされています。例えば、水差しは備前焼、なつめは志戸呂焼というように、一つひとつの道具が固有の物語を持ち、それらが文脈の中でつながり合うことで、茶会全体に統合されたストーリーが立ち上がる。その瞬間こそが最も美しいとされるのです。
一方、西洋のテーブルマナーやテーブル様式は、白磁一色ですよね。真っ白で単一のものが美しいと感じる考え方と、多様なものがその場に存在しているけれども、それがナラティブによって紡がれている空間が美しいと感じる日本の発想は、まったく異なるわけです。
日本の思想は「関係性」を重んじ、西洋のデカルト的な二元論とは対照的です。日本では、すべてのものが連動し合って生きているという考えが根付き、人間も自然の一部として捉えられます。この視点に立つと、点在するさまざまな存在を有機的につなぎ、1つの世界観として統合する力は、日本の茶の文化、そして茶人が最も得意とするスキルだといえるでしょう。私はこの力を生かし、世の中に存在する多様な「対立」を乗り越えるための一助となりたいと考えています。
— 最後に、文化資本を継承することによって社会がどのように変化していくか、岩本さんが抱いておられるイメージを教えていただけますか。
岩本 日本企業によって、経済活動と文化活動が連動する関係性が構築され、その好影響が世界にも広がっていってほしいと思っています。
なぜなら、世界がカオスになればなるほど、日本文化の果たす役割が重要になってくると考えているからです。どういうことかというと、日本の文化は「日常性」に価値を見出します。七十二候、一期一会、八百万の神……ほぼすべて、日常に根差した考え方です。そうした価値観の背景には、世界でも有数の自然災害の多い地域であることが挙げられます。環境変動が大きくなるほど、日常の価値というのは高まります。そのため、古来自然災害に苦しんできた日本では、日常性を重んじた文化の価値が重視されるようになったのです。
現代では、世界的に自然災害が増え、紛争も絶えることがありません。だからこそ、災害大国として独自に培われてきた日本の思想や価値観を、いまこそ世界に発信すべきときが訪れているといえます。自然災害や紛争に苦しむ国や地域に対し、文化という形で日本が貢献できる可能性は大きいでしょう。
そして、多くの日本企業が文化資本を重んじる経営へと舵を切り、社会の持続可能な発展に寄与する姿勢を確立できれば──その力をもって世界に歩み出し、世界の調和に資する未来のシナリオが見えてくるはずです。