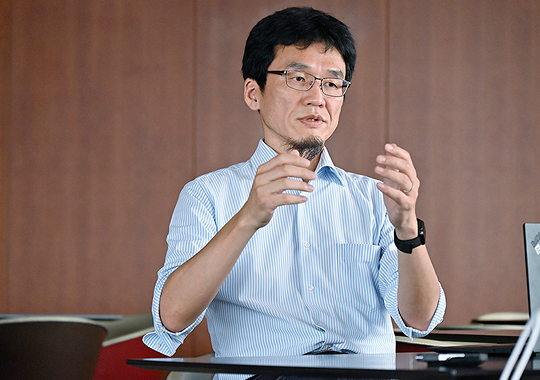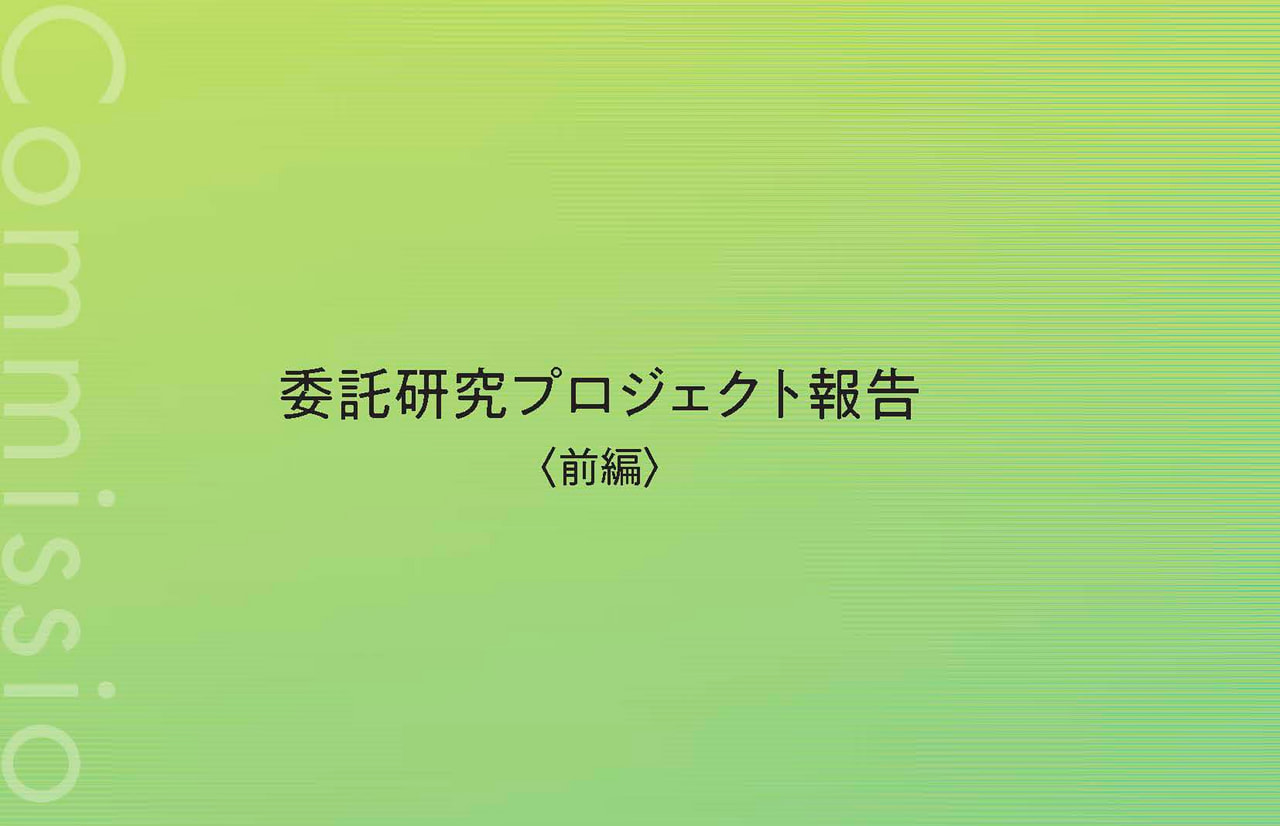本プロジェクトは2022年5月から始まり、約半年を費やして、研究の方向性やチーム編成について検討が行われた。そして2023年2月にメンバー全員が集まり、キックオフ・ミーティングが開催された。その日のメモを振り返ると、こんなことが書いてある
・ 5年後、あるいは10年後の広告コミュニケーションの教科書に1ページを加えることを目指していく。
・ 今日のデジタル・コミュニケーションの多くが「流通業者による短期的なプロモーション」という観点で構成されており、「メーカーやサービス事業者による中長期的なコミュニケーション(ブランディング)」の観点が希薄である。そこでこの領域に焦点を合わせ、デジタル時代におけるブランド・コミュニケーションについて深掘りしていく。
こうしてプロジェクトのビジョンと内容が定まった。そして、それから3年間にわたり、日本を代表するマーケティング研究者によって構成された2つのチームが研究に取り組んだ。素晴らしい成果を生み出してくださったメンバーの先生方には、感謝の言葉しかない。
私に残された仕事は、彼・彼女らの研究を包括して、「教科書の新しい1ページ」をつくることだろう。これから2回にわたり具体的な研究報告が掲載される予定であるが、ひと足先にプロジェクトの成果を教科書風にまとめてみる。
* * *
消費行動の変化:少し気になる×ゆるくつながる
現代を象徴するキーワードはいくつもあるが、その1つがデジタル化である。デジタル化が進展することで、人々の消費行動はどのように変化しただろうか。
消費者自身の立場から見ると、いろいろなブランドを、いつでも、どこでも、簡単に、比較・検討・購買できるようになった。つまり(1)選択肢が多くなり、(2)入手容易性が高まった。その結果、「少し気になる」ブランドが増えるとともに、お気に入りのブランドと「ゆるくつながる」ようになった。
これを企業の立場から見ると、消費者の選好が「強度」と「分散」において変化したと捉えられる。お気に入りのブランドとゆるくつながるということは、好みの強さが弱まっていること、つまり選好の「強度」が低下していることを意味する。またお気に入りのブランドがたくさんあるのは、好みが散らばっている、つまり選好の「分散」が大きいことになる。これら2点をブランド・マネジメントで用いられることが多い概念に当てはめると、「弱くて広い」ロイヤルティ、エンゲージメント、あるいはリレーションシップが増えつつあるといえる。
弱くて広い時代のブランド・コミュニケーション
通常のブランド・コミュニケーションでは、自社ブランドだけに対して、強いロイヤルティ、エンゲージメント、リレーションシップを形成しようとする。つまり顧客とブランドの間に「強くて集中した」つながりをつくるのが一般的である。しかし現代の市場環境では、上述したような「弱くて広い」つながりも大切になっていく。弱くて広い時代のブランド・コミュニケーションについて考えてみよう。
つながりのつくり方
初めに、ブランドとのつながりのつくり方についてである。弱くて広いつながりの時代には、より多くの人に、少しずつ気に入ってもらうのが大切である。このために肝心なのが、パブリシティやクチコミを駆使して、できるだけ多くの人に情報を届けること、つまり情報を拡散させることで、到達範囲の広さ(リーチ)を実現することである。
弱くて広い時代にリーチを獲得するポイントは、情報の拡散を「一般性の高いメディア」へとつなげることである。デジタル・メディアの中には専門性が高く、コアな消費者に到達しやすいものもあれば、Yahoo!ニュースのように、一般性が高く、人々に広く浸透しやすいものもある。まず専門性の高いメディアで話題づくりを行い、それが一般性の高いデジタル・メディアでも取り上げられるようにするのが理想的である。また、少々意外かもしれないが、マス・メディアの活用も有効である。テレビに代表されるマス・メディアには、多くの人々が接触している。このため、無関心層を中心とした知名度の向上や、話題の創出、あるいは拡散の起点として有効となる。
ブランドとのつながりをつくるには「豊かな体験」の提供も欠かせない。弱くて広いつながりを持つ消費者は、日頃から数多くのブランド情報に接している。このため、ありきたりな情報では気に留めてもらえないし、すぐに忘れられてしまう。競合ブランドよりも印象深い体験を提供することが重要になる。豊かな体験には(1)コンテンツの内容と(2)接触方法に気を配るとよいだろう。まずコンテンツの内容が独自で魅力的でなくてはならない。独自性が高く、魅力的なコンテンツでなければ、SNSを中心としたデジタル・メディアでの拡散が見込めないためである。魅力的なコンテンツをつくる方法はいくつもあるが、その1つが「期待や想像を少し裏切ること」である。私たちは予想どおりの情報に対して、つまらなくて退屈だと感じる。しかし予想とあまりにかけ離れていると、理解できないと感じたり、自分には関係ないと思ったり、ときには嫌悪感を抱いたりする。消費者が関心抱き、思わずクチコミしたくなるには、良い意味で期待をいくらか裏切る内容であるのが肝心である。
接触方法という点では、「デジタルと対面の2段階コミュニケーション」や「直接的な経験」を活用するのが有効だろう。デジタル・メディアで拡散された情報は、親密な他者から対面で伝えられることで、さらに強い影響力を発揮する。SNSで知った話題を、家族に伝えたり、教室や職場で友達に話したりするといったケースである。このためには「デジタルで拡散→対面的コミュニケーションで浸透」という、デジタルと対面を組み合わせた2段階のコミュニケーションを設計することになる。さらに、店頭や街で見かけた、友人が持っていた、試しに使ってみたといった直接的な経験も、強力なコミュニケーション効果を発揮する。
つながりの育て方
続いて、つながりの育て方である。消費者とつながり続けるための工夫、といってもよいだろう。デジタル化が進んだ現代でも、ブランドとのつながり感は(一瞬で形成されるのではなく)時間とともに深まっていくようである。このため、ブランドとのつながりを育成するには、消費者とブランドが継続的に接触できる場を確保することが大切になる。アプリ、プラットフォーム、オンライン・コミュニティ、実店舗などを活用するのが一般的だが、いずれの場合も(1)手軽で、(2)安心で、(3)新鮮で心地よいことが大切である。
弱くて広い時代において、まず大切なのが手軽さである。消費者にとって選択肢がいくつもある状況では、簡単でわかりやすく、手間がかからず、気楽に利用したり参加できたりすること、つまり心理的なハードルが低いことが求められる。特にZ世代と呼ばれる若い人たちは、SNSや生成AIの普及によって情報を受動的に獲得することに慣れているため、少しでも複雑なものや、手のかかるものに対して、すぐに「自分向けではない」と拒否しがちである。
手軽さという点では、複数のブランドや製品に一度にアクセスできることも重要である。これはいわゆるワンストップ化であり、アプリ、プラットフォーム、コミュニティ、あるいは店舗から、多様な情報やブランドにまとめてアクセスできるようにする。
安心できる場であることも忘れてはならない。多くの消費者が、失敗したくない、嫌な思いをしたくないという気持ちを強く持っていることを、企業は忘れがちである。例えばオンライン・コミュニティであれば、気軽に参加できるとともに、秩序が保たれていることが大切である。このためには、セミ・オープンスタイル(誰もが参加できるものの、企業側が一定のルールの下で管理を行う運営方法)が有効となる。 最後に、新鮮さと心地よさについて考えてみよう。それがアプリであっても、実店舗であっても、変化がなければ消費者は飽きてしまうので、リニューアルやアップデートは欠かせない。しかし変化が速すぎても、せわしく感じることになる。心地よい速度で常に変化することが肝心である。適度な変化が、新鮮さを生み出す。
心地よさを提供する方法はいろいろあるが、消費者が自分のことを優れた存在だと感じられる工夫は、とても有効である。例えば、製品を自分の好きなようにカスタマイズしたり、アプリを思い通りに操作したり、あるいはオンライン・コミュニティに新たな知識を提供したりすることで、気持ちが高まり、有能感を得ることができる。人は誰でも自分のことを有能で優れていると感じたいので、こうした体験を提供し続けることで、多くの消費者がそのアプリ、プラットフォーム、オンライン・コミュニティ、店舗を継続的に利用してくれるようになる。
* * *
いかがだろうか。本稿では3年半にわたる委託研究の成果(のごく一部)を教科書風にまとめてみた。冒頭にも書いたように、本誌には2回にわたり各グループの研究報告が掲載される予定である。またさらに、学術論文として世界にも発信されるはずである。いずれもデジタル時代におけるブランド・コミュニケーションを考えるための、素晴らしい情報だろう。どうぞご期待いただきたい。
委託研究プロジェクトメンバー
今回の委託研究では、7名の研究者の方々に約2年間、「デジタル時代におけるブランド・コミュニケーション」というテーマに取り組んでいただいた。今回、研究報告という形で、2回にわたってご紹介する。