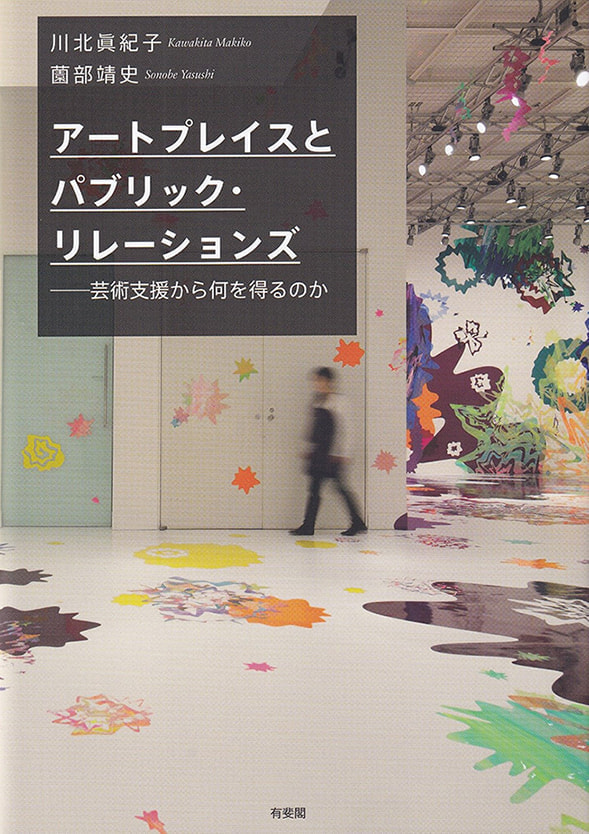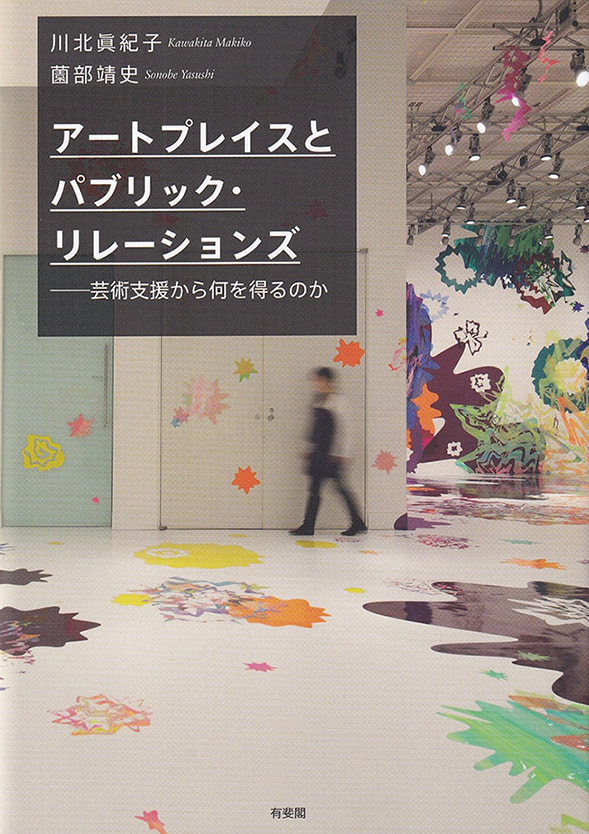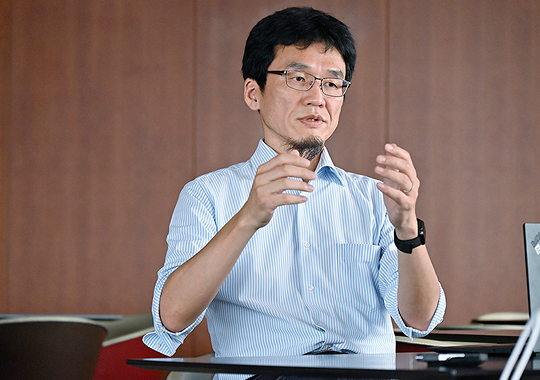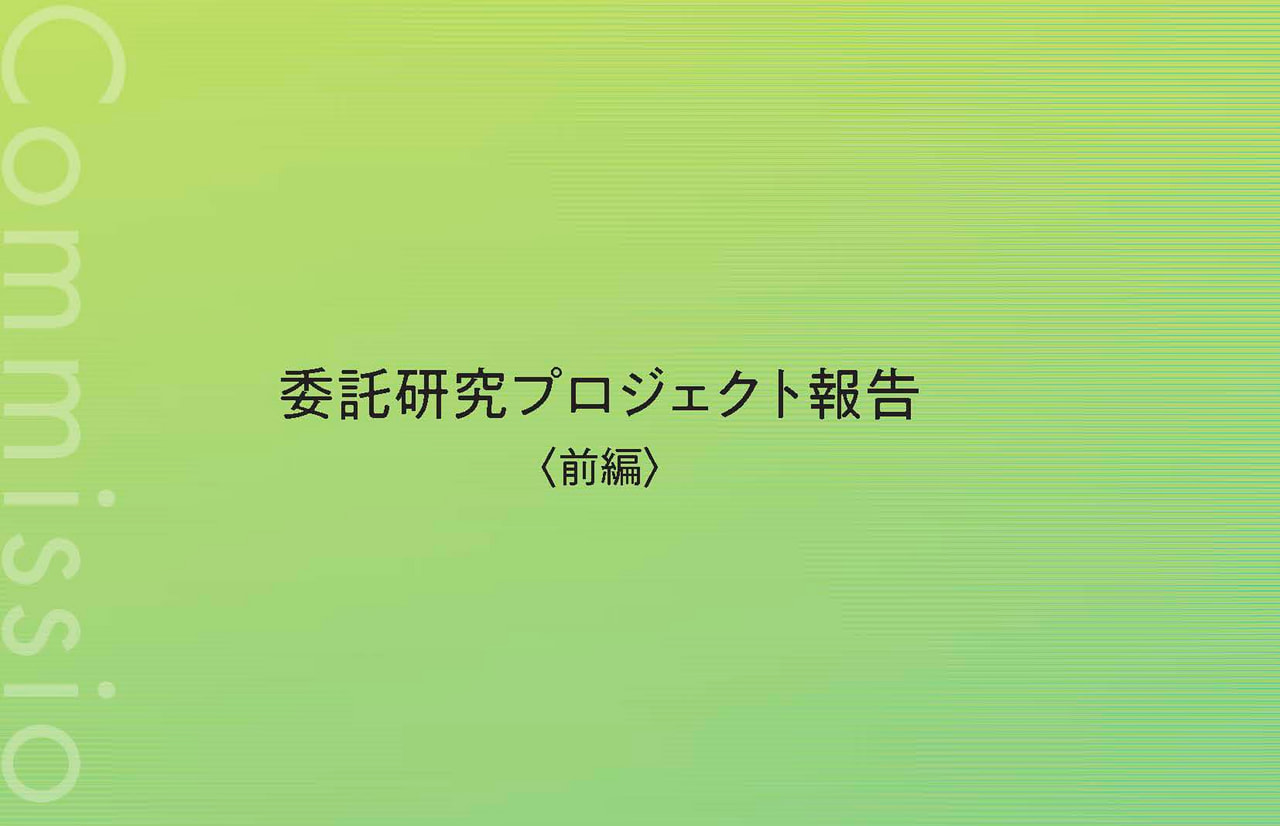企業とアートとの理想の関係とは
— 川北先生は芸術学、経営学を専攻され、広告業にも携わっていらっしゃいました。ご著書の『アートプレイスとパブリック・リレーションズ』は、多角的視点からアプローチされている点に類書との違いを感じました。
川北 私自身、もともと美術に関心があり、大学では筑波大学の芸術専門学群で日本画を専攻していました。卒業後はリクルートに約2年間勤めたのち、広告事務所を立ち上げています。業務を通じてマーケティングを体系的に学ぶ必要性を感じ、慶應義塾大学ビジネス・スクール(KBS)へ進学し、最終的には博士号を取得するに至りました。当初は研究者になるつもりはなかったのですが、経営学に触れる中でその奥深さに惹かれ、学問の道へと進むことになったのです。
趣味でチェロを演奏しており、弦楽四重奏やオーケストラにも参加しています。美術や音楽といった自分の好きな芸術分野に関わる研究を模索する中で、企業による芸術支援が、実はパブリック・リレーションズ(PR)の一環であることに気付きました。広告の実務経験があるため企業側の視点にも通じており、アーティストやキュレーター、マーケターなど、さまざまな立場の考え方もある程度理解できます。こうした自身のバックグラウンドを強みに、研究成果を一冊の著書として形にすることができたのではないかと感じています。
— 想定する読者も芸術支援に関わるさまざまなステークホルダーだったわけですか。
川北 そうですね。メインターゲットは企業の芸術支援や社会貢献の担当者や広報関係者、企業ミュージアムに関わる方など芸術を支援する側の人たちですが、同時に、支援を受ける側のアーティストや芸術組織の方々にも読んでいただきたいと思いました。
本書では、企業が芸術を支援することで得られるさまざまなメリットについて、事例をもとに説明しています。また逆に、その文脈を理解することが、アーティストや芸術団体にとってどのような資金調達のヒントとなり得るかについても提案しています。つまり、アーティスト側が企業の支援をより有効に活用するために、どのような視点や工夫が求められるのかを整理したつもりです。
ただ、芸術関係者の方々の中には、こうしたアプローチに対して慎重な姿勢を示される方もいらっしゃいます。芸術は本来、独立性を重んじるものであり、企業からの関与や助言に対して違和感を持たれるケースもあるように感じます。実際に、「お金で芸術を測られたくない」と率直な声をいただいたこともありますし、マーケティングという言葉自体に抵抗感を抱かれることも少なくありません。
一方で、多くの芸術活動が自治体などからの公的支援に頼っているのも事実です。なかには「補助金は当然の支援である」という意見も見受けられ、その背景には「芸術は社会的に意義のある行為であり、理解されるべきもの」という信念があるのだと思います。
企業側は近年、「資金は提供するが、表現には口を出さない」というスタンスを取ることが一般的になってきています。そうした動きも踏まえ、芸術側にももう少し柔軟で開かれた姿勢が広がっていくと、よりよい関係が築けるのではないでしょうか。大切なのは、支援する側とされる側が対等な立場で、互いを尊重し合える関係性をつくること。その理想を実現するには、まだ乗り越えるべき壁もあると感じています。
変わりつつある美術館の役割
— 文化庁が掲げる「文化芸術推進基本計画(第2期)」の中では、地域における文化コミュニティの形成をうたっています。貴書を拝読して、アートプレイスを通した文化コミュニティの形成が鍵になるのではと思ったのですが、今注目されている取り組みを教えていただけますか。
川北 わかりやすい例として、岐阜県美術館で展開されているアートコミュニケーター「〜ながラー」の活動があります。アートコミュニケーターとは、アートを媒介に、人と人、人と作品、人と場所をつなぐ存在であり、多様な価値観を持つ人々を結びつけるコミュニティづくりに取り組んでいます。
活動に参加しているのは、会社員、学生、主婦、退職後の方、フリーランスなど、実にさまざまな立場の人たちです。取り組みの内容も幅広く、ラジオ番組の制作、地域の建築を巡る解説ツアー、対話による鑑賞の企画、子ども向けの読み聞かせなどの実績があり、いずれもアートコミュニケーター自身が手を挙げ、自発的に取り組んでいます。活動の場は美術館内に限らず、地域に出て屋外で展開することも可能で、自由度の高い仕組みが特徴です。
この活動はもともと、東京都美術館と東京藝術大学が連携して始めたソーシャルデザインプロジェクト「とびらプロジェクト」に端を発します。美術館を拠点に、アートを通じてコミュニティを育むことを目的とした取り組みで、一般から公募されたアート・コミュニケータ「とびラー」が、学芸員や大学教員、現役の専門家とともに、美術館の文化資源を活かしながら人と人、人と作品、人と場所をつなぐ活動を続けてきました。この取り組みは、現在少しずつ全国に広がりを見せています。
— アート関係者だけではなく、異業種の人たちが広く関わることが大事なポイントに感じました。美術館という場が、つながりを生み出す場になっているのですね。
川北 近年、美術館の役割が変化してきているのを、確かに感じます。かつては「芸術を庶民に届ける」といった、いわば上から下へという意識がどこかにありましたが、近年はその構造が大きく変わってきました。アートを広く社会に伝えるという役割は今も変わりませんが、それに加えて、芸術や文化を通じて人を育てたり、人々の心を元気にしたりといった、新たな役割も担うようになっています。
市民の側の価値観にも変化が見られます。例えば名古屋や岐阜のような地方都市でも、若い世代の人たちはアート活動に対して抵抗感が少なく、きっかけさえあれば積極的に関わろうとする傾向があります。私たち中高年世代にとっては、美術館といえば「モネ展を観に行く」といったイメージが一般的でしたが、今はそうしたかたちだけではありません。もちろん、今も名画を楽しむ人は多くいますが、それと同時に現代アートなど新しい表現に関心を寄せる人も増えており、美術との向き合い方が確実に変わってきていると感じます。
美術館の機能という点では、近年、館内に併設されたカフェやショップを楽しむ人も増えていますね。この動きの背景には、世界的な潮流があります。2019年に開催された「第25回国際博物館会議(ICOM)」京都大会では、大会テーマが「“Museums as Cultural Hubs : The Future of Tradition”」(文化をつなぐミュージアム—伝統を未来へ—)というものでした。大会決議文ではアジア重視と「文化をつなぐミュージアム(Museums as Cultural Hubs)」が採択されました。
世界のミュージアムにおけるムーブメントが節目を迎えたと感じています。つまり、ミュージアムは本来アーカイブ機能を担う場ですが、そこにとどまらず、蓄積された文化的資源の上に未来のイノベーションや個人の世界がつながっていく。そうした新たなコンセプトが明確に打ち出されたのではないでしょうか。
言い換えれば、ミュージアムは「過去」と「未来」を結ぶハブとしての役割を果たす場になりつつあります。これまでのミュージアムは、美術品を展示・保存する場として始まり、その後、人々が集い交流する「センター機能」が加わりました。そして今、「未来への接続点=ハブ」としての新たな機能が注目されているのです。
「アートプレイス」が地域文化を生む
— アートプレイスとしては近年、大型ショッピングモールもその機能を担っているように感じます。買い物だけではなく、人々が集う場、エンターテインメントの場所であったり、地域の寄り合い所みたいな役割もあったり。商業施設がアートプレイスの機能を持つことで、経済的な側面、消費拡大などにもつながると思うのですが、どう考えられますか。
川北 非常に大きな可能性を感じられますね。ショッピングセンターや観光地など、人が集まる場所を設計する際には、その地域固有の文化をどのように取り込むかが、これからの重要な視点になると思っています。
アートプレイスのあり方にはさまざまな形があります。美術館が主導してコミュニティを育むケースもあれば、企業が主体となって展開する事例もある。私が今特に注目している、企業主体の取り組みが、良品計画の活動です。同社では「ソーシャルグッド事業部」を設け、地域貢献を通じた活性化や新規事業の創出に力を入れています。キーワードは「土着化」。企業の独自性を発揮しながら社会に貢献し、人と人とがつながっていく—私自身の研究テーマとも重なる領域であり、大変興味深く見ています。良品計画は、それを非常に丁寧かつ効果的に実践している企業だと感じています。
例えば、同社の旗艦店の1つである「無印良品 グランフロント大阪」では、売り場の一角をイベントスペースとして活用し、「無印良品らしさ」と地域とのつながりを融合させたさまざまな催しを展開しています。2024年5月には、「大阪もん つながる市」というイベントを2日間にわたって開催しました。大阪府では、地元産の農産物や畜産物、水産物、林産物などを活かした加工品を「大阪産(もん)」と名付けていますが、このイベントでは、そうした地元食材を活用した商品をセレクトし、地域の魅力を伝える場をつくっていました。興味深いのは、自社商品だけでなく、競合になり得るようなお菓子などの製品も並べられていた点です。利益重視というよりも、地域の魅力を伝えるというコンセプトが優先されていることがうかがえます。
さらに「大阪といえばお笑い」という文化にちなんで、「無印良品 お笑い&おもしろかくれんぼ」というイベントも開催。若手芸人による漫才やコントの披露に加え、無印良品の衣料品を使ったファッションショーも行われ、幅広い層にアプローチしていました。
こうした取り組みは、「この地域にとって必要とされる店になろう」という信念に基づいています。従来の店舗運営とは異なる発想で、地域の文化や人とのつながりを大切にする、ソーシャルグッドな考え方に立脚した活動だといえるでしょう。そこには、企業として地域と共生しなければ持続可能な経営は難しいという認識もあるはずです。
一方、全国展開している大手ショッピングモールなどは、どの地域でも似たような建物構成やテナントが並び、社会インフラとしての機能としては重要なプレイヤーですが、アートプレイスという観点から見ると、どうしても画一的で味気なく映ってしまいます。
— 確かに、その土地ならではの個性は感じられませんね。
川北 私はPRの研究者なので、パブリックリレーション、つまりさまざまなステークホルダーとのコミュニケーションに注目しています。従業員と地域住民がつながり、さらに投資家なども集うような場に、いかにアートや文化を組み込んでいくか。そこには大きな可能性がある一方で、非常に手間のかかるプロセスでもあります。特に重要なのは、アートや文化の特性を理解している人が、全体を適切にコントロールすることです。単に空間を提供するだけでは、期待される価値は生まれません。
その点で、先に触れた「無印良品 グランフロント大阪」の取り組みは秀逸です。イベントスペースにおけるキュレーションが巧みで、プロジェクトの趣旨にふさわしい出展者がしっかり選定されています。いわば、キュレーター的な役割を担う人がプロジェクト全体の質を担保しているのです。
こうしたキュレーションが不十分だと、単に「無料で出店できる場」として利用されてしまい、結果的にコンセプトが曖昧で、内容に乏しいイベントになりかねません。だからこそ、アートを取り入れた場づくりには、戦略的な視点と専門的な知見が不可欠なのです。
— アートプレイスという場合、基本的に芸術、美術や音楽に限定されますが、人々が集う場と考えると、もう少し広く地域文化として捉えることもできるわけですね。
川北 そうですね。著書の中では「アートプレイス」を、美術や音楽などの芸術が存在し、かつ人々が集う場、という狭義の定義で捉えています。ただ、近年はその枠組みを少し広げ、アートに限らず、地域文化や地域貢献的な活動も含めて考えるようになってきました。こうした活動も、人と人が集い、対話が生まれ、文化が交差するという点で、アートプレイスと同じ機能を果たしているのではないか。そう感じるようになり、私自身の研究領域も芸術にとどまらず、企業の地域貢献へと広がりつつあります。
愛知県田原市の渥美半島に拠点を構える「渥美フーズ」という地場のスーパーマーケットがあります。同社は「オアシスファーム」という取り組みを通じて、自社のスーパーやレストランから出る野菜くずなどの食品残渣を活用し、循環型農業を実践しています。耕作放棄地を再活用して、鶏や牛を飼育したり、果物やはちみつの生産を行ったり、多様な農業活動に取り組んでいるのですが、これらの活動には地域の人々も参加し、定期的に体験型ツアーを開催するなど、交流と学びの場としての機能も果たしています。地域課題を肌で感じられる教育的な機会を提供しながら、人と人が集う拠点にもなっているのです。
さらに同社は、地域で50年間営業していた商業施設「ショッピングセンター レイ」の閉店に伴い、その運営を引き継ぐ新会社「あつみ編集舎」を設立し、そこに「あつみの市 レイ」をオープンさせました。現在では、渥美半島最大級の醸造所でクラフトビールを製造し、ブリューパブで提供するほか、パン工房、食堂、ゲストハウスなども手がけ、多面的な地域プロジェクトを展開しています。地元住民のみならず、観光客も巻き込みながら、人の流れを生み出し、地域に新しいつながりをつくっています。実際、東京大学大学院を中退して移住してきた若い女性や、海外から移住した外国人など、多様な人々がこのプロジェクトに関わっています。
社名の「あつみ編集舎」が象徴するように、私は「編集」という概念が、地域における場づくりの鍵になると考えています。地域に根差した文化や資源をいかに掘り起こし、独自の価値を持った「場」として編集し直すか。こうした視点がなければ、どの地域も同じようなショッピングモールばかりが並ぶ、画一的な風景になってしまうでしょう。
— 地域の企業が果たせる役割は大きいですね。
川北 そう思います。業種で見ると、地域と密接に関わる流通業に、こうした取り組みは特に多い印象があります。地域に受け入れられ、尊敬されなければ、ビジネスの継続は難しいという前提があるからでしょう。
私が注目しているユニークな事例が、大橋運輸という運送会社です。大橋運輸は、地域で最も信頼される会社を目指すため、オオサンショウウオが生息する川の清掃や、学校の授業として交通安全教室と食育指導を行うなど、地域に根差した活動を続けています。同社は15年以上前から健康経営を実践し、社内に蓄積された健康ノウハウを地域にも還元しようと、管理栄養士である社員が健康相談や健康セミナーも開催。さらに、地域の方々に運動の機会を提供するため、バランスボールやヨガ、太極拳教室を毎月2回ずつ開いています。こうした活動を通じて、地域課題に気付くようになったといいます。
具体的には、けが予防や震災対策としての生前整理に注力したり、「人生会議(厚生労働省が推奨するアドバンス・ケア・プランニングの名称。自分らしい最期を迎えるため、希望するケアを家族や医療者と事前に話し合う取り組み)」啓発のためにオリジナルのエンディングノートを無償配布したり、特殊詐欺被害の防止に取り組んだりするなど、さまざまな地域活動を展開してきました。実は、この生前整理が新たなビジネスの契機にもなっているのです。
地域と顔の見える関係を築くことで人材採用にも良い影響が出ています。採用が難しいとされる運送業においても、地域の人々が「どんな会社か」を知っていることで、求人の応募は年々増えているそうです。
芸術がもたらす多元的な視座
川北 多くの企業でCSR担当者の方に話を聞くと、「社員にもっとボランティア活動などに参加してほしい」と考えているものの、現実には「仕事のほかに、そんな時間は確保できない」という声が少なくありません。そこで私が提案したいのが、勤務時間の5%や10%といった一部を、社会貢献活動にあてる制度です。月に1日だけでも構いません。経営側からは「その余裕はない」「業務を優先すべきではないか」と言われるかもしれませんが、実は逆で、本気で取り組めば、企業はむしろ強さを手に入れられるのではないかと考えています。
多くの企業は、取り組みが中途半端であるがゆえに、そのメリットを実感できず、本腰を入れにくい—そんな悪循環に陥っているように思います。その点、渥美フーズやこの大橋運輸のように、経営者が本気で、全力で地域と向き合っている例を見ると、そこには確かな成果と手応えが見られるのです。
これはまだ私の仮説段階ではありますが、近いうちに、こうしたテーマで論文をまとめてみたいと考えているところです。
— アートに関する活動も、社会貢献活動も、リターンがあるはずだけれども、プロジェクトとして提示する段階で、それを数値化して示すのが難しいですよね。
川北 そうなんです、明確には“示せない”。逆に言えば、もしそれが示せてしまうなら、アートではないのではないかと思うこともあります。アートとは、おそらく「価値がまだ定まっていないもの」に、あえて価値を置こうとする営みなのだと思います。現代アートを見ればわかるように、今の時点では評価が定まらず、将来価値が生まれるかどうかもわからない。にもかかわらず、そこにこそ意味を見出そうとする態度。それが芸術の本質ではないでしょうか。
よく聞かれるのが、「スポーツとアートは何が違うのか?」という問いです。企業がスポーツを支援するのと、芸術を支援するのでは、どこに違いがあるのか。私自身は、最大の違いは「価値が確定していないものに接触する」という点にあると考えています。その不確かさに向き合うこと自体に、大きな意味があるのです。
もちろん、芸術支援によって企業のブランド価値を社外に向けて高めるという目的はあります。しかしそれだけでなく、社員がアートに触れたり、アーティストとともに活動したりすることを通じて、これまでにない視点や価値観に出会うことができる。つまり、既成概念にとらわれない発想を得る機会にもなり得るのです。実際、企業の広報やPRの企画書を見ていると、従来の手法や前例に倣った施策が多く見られます。しかし、社会や価値観は日々変化しており、昨年の正解が今年も通用するとは限りません。こうした変化に対応していくためには、視点や価値観のアップデート、あるいは柔軟性が欠かせません。
その意味でも、アートに触れることは、多元的な視座を得るために有効な手段です。不確実性がますます高まる時代に、自分にはすぐには理解できないものに出会い、戸惑い、考えを巡らせる。そのプロセスこそが、発想力を養い、新しい社会への適応力を育てていくのです。
組織や企業の中で、斬新なアイデアを出したり、突拍子もない発言をしたりする。そうした人を、排除せずに受け入れる。組織のメンバーがチャンピオニング(擁護)できる感覚を持つことが大切です。そこから建設的で活発な議論が生まれ、イノベーティブな製品やサービスが生まれる可能性があります。そのためにも多くの社員がアートに触れる機会を設け、アート的な思考に対する理解を深めることが大事だと考えています。
文化を軸にコミュニティを育てる
— アートや地域文化を含め、これからの文化活動について先生が考える理想のイメージをお聞かせください。
川北 どの地域にも、その土地に根差した土着の文化や芸術があると思います。子どもの頃から、日常生活の中で自然にそれに触れる機会があるといいなと感じています。
例えば、京都の祇園祭にまつわる話を、京都で開かれた学会で聞く機会がありました。印象的だったのは、京都の人々が持つ時間感覚の長さ、そして物事を捉える視野の広さです。多くの老舗企業が地域文化に積極的に投資していますが、驚くことに「自分の代で回収する」という発想はまったくなく、「三代先を見据えて」動いているというのです。
では、そうした考え方はどこから生まれているのか。おそらく、祇園祭のような地域行事を、地域の人たちが一緒に維持してきた歴史があるからではないでしょうか。お囃子の練習をしたり、祭りの準備に関わったりしながら、一緒に盛り上げ、次世代へと受け継いでいく—そうした営みの中で自然と価値観が共有され、同じ方向を向いて動く土台が築かれているのだと思います。つまり、その地域ならではの価値観や文化を、生活の中で大切にし、共有しながら育んできた人々には、強さがあると感じます。京都のブランド力は言うまでもありませんが、世界に通用するその力は、まさに長い時間をかけて育まれてきた独自の文化的価値観に支えられているのだと思います。
京都のような特別な例でなくとも、どの地域にもその土地固有の歴史や文化があります。そうした地域文化を改めて見つめ直し、掘り起こし、文化コミュニティとして形成していく。そして地域の人々が主体的に参加し、守り育てていくことが、これからの地域づくりにとってますます重要になっていくのではないでしょうか。
— アートに限定して考えるとハードルが高く感じますが、渥美フーズや大橋運輸の例のように、まずは足元でできる範囲で実践していくことはできそうな気がします。そうした活動によって地域の人たちが交流できる場ができ、小さな成功体験を積み上げていくことで、いずれアートも取り入れていけるかもしれませんね。
川北 そう思います。私も共著者の薗部靖史先生(東洋大学社会学部教授)も、そうした人々の交流の場を「空間メディア」として捉えています。美術館も空間メディアであり、先ほどの「あつみの市 レイ」というスペースも空間メディアと捉えられるわけです。アートでも、地域文化でも、そこに何かがあることによって人が集う場所は、空間メディアになります。
今、従来の広告がなかなか効かないといわれています。そして、ソーシャルメディアばかりになって、とにかく瞬間的に注目を集めればいいというような風潮もあり、予期せぬ“炎上”も増えています。そんな中で、リアルなコミュニケーションは、新しい広告ツールとしても注目されているのです。人々が直接会って、話をして、一緒に協働する。もっとリアルな空間メディアを重視しましょうというのが、薗部さんと私の今の主張です。
企業にとっても、良品計画のように実店舗を活用した取り組みは、今後ますます重要になっていくと思います。SNSによる広告や発信も有効ではありますが、それはあくまで、リアルなコミュニティとの接点を補完する手段にすぎません。実際に人と人が直接会い、コミュニケーションを取る場があることで、製品が生まれた背景や企業文化、「なぜこの会社がこの商品をつくっているのか」といったストーリーが、より深く、生活者に伝わるのではないでしょうか。
リアルな空間を“メディア”として活用するという発想は、企業に限らず、自治体や美術館など、さまざまなプレイヤーにも広がっています。なかでも、地域に根ざした文化コミュニティの形成という観点から見ると、成功している事例には、手間暇をかけているという共通点があると感じます。それは、「その地域を本当に愛している人」が起点になっているということです。
地域を盛り上げる、地域への愛着を育てるといった取り組みには、その土地の文化や歴史を深く理解している人が欠かせません。そうした人々が中心となり、周囲を巻き込みながら、対話と共創を通じて地域文化を育てていく。そうした姿勢が、持続可能なコミュニティ形成の鍵になるのだと思います。