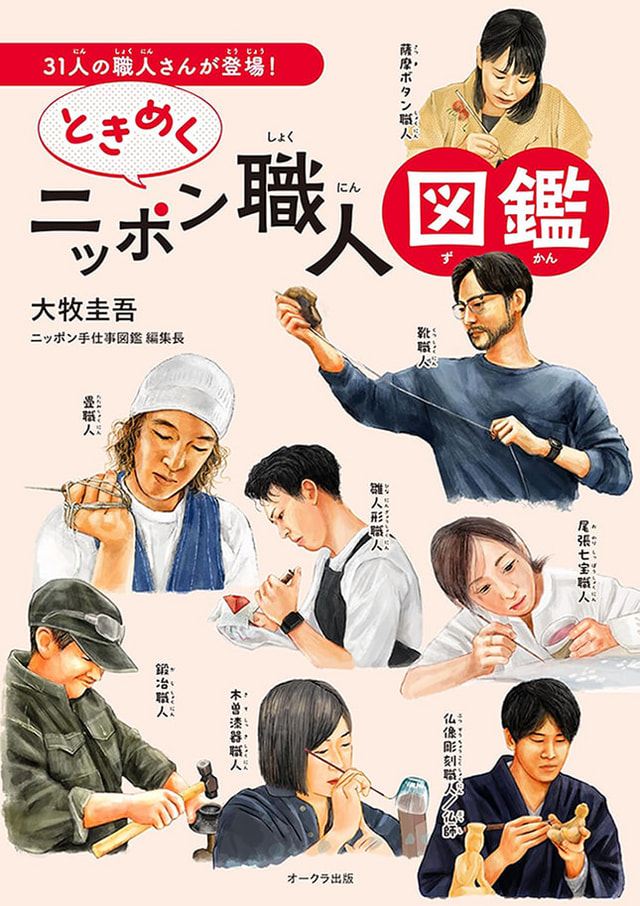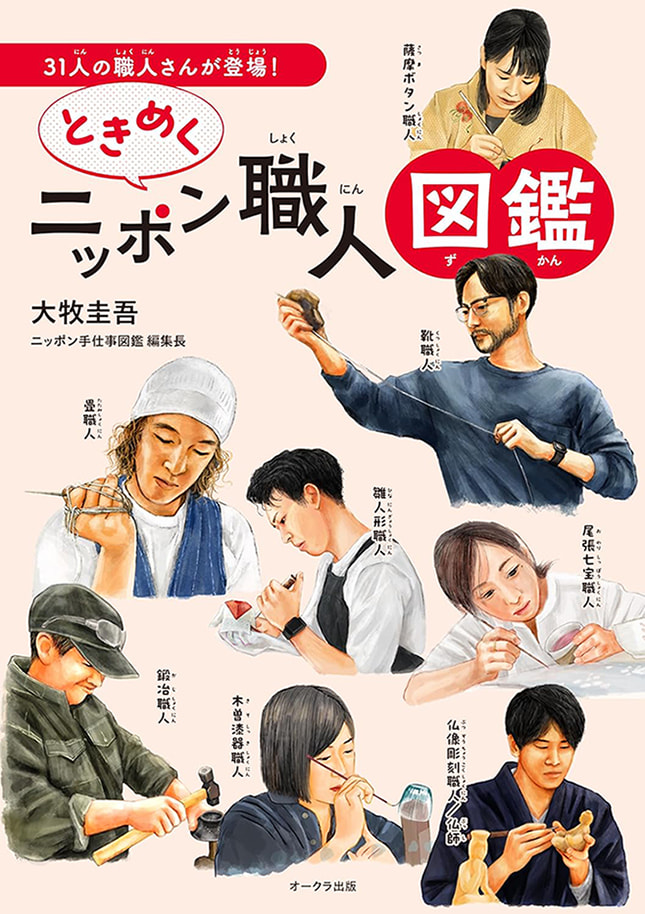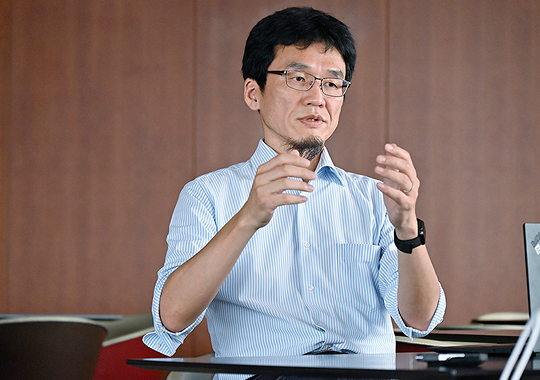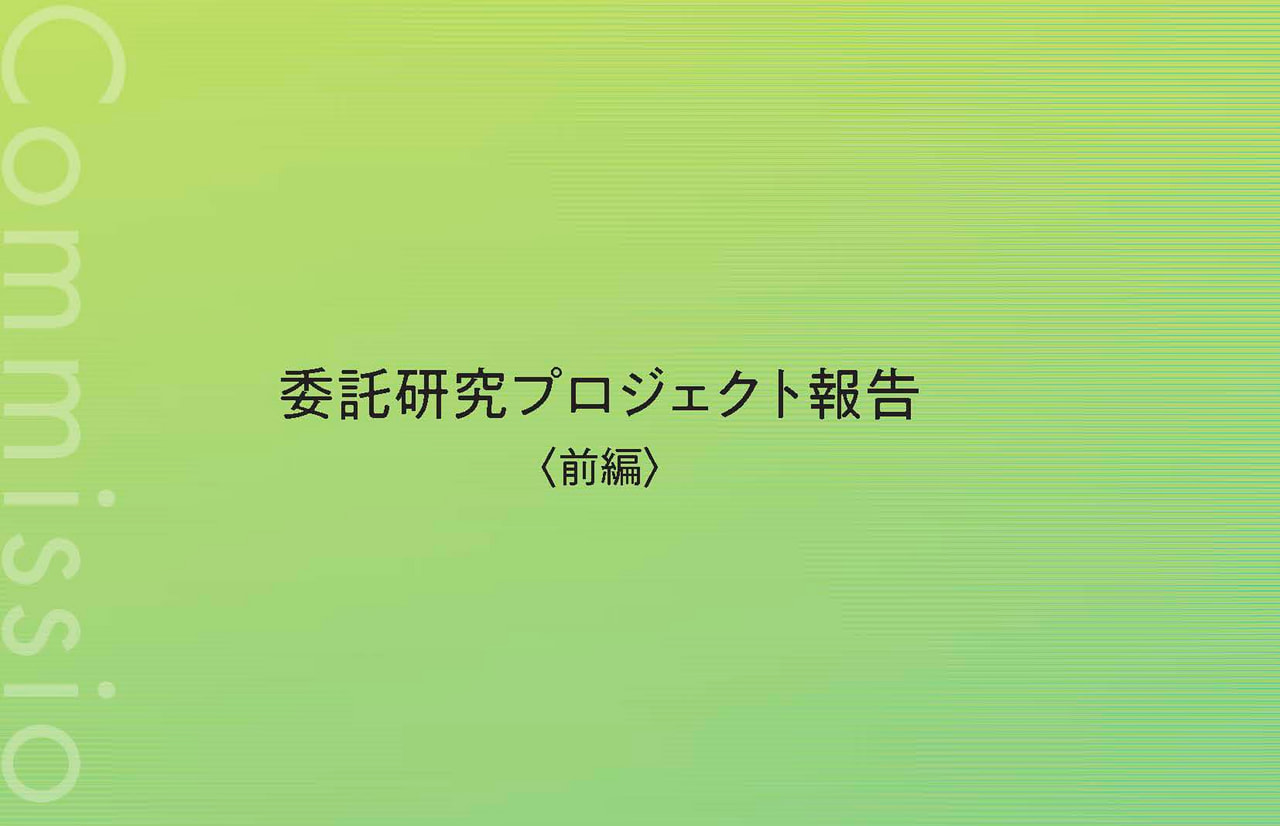街の個性を生むのは「手仕事」
— 日本全国の職人が持つ技術や想いを動画で紹介する「ニッポン手仕事図鑑」を運営されています。初めに、メディア立ち上げの経緯を教えてください。
大牧 「ニッポン手仕事図鑑」を始めたのは2015年1月ですが、実はスタートの時点では、伝統工芸や職人に特化したメディアをつくるつもりではありませんでした。「職人」ではなく「手仕事」と題しているのは、そのためです。僕は「それぞれの地域にある、農業のような一次産業や、地元の人に愛される食堂、家族でやっている個人クリーニング屋さん。土地の文化を形づくるのは、そうした“手仕事”をする人たちなのではないか」という仮説を持っています。そうした人たちの仕事を紹介し、地場の仕事を応援するサイトをつくろうと考えたのが、メディア立ち上げのきっかけです。
— どうして「手仕事がその土地の文化をつくっている」という考えに至ったのですか?
大牧 僕は長野県安曇野市の生まれですが、父は京都出身、母は長野出身で、幼い頃からそれぞれの故郷に行く機会がありました。でも大人になってから、父のふるさとでも母のふるさとでも、街の個性や昔からの風習がどんどん薄れてきているという実感があったのです。地場の産業が衰退し、その街で働く人が減っていく—そのことが、街の個性の消失につながっているように感じました。そこから、「それぞれの街の手仕事を残していくことが街の個性を残すことにつながるんじゃないか。そこにフォーカスする地方創生の道があるかもしれない」と考えるようになったのです。
僕はこの仕事を始めるまで、伝統工芸との接点はまったくありませんでした。ある日、それまでコピーライターとして勤めていた会社での仕事を通して、まだ創業したばかりのファストコム(「ニッポン手仕事図鑑」を運営する親会社)と出会います。小林栄治社長に、地方創生に対する自分の想いを話したところ、「一緒にやりましょう。ファストコムでその夢を叶えてください」と声を掛けてもらい、2013年に入社することになったんです。そして、ファストコムの新規事業として、「ニッポン手仕事図鑑」をスタートさせました。
— 持続可能な文化支援を目指す上で、営利企業として取り組む意義はどこにあるとお考えでしたか。
大牧 実は、当初はあまり売上のことは考えていませんでしたね。映像をつくるチームのメンバーには、「3年間、売上はゼロでいい」と言っていたほどです。とにかくいい映像をつくって、メディアのファンを増やし、知ってもらうことが大事だと。この場合のファンとは、映像に出てもらう職人さんたちと、映像を見てくれる人たち、両方を含んでいます。メディアとして広告収入を得ようとすると、ページビューを稼がないといけなくなります。数を稼ぐことを一番の目標にすると、早々に疲弊してしまうと感じたのです。そこで、一般的なメディアのスタンダードなマネタイズの方法はすべて断った上で、「じゃあ自分たちは、何を武器にしてどう生き残るか?」と考えました。広告費などは一切いただかないことにして、3年間は実際に売上が1円もありませんでした。
— その間、運営資金をどうつないでいたのでしょう?
大牧 ウェブ制作や企画を手掛ける親会社、ファストコムでの映像制作、ホームページ制作の受注を業務として、「ニッポン手仕事図鑑」はそのための名刺代わりと位置付けました。「職人やものづくりの魅力が伝わる、こんなに素敵な映像をつくっている人たちにぜひ、映像制作を頼みたい」「自分たちも、コンテンツをつくってほしい」と思ってもらえるようなブランドになればいいと考えたわけです。この方針は今振り返っても間違いではなかったと思います。お金を稼ぐことを目標にしてコンテンツをつくると、逆にファンを増やせないということがありますから。僕自身はその間、受注業務としての映像制作を行いながら、それとは別に「ニッポン手仕事図鑑」を運営していました。年中無休でやる覚悟でしたね。
— 現在は「ニッポン手仕事図鑑」として、独立したビジネスができているのですね。
大牧 はい。立ち上げから10年で、100本ほどの映像を制作していますが、そのうち80本くらいは自費でつくったもの、20本ほどは行政から依頼を受けて制作したものです。というのも、新型コロナが流行し始めた時期に、全国各地の催事が相次いで中止になり、発信機会を失った行政から「自分たちの地域の文化について情報を発信したい。映像で紹介してくれないか」という依頼があったのです。
コロナ禍前は、そういった行政からのオファーもすべて断り、あくまで自費でつくることにこだわっていたのですが、コロナ禍で地方が受けた打撃の大きさを知り、行政の仕事だけは受けることにしたのです。一方で、職人さんからお金をもらって宣伝のための映像をつくるということは、今も一切していません。
共感を醸成する伝え方
— 技術や文化を可視化し発信する上で、動画メディアを選ばれた理由はどこにあったのですか?
大牧 自分自身、もともとライターとして文章を書いていたため、「なぜ映像メディアにしたのか?」ということはよく訊かれます。背景には、2011年の東日本大震災があります。震災の後、被災者の皆さんにお話を伺う機会があったのですが、そのときに聞いた言葉の重さが、とても心に残ったのです。その方たちが話してくださった言葉は決して、難しい、複雑な言葉ではありません。「一生懸命頑張っています」「街を、復興させたいと思っています」といった、文章にしてしまうと当たり前に思えてしまう言葉。でも、実際にお話を聞いていると、言葉にはのらない重さがある。それは、話す人の声や表情、身振りに起因するものです。言葉自体は平易でも、声や映像にはその人の「想い」を伝える力がある。その手ざわりこそが、受け手に届けたいものだと思ったので、動画という形を選びました。
— コンテンツを発信する上で、「共感」や「関心」を促すため、どのような伝え方や仕組みを意識されていますか。
大牧 僕たちの映像は、一般的な記録映像とは違う、いわば「『想い』の記録映像」。そこで力を発揮するのは、先程もお話ししたように、やっぱり「声」ですね。これは間違いないと思っています。
職人さんの作業風景を見せるだけなら、今は職人さん自身がスマートフォンをセットして自撮りすれば、簡単にできてしまいます。しかしそれができたとしても、「その伝統工芸の技が将来途絶えてしまったときに、その映像をもとに技術を復活させられるか」といえば、ほとんどの職人さんが「無理です」とおっしゃいます。
それはなぜかというと、ものづくりには技術だけではなく「想い」が必要だからです。ここでいう「想い」というのは、お客さまへの感謝の気持ちだったり、道具への思い入れだったり、その工芸の歴史に対する敬意だったりします。そうしたものがなければ、工程だけ見ていても技を再現することは難しいんですね。
そしてその「想い」を引き出すには、自撮りでは難しい部分があります。聞き手がいないところで、1人、カメラの前に立って「想い」を語るというのは、なかなかできないですから。僕たちは、会話を重ねるように取材を進め、内にある「想い」を引き出していきます。完成した映像を見た職人さんからは、「自分はこんなふうに思っていたんだって、初めてわかった。自分でも驚いた」といわれることがあります。その言葉をいただいたとき、「この方向性でよかったんだ」という実感を得られました。
「想い」を伝えることで、見た人の心には共感が生まれます。「この人に会ってみたい」「この人のつくったものを買ってみたい」「こういう人になりたい」 —そう考える人が少しずつ増えていくことが、大切だと考えています。
— そうした内容につくりあげるために、取材前にシナリオを考えるなど、下準備があるのでしょうか?
大牧 こちらで流れを決めるような下準備はしません。というのも、準備すると「知った気」になってしまうからです。自分自身が現地に行って初めて感じたことや、「なんでこういうやり方をしているんだろう?」と、知識がないからこそ生まれる純粋な疑問や驚きを守りたいから、できるだけフラットな状態で話を聞きたいと思っているんです。
取材前にはインタビューシートもつくりません。取材中にシートに目を落としてしまうと、そこで会話が途切れてしまうからです。僕は、できるだけ相手から目を逸らさずに話し続けたい。
職人さんには「いいところだけを使うんで、30分だけ、おしゃべりをさせてください」とお願いしています。「30分も話すことなんて、ないよ」といわれたりもしますが、話しているうちに、1時間ぐらいはすぐに経ってしまいますね。
「職人さんには寡黙なイメージがあるから、取材が大変そう」といわれることもありますが、そんなことはまったくありません。僕はこれまで、話すのが苦手な職人さんには会ったことがないです。自分の仕事に対する「想い」をしっかり持っているから、語る言葉をたくさん持っているのです。取材というより、会話の中で「想い」を聞いていく。そうすることで「おっ」と思うような言葉が出てくることがあります。ご本人が「今、俺すごいこと言っちゃったな」っておっしゃることもあるんですよ(笑)。
継承の課題と、希望
—全国各地で伝統工芸の職人さんたちと向き合ってきた上で、ものづくりの現場で共通する課題は何だと感じておられますか。
大牧 それぞれの土地で異なる課題を抱えていますが、全体としていえることがあるとすれば、「つくる技術はあるけれど、売る力がない」ということですね。いいものをつくっても、売れなければ従業員も雇えないし、後継者の育成もできません。
安定した売上を維持する産地では、自然と後継者も育っているという傾向があります。あるいは、自治体が強い危機感を持って、「地場産業を守っていこう」と本気で取り組んでいる地域もあります。
— 伝統工芸の支援に熱心な自治体とそうでない自治体との違いは、どこにあるのでしょうか。
大牧 ある地域で、地場産業が伝統工芸しかなければ、「これを守らなければ」という意識が生まれやすいですが、実際には農業もあれば、ほかの産業もあるわけです。行政は、さまざまな産業への支援のバランスを考慮しないといけません。そのときの市長や知事が、地場産業をどれだけ重視しているかによっても、行政の方針は変わってきます。担当者の想いの熱量も、さまざまです。
また、同じ産地で何人かのつくり手がいる場合、団結できるかどうかも重要なポイントだと思います。地域全体で合意が取れていない産地では、新しい取り組みも、難しくなってきます。
— 伝統工芸の製品を「売る」ためには、何が必要になるのでしょうか。
大牧 まずは「知ってもらう」ことが必要です。ですが、SNSで情報発信すればすぐに売れるというわけではありません。マーケティング視点を持って、消費者が求める製品をつくっていかなければいけないし、商談会などを通じて販路を開拓していく必要もあります。多くの産地にとって、この最初の一歩が高いハードルになっていると感じます。
一口に伝統工芸といっても、職人さんが顔を見せているところもあれば、工房の名前すら出していないところもある。例えば、織物などでは産地ブランドだけで、個別の工房の名前が出ていないケースもあります。そうなるとメーカーは、問屋や百貨店に対して立場が弱くなり、新しい販路の開拓もできなくなってしまうのです。
もっとも、職人さんにもいろいろな方がいて、仲介を入れず自分自身で販売していこうという人や会社もあります。
— 「ニッポン手仕事図鑑」では、「後継者インターンシップ」という、伝統工芸の工房と若い人たちをつなぐ取り組みも行っています。
大牧 後継者がいないまま職人さんが高齢化し、今まさに存続の危機にある伝統工芸は全国にたくさんあります。後継者インターンシップは、産地の事業者さんごとに参加者を募って、現地で1、2泊一緒に過ごし、その中で職人さんが「この人を後継者にしたい」と決め、内定を出すという、ちょっと長めの採用面接のような仕組みです。本格始動から今年で5年目を迎え、現在は行政とも連携しながら取り組みを進めています。移住後の生活支援までを民間単独で担うのは現実的に難しい部分もあり、官民の協力が不可欠だと感じています。
— そうした取り組みを始めたきっかけは何ですか。
大牧 日本の伝統工芸は、販路の開拓や商品開発、パッケージデザイン、情報発信といった分野には、すでに多くのプレイヤーがいます。でも「後継者がいない」という課題に対しては、実は、国や自治体、そして民間にも、ほとんどプレイヤーがいない状況なのです。
そこで2018年、まずは私費で2年間、試行的にマッチングに取り組んでみることにしました。手探りではありましたが、「うちのサイトを通じて声をかければ人は集まるだろう」という確信はありました。というのも、全国にある伝統工芸を学べる学校をリストアップしてみると、60~70校もある。ここに、「職人になりたい」という若い人がいるんじゃないかと、ポテンシャルを感じていたからです。
「とにかくまずは現地に連れて行くことが大事だ」と考え、4回に分けて、現地に若い人たちを6人ずつ連れて行きました。「参加者の中から誰かが後継者に内定します」と伝えて参加者を募ったところ、4回ともすべて10倍以上の倍率になりました。なんと、毎回60名以上の応募があったのです。そしてこの4回のインターンシップを通して後継者を誕生させることができ、確かな手応えを感じました。
後継者インターンシップはその後、総務省からも支援を得られることになりましたが、本格的にやっていこうとした矢先に新型コロナが流行。2020年の1年間は活動を自粛せざるを得ませんでしたが、その後、2021年から再開しました。
これまでに合計61回開催し、全部で3,200人以上の応募がありました。61回のうち59回で内定者が出て、98人が内定を受けています。そのうち2割ほどが辞退しましたが、77人の新しい職人が誕生しました。
誕生した77人の職人は76%が「Iターン」なんですよ。つまり「この仕事がしたい」という一心で、縁もゆかりもない土地に移住する決断をしたわけです。その後に辞めていく人もいますが、1年以上定着している人の割合は80%あります。この後継者インターンシップは、伝統工芸の担い手を募る仕組みとして、理想に近い形ではないかと感じています。
— 60回以上も活動を続けていると、それが新たな強みになってくるでしょうね。
大牧 実際に成功事例が出て、それが各産地に知られるようになってきたことは大きな成果です。これまで多くの伝統工芸の産地では、「今どき、あえて伝統工芸の道を志す若者なんていない」という認識が根強くありました。でも実際に募集したら3,000人以上の応募があり、後継者が誕生している。この事実が浸透することで、「うちの地域でもできるかもしれない」「若い人にも興味を持ってもらえるんだ」という前向きな空気が生まれてきたし、僕たちも「ほかの産地の成功事例を共有する」という形で、活動の紹介ができるようになってきました。
今、「伝統工芸インターン|ニッポン手仕事図鑑」(@kogei)というLINEの公式アカウントで、伝統工芸インターンについての情報共有をしています。これには現在8,300人以上(2025年6月取材時点)が登録してくれています。こうした数字が可視化されたことで、産地の職人さんたちも未来に希望を持てるようになってきた、という話も聞いています。
— 25年5月には、伝統工芸専門の求人メディア『まちびと』という新サービスもリリースされました。
大牧 『まちびと』は、後継者を募集している職人さんを僕たちが取材した上で、それぞれのプロフィールや仕事の内容、仕事場のある地域などについて写真入りの記事を掲載し、読んだ人が「応募する」をクリックすると、職人さんに連絡がいくというシステムです。リリースから1カ月弱で、6名掲載したうち4名のもとに複数名の応募がありました。僕としてはこの『まちびと』に大きな可能性を感じています。
後継者インターンシップは、マッチングの仕組みとしては理想的でも、僕らのキャパシティには限界があるし、県庁や市役所など行政の支援がないと成立しない事業でもあります。自治体によってはそうした活動に消極的なところもあって、なかなか予算がつかないケースもあります。
インターンシップ方式だけに頼っていると、結局ほとんどの人が参加できないまま就職の時期を過ぎてしまう。『まちびと』という取り組みは、立ち上がったばかりではありますが、大きな可能性を持つ事業と考えています。
地域の魅力を残していくために
— 御社の活動に対する若い人たちの反応はどうですか。
大牧 職人になるという選択肢は、少し前までは、若い人にとってあまり現実的なものではなかったかもしれません。でも実際には「ものづくりがしたい」という若者は常にいるのです。「ニッポン手仕事図鑑」にも、「職人になれる道があるなんて思わなかった」「もっと早く知っていれば」という声が届いています。
ただ、伝統工芸の学校に通っている若い人の中には、「職人になるのが不安だ」と感じて、在学中にあきらめてしまう人も少なくありません。学校で「伝統工芸の仕事は厳しい」「10年は修業が必要だ」といわれて、職人になる前から気持ちが折れてしまうんです。
後継者インターンシップで実際に職人になった若手たちと、そうした学生たちをつないで直接話をする機会をつくると、若手職人さんから「最初は不安だったけど、周囲の人の応援や支えがあったから、大丈夫だよ」なんて話を聞けて、「自分にもできるかも」と勇気をもらえるんです。僕たちのような大人が語るよりも、職人としての道を歩み始めたばかりの若い先輩と、まさに今、進路に迷っている学生とが対話を重ねることにこそ、大きな意味があると感じています。
— 動画やインターンシップなどのリアルイベントを通じて、職人と生活者の新たな接点も生まれているのではありませんか。
大牧 はい、それは実感していますし、接点はまだ増やしていけると思います。今取り組んでいるのは、後継者インターンシップを経て職人になり、現場で活躍している人たちの声を届けるコンテンツづくりです。また、職人歴7年目くらいまでの若い職人たちに限定した作品展も開こうと、企画しています。
伝統工芸の作品展といえば、一般的には著名な作家による出品が中心で、若手職人が自らの作品を発表できる場はまだ多くありません。ただ、20代の若者が手掛けた作品だからこそ、一般の方々の関心を集める可能性もあると感じています。
今の時代、必ずしも技術が完成されていなくても、その成長過程や挑戦そのものに共感し、すでに知られている巨匠の作品よりも、若手の挑戦を応援したいという人も多いのではないでしょうか。
— 消費者側のそうした変化を感じることはありますか。
大牧 福岡県の東峰村にある小石原焼(こいしわらやき)の産地では、後継者インターンシップを経て、一昨年4月に地元の工房へ就職した若手職人がいます。彼は大学でろくろを学んだ経験があるものの、いわば職人としてはまだ駆け出しの段階です。
そんな彼に対して、親方が「お客さんと接する機会がなければ、ものづくりも面白くないだろう」と考え、5月に開催された現地の陶器市での出品を特別に許可しました。とはいえ、本人はまだ成形しかできず、釉薬などの仕上げは親方が手掛けたものです。作品には、若手職人の名前を添えたプライスカードが添えられ、初心者マークも付いていました。また、親方の作品が3,000円で販売されている中で、彼の器はあえて少し価格を下げた2,500円で出品。すると、「応援したい」という声とともに予想以上の反響があり、かなりの数が売れたそうです。
まるで若手アイドルを“推す”ように、成長を見守り応援したいという気持ちが、若い職人にも向けられる時代になってきたのかもしれません。そうしたムーブメントが生まれれば、伝統工芸の伝え方や売り方そのものも、変わっていく可能性があると感じています。
実際、視聴者の方々からも、こうした後継者たちのリアルな姿をもっと知りたいという声を多くいただいています。若い職人に話を聞く際は、私がインタビューするよりも、年齢の近いスタッフが取材したほうが、彼らも自然体で話せることが多い。そんな取材を通じて、同世代の学生たちが「自分にもできるかもしれない」と思えるようになることを願っています。
— 最後に、大牧さんが「文化継承」を通して実現したいと考える社会の姿とは、どのようなものでしょうか。
大牧 常に意識しているのは、「それぞれの街が持つ個性を残していきたい」ということです。もし土地ごとの個性や文化をつくっているのがその土地で働く人たちだとすれば、地場の伝統産業が何で、どんな状況なのかが、街の個性を維持するためには、非常に重要になってくる。自分自身、年齢を重ねて、「次の世代を担う若者が暮らす日本が、自分の大好きな日本であってほしい」という気持ちが強くなりました。「自分はなぜ日本が好きなのか」とあらためて考えたときに、隣り合う街同士であっても、文化や食、言葉に違いがあり、それぞれに独自の個性がある─。そうした多様性が織りなす日本の地域性こそが、この国の魅力ではないかと感じました。その面白さを次の世代につなげていきたいという想いが、私がこの仕事を始めた原点です。
経済的な視点で見ても、今後、日本がITや半導体といった大量生産型の製造業で国際競争を勝ち抜いていくのは、決して容易ではありません。そうした中で、日本がこれから注力すべき分野の1つが「観光」だと考えています。その観点から見ると、伝統工芸の持つ価値は非常に大きい。
体験型コンテンツとしての提供も可能ですし、物販にも展開できる。何より重要なのは、自動車のように海外に生産拠点を移すことができないという点です。伝統工芸は、産地の文化や暮らしと分かちがたく結びついており、地域とともにあるからこそ、その魅力が生まれます。
ある職人の方が、「伝統工芸が1つ失われるということは、日本の魅力が1つ失われるということだ」というお話をされていて、ハッとしました。まさにそのとおりだと思います。地域に根差した文化が失われてしまえば、世界から人を惹きつける日本の魅力もまた、静かに失われていく。それは、私たちにとっても大きな損失であるはずです。