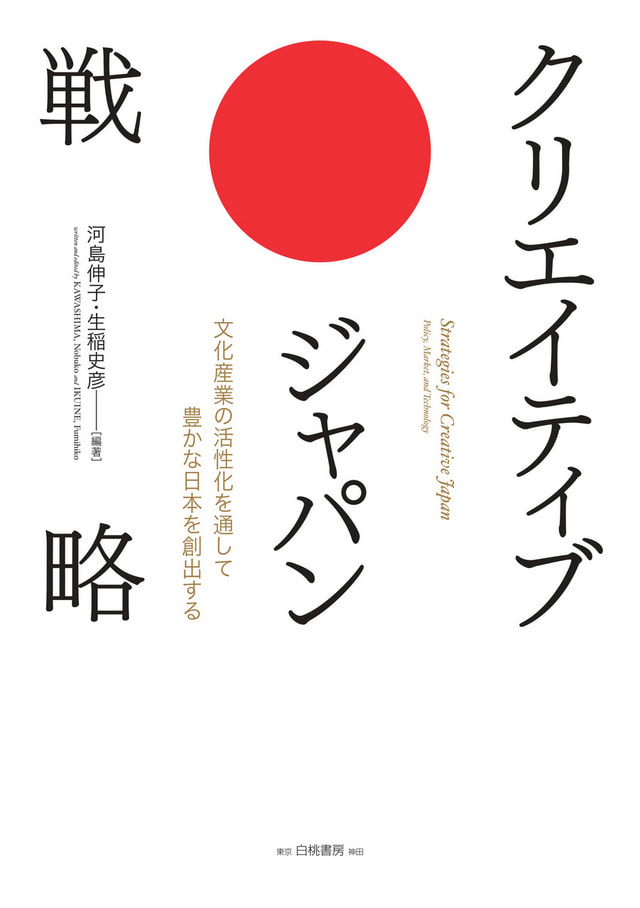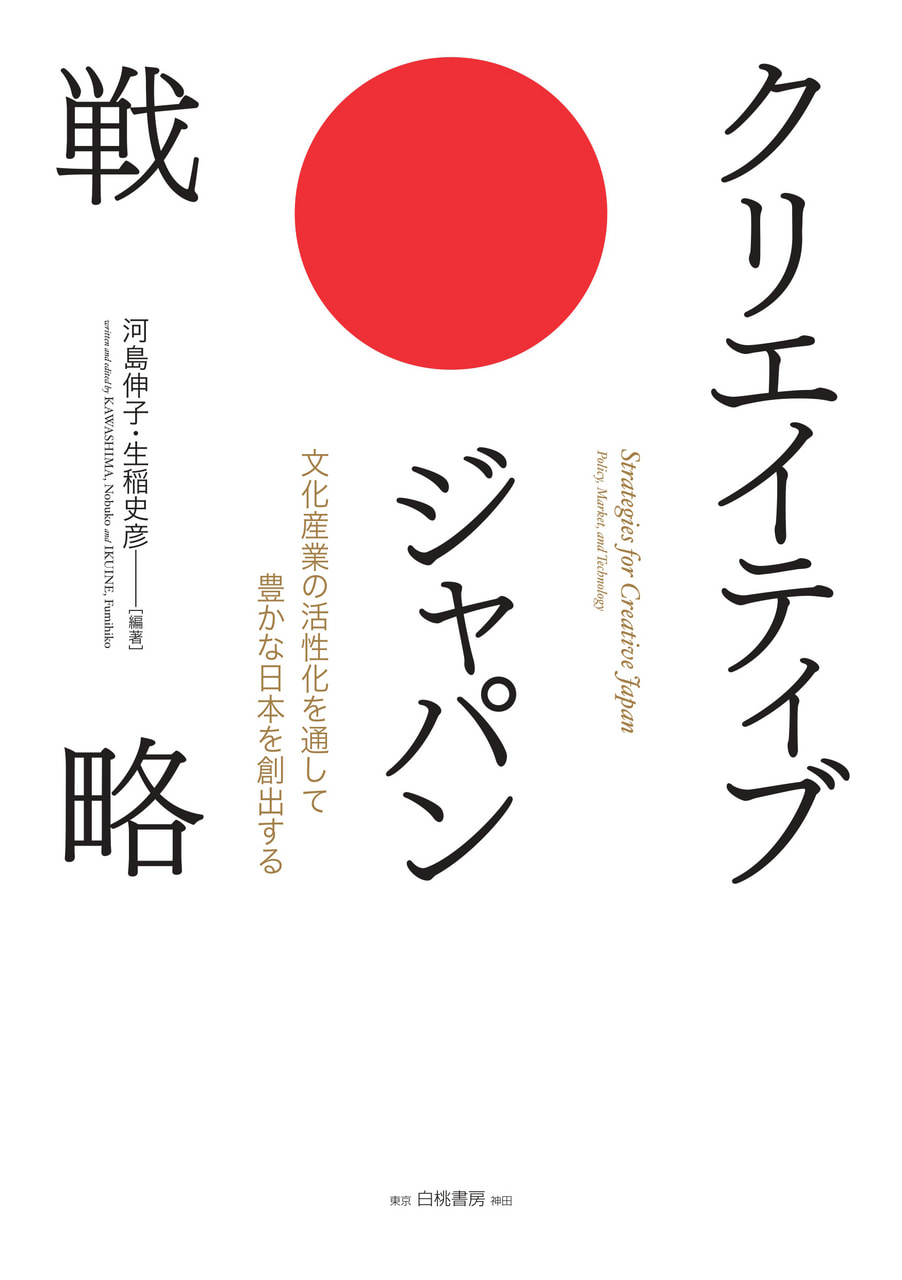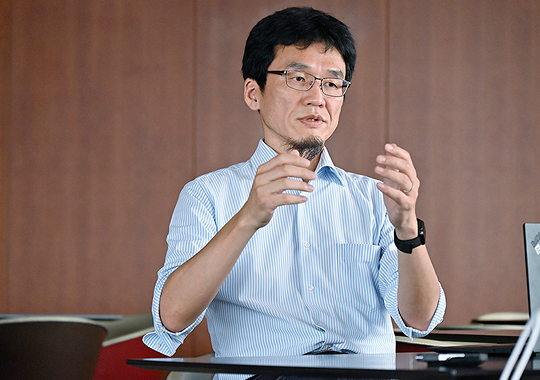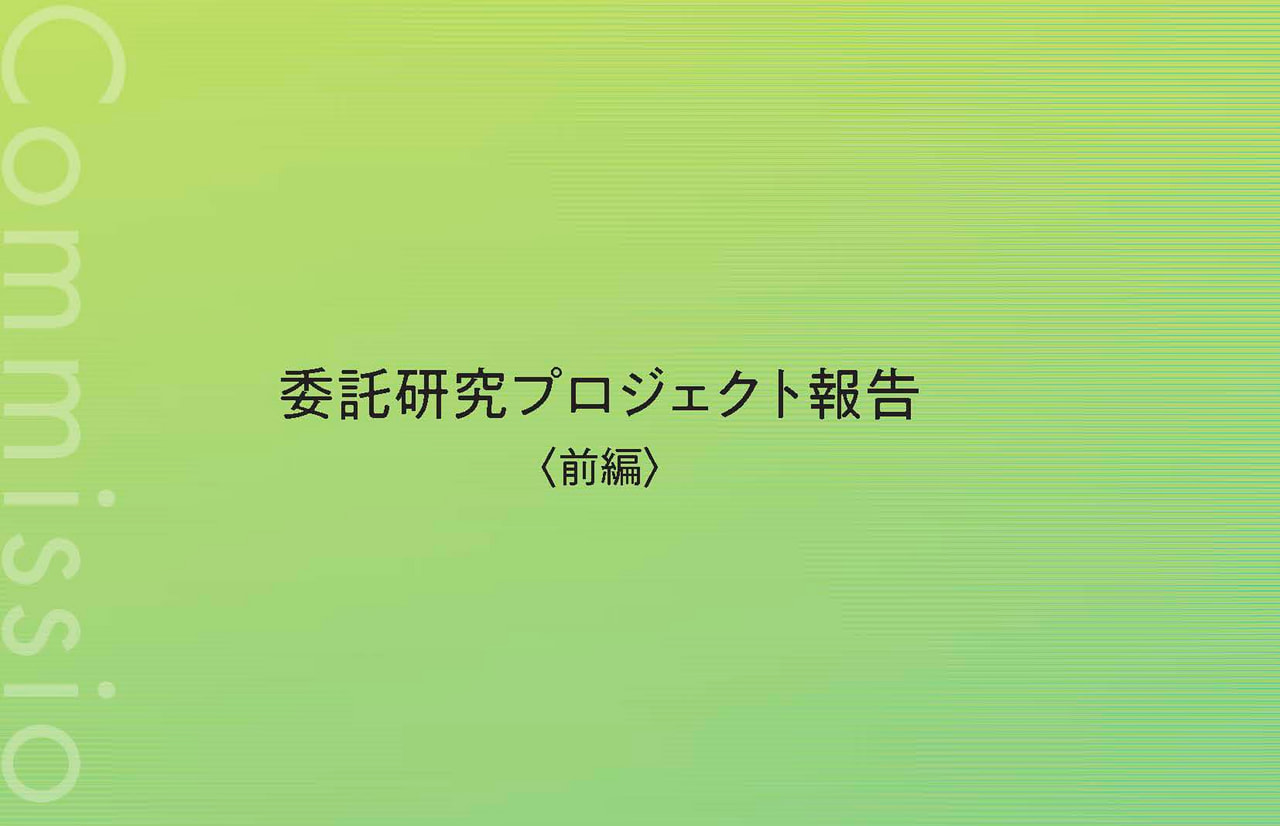文化としての広告表現
— 最初に、広告と文化政策の両方を研究テーマとされている河島先生のバックグラウンドについてお教えください。
河島 大学卒業後、金融機関に短期間勤務した後に転職し、電通総研で8年間、研究員として勤務していました。その際、日本の文化大国づくりについての自主研究に取り組む機会があり、各国の文化予算や文化政策、文化のマネジメントについて調査し、研究成果は本の形にまとめて出版しました。それが今の研究の第一歩となっています。
私は大学時代に国際関係論を学んでおり、もともと文化外交や文化交流に関心があったのです。加えて当時の日本では「モノの豊かさから心の豊かさへ」「文化大国日本」といったスローガンが掲げられていました。「日本は今後、経済大国から文化大国を目指さねばならない」と言われていたこともあり、文化政策はそうした時流にも沿う研究テーマでした。
— 民間企業から大学に移籍したきっかけは何でしたか。
河島 会社を休み、イギリスのロンドン大学(London School of Economics)の社会政策研究科に留学する機会があり、そこで学術研究の面白さに目覚めてしまって(笑)。帰国後2、3年経ってから、正式に会社を辞め、イギリスのウォーリック大学文化政策研究センターに研究員として勤務しました。私は大学卒業後そのまま新卒で働き始めたため、Ph.D.などは持っていなかったのですが、ロンドン大学から帰国後、文化政策の国際比較をテーマとした英語の論文が、学術誌『EuropeanJournal of Cultural Policy(現在のInternational Journalof Cultural Policy)』に掲載され、それが採用の助けになったと思います。
4年間イギリスで研究員を務め、論文を提出し文化政策学のPh.D.を得て、1999年に帰国。日本で同志社大学に教員として採用され、現在まで籍を置いています。
その後も大学の在外研究員制度を使い、改めてロンドン大学に1年半、アメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)に半年、フランスの国立社会科学高等研究院に1年間、客員教授として在籍しました。
— 現在のご専門はどういった範囲になりますか。
河島 研究分野は文化政策で、イギリスを中心に、ヨーロッパ、アメリカ、アジアを視野に入れつつ、日本との比較を通じて研究を進めてきました。政策的な枠組みにとどまらず、企業による文化支援や、文化を産業として成り立たせる仕組みなど、文化経済学の観点からもアプローチしています。対象とする「文化」は、音楽や美術に限らず、各地の食文化にもおよび、授業では映画、テレビ、マンガ、アニメ、ポピュラー音楽、スポーツなど、多様なコンテンツ産業を取り上げています。
一口にヨーロッパといっても、文化政策のあり方は国によって大きく異なります。フランスのように国家が主体的に文化政策を推進している国もあれば、スウェーデンでは社会福祉政策の一環として文化を位置付けています。それぞれの歴史や社会構造を反映した、さまざまなタイプの文化政策が存在するのです。
アメリカは市場原理が強く働く国ですが、民間によるフィランソロピー(社会貢献活動)としての文化支援が活発です。アジアにおいても、シンガポールのように文化を経済戦略の一環として活用する国も見られます。
— 広告分野の研究もなさっていますね。
河島 実はこれまでに、吉田秀雄記念事業財団の助成金を3回にわたっていただいています。2001年度には「オーケストラにおけるマーケティング・広告活動の現状と今後の課題──コンサート・マーケットと聴衆セグメントの分析」、2003年度には「文化産業としての広告表現制作活動──創造とビジネスの組織、その変容」、2006年度には「アメリカにおけるブランデッド・エンタテインメント──“業界”としての現状と今後
の課題」というテーマで研究を発表しました。
特に2003年度の「文化産業としての広告表現制作活動」では、広告表現を1つの文化的創造物と位置付け、そのクリエイティビティを支える環境とは何かを考察しました。文化的な創造性を高め、それをより多くの人々に届けることは、文化政策の根幹ともいえる重要な視点です。財団の助成を受けたこの研究では、その視点を「広告」というテーマに落とし込み、文化産業の一側面として掘り下げました。
— 文化産業としての広告表現の特徴はどこにあるでしょうか
河島 広告やクリエイティブに携わる方々は、商品の認知度を高めたり、購入につなげたりするために表現を行っていますから、対象となる商品の魅力や、その本質を見抜く力が非常に高いと思います。そこにはアーティストと共通する面もあるでしょう。
商品の良さを訴求する際、アーティストは自らの感性を起点に、率直な表現を試みます。一方、広告クリエイターは、ターゲットやメディア特性など多様な要素を踏まえた上で、伝え方を設計していきます。いわば「マーケットありき」の発想ですね。
この研究に着手した当時は、まだiPhoneが発売される前で、インターネット広告も本格的に普及する前でした。そのため、主な対象はテレビCM。電通総研に在籍していた際の人脈もあり、電通の優秀なクリエイターや、独立した方々から貴重なお話を伺う機会が得られました。
当時も広告クリエイターは人気の職業でしたが、バブル崩壊後という背景もあり、多くの方が「良い広告を生み出すための環境が失われつつあり、広告全体の質も低下している」といった問題意識を持っていたことが印象に残っています。
この論文をきっかけに日本広告学会に所属するようになり、ブランド論を専門とする経営学者の田中洋先生や、広告研究の水野由多加先生ともご縁ができました。お二方のもとでマーケティングやブランディングについて学べたことは、現在の研究にも大きな影響を与えています。田中先生のご著書に寄稿させていただいたこともありました。日本広告学会の関西部会では、毎年1回同志社大学を会場に研究会を開催しており、CMプランナーを招いて講演を行うなど、実務と研究をつなぐ試みも行っています。
なお、広告研究は私の研究全体の中ではおよそ10%を占める位置付けです。文化政策の研究対象は、伝統芸能からポップカルチャーまで幅広く、広告はその中の一領域として扱っています。
マーケティングの視点に欠ける日本の文化研究
— 最初はオーケストラのマーケティングについて研究されたのですね。
河島 はい。最初に「オーケストラにおけるマーケティング・広告活動の現状と今後の課題」というテーマを選んだのは、日本のクラシック音楽におけるマーケティングのあり方に疑問を感じていたからです。日本における文化研究においては、マーケティングの視点が非常に弱いと感じています。実際、文化のマーケティングを専門的に研究している研究者は、日本ではごく限られているのが現状ではないでしょうか。
欧米では「アーツ・マーケティング」として確立された分野があり、大学院などの教育機関では、文化分野におけるマーケティングを学ぶ中で、実際の現場に赴いてインターンとして働くことも一般的です。一方で日本では、大学がアーツビジネス領域をどこか軽視している傾向があり、研究者が販売や広報の現場に関与することはほとんどありません。
— それはなぜなのでしょう。
河島 販売面の努力をしなくても、現状は幸い何とか持続できているからでしょう。例えば、長い歴史を持つとあるオーケストラでは、チケットをほぼ定期会員向けに販売してしまっているため、それ以上に観客を増やす必要性をあまり感じていません。ここに限らず、日本のクラシック音楽や伝統芸能は、基本的にニッチな世界。熱心な固定ファン層に支えられており、その強い支持層を対象とすることで、事業としての持続が図られています。
クラシック音楽の演奏会に行くと、次回以降の公演チラシが何枚も配布されます。ただ、こうしたチラシは演奏会の場でしか手に入らないことが多く、情報がどうしても既存の来場者に限られがちです。その結果、リピーター中心の構造になりやすく、新規の方へのアプローチが難しい一因ともなっています。
チラシの内容もある程度パターン化されており、演奏家の写真を美しく掲載し、出身校や留学歴、師事した音楽家の名前などを通じて、専門性や実績を伝える構成が主流です。伝統あるジャンルゆえの安心感にはつながりますが、初めての方にとっては少し距離を感じるかもしれません。
演奏家は、良い音楽を追求することに集中したいと考えており、その姿勢は純粋なものです。ただし、マネジメントの視点からすれば、それだけでは不十分だと私は感じています。芸術のファン層をピラミッドに例えると、最上部には「何もしなくても必ず来場してくれる人たち」がいます。その下には「機会があれば時々足を運ぶ人たち」、そして最も裾野の広い層には「まだ関心を持っていない人たち」が存在します。トップ層の方々に、年に3回だった来場を4回に増やしてもらうことは容易ですが、「たまに来る人」を常連にしたり、「来たことがない人」に一度でも足を運んだりしてもらうことは、はるかに難易度の高い取り組みです。
しかし、こうした階層を少しずつ上へと押し上げていく努力をしなければ、ファンの裾野が広がることはありません。だからこそ、マネジメントはそこに積極的に取り組むべきだと私は考えています。
— 海外ではどういった状況でしょうか。
河島 ロンドンやパリでは、地下鉄が市民の足となっており、その通路やプラットフォームには美術展、演奏会、オペラなどの告知ポスターがたくさん掲出されています。芸術に特別な関心がない人であっても、「今あそこでこんな催しが行われている」と自然に情報が目に入る仕組みです。
このように、新聞広告やポスターなどのマス・マーケティングによって、社会階層を問わず幅広い層に情報が届いている背景には、美術館やホールが広告費をしっかりと予算化しているという前提があります。もちろん、セグメントごとの個別マーケティングも積極的に行われています。例えばイギリスでは、地域ごとに居住者の社会階層がある程度分かれる傾向があるため、各地域の属性を分析し、ターゲット層に応じたアプローチが行われています。現在では、デジタル技術の進展により、さらにきめ細かなマーケティングが実現されていることでしょう。
日常における文化の位置付け
— そうした日本と海外の違いは、運営側の意識の違いが大きいのでしょうか。それとも人々の日常的な文化に対する意識の持ち方が違うのでしょうか。
河島 私は以前、アメリカのUCLAに半年ほど滞在していたことがあり、現地で友人もできました。帰国後、再びロサンゼルスを訪れる機会があり、以前に親交のあった教授に「ご都合いかがですか」と連絡を取ったところ、「ちょうどその日は友人夫婦と一緒に食事をしてから映画を観に行く予定です。よかったらご一緒にどうですか」と誘われました。
日本でも夫婦2組で食事をすることはよくありますが、さらに一緒に映画まで観に行くというのは、あまり一般的ではないように感じます。知り合いの家族と一緒に美術館やコンサートへ出掛けるというのも、日本ではそう多くはないでしょう。でも、アメリカではそれがごく自然に行われていて、文化的な活動が日常生活にしっかりと根付いているのだと感じました。
このような傾向はヨーロッパにも共通しています。2年ほど前に私が日英比較の研究プロジェクト内で実施した調査では、音楽会や美術展などへの参加率を両国で比較したところ、日本はイギリスと比べて著しく低いことが明らかになりました。日本では「テレビ、CD、動画視聴以外で、どのような文化芸術の鑑賞活動をしているか」という質問に対して、「何も鑑賞していない」と答えた人が約4割にのぼりました。比較的回答が多かった「歴史的建造物や遺跡などの文化財」「映画(アニメを除く)」「歴史・民俗系の博物館や資料館」「美術」「ポップスやジャズ、演歌などの音楽」についても、いずれも鑑賞率は10%台にとどまっています。
イギリスでは、「イギリスは階級社会で、文化に関心があるのは中流以上の人たちだけで、労働者階級は文化活動には関わらない」とよく言っています。けれども実際には、1年の間にコンサートや美術展に足を運んだ人の割合は、日本よりもイギリスのほうが圧倒的に高いのです。
イギリスでは、美術館や博物館の入場料が基本的に無料です。図書館と同じく、「行きたいときに、誰でも行ける」という仕組みが整っています。もちろん、無料だからといって誰もが訪れるわけではありませんが、イギリスでは「美術にせよ自然にせよ科学にせよ、過去の知の蓄積にアクセスすることは市民の権利である」という考え方が根付いているように感じます。
— フランスにおける、文化への態度はどうでしょうか
河島 フランスに住んでみて感じたのは、彼らは「格付け」を利用しながら、文化を海外に発信することに非常に長けているということです。有名なのはワインの格付けで、シャトーごとの格付けはもちろん、地域によっては、村単位、畑単位でも格付けされ、そこで「良い」とされたものを、積極的に海外に輸出しています。レストランの格付けを行っているミシュランも、フランス企業です。彼らはそうした格付けを行うと同時に、「その頂点にはフランスがある」というストーリーをつくるのが得意だといえます。
一方でこうした格付けは、日常的なフランス人の食生活とはあまり関係がありません。一般のフランス人は、普段はリーズナブルなワインを飲みます。しかし格付けすることによって、海外のワイン好きに自国の文化をわかりやすくアプローチし、商業につなげることができるわけです。
日本人もランキングをつけるのは好きだと思います。ただ日本の場合は、自分で選ぶ手間を省くためにランキングが使われているイメージがあります。「情報が多すぎて選べない」という面倒くさがりな人のための仕組みなのです。
— 確かに、日本の消費者はランキングサイトを重要視する傾向があるように思います。フランスでの格付けは、フランス人個人の選択や評価とは関係しないのですね。
河島 フランスでは、個人が主体的に考え、評価することが大事だと教えられます。「人と同じであること」はあまり評価されず、「自分だけの評価」を大事にしていて、専門家にもそのような志向が見られます。そのため、格付けはあくまで、グローバル市場に向けた積極的なアピールなのでしょう。
フランスの蚤の市を訪れた日本人からは、「いろいろなものが売られているけれど、何を探せばいいのかわからない」といった声をよく耳にします。これは裏を返せば、「自分は何がほしいのか」という意識が明確でないことの表れかもしれません。
日本では「何もない空間の美しさ」が好まれる傾向がありますが、欧米では住まいのインテリアを重視し、自分なりに空間をコーディネートしている家庭が多く見られます。例えばフランスの家庭では、壁にギターが掛けられていたり、アンティークの大きな鏡が置かれていたりと、個性が感じられるインテリアが印象的ですが、そうしたものが実は蚤の市で見つけた一点ものだったりするのです。
彼らは普段から「この場所に何か置いたら素敵だな」と想像していて、蚤の市でそのイメージに合うものと出会えたら、ためらわず購入し、自宅の空間に取り入れます。選ぶ基準はブランドではなく、自分自身の美的感覚。自分の暮らしに合ったものを見つけて取り入れるという、文化的なスタンスの違いがそこにはあるように思います。
日本人はブランドが好きですよね。でもブランドというのは外から与えられた権威であって、自分自身の評価ではありません。日本人は「自分で主体的に評価する」ことにあまり慣れていないのではないかと感じます。フランスの場合、一般の人はブランド品には興味を持たず、ルイ・ヴィトンなどは「外国の人が買うもの」という感覚があるようです。
経済に転換するのが苦手な日本
— そうした違いは、国の歴史や政策から来るものでしょうか。
河島 フランス人がブランディングや格付けを上手にビジネスに結び付けるのは、ヨーロッパの地理的・歴史的背景が影響しているのではないかと思います。国境が近く、常に他国との関係やインターナショナルな市場を意識せざるを得ない環境の中で、文化を経済価値として捉える視点が自然と培われてきたのでしょう。
一方、日本は文化そのものの豊かさには恵まれているものの、それを経済に転換することがあまり得意ではないように思います。例えば近年、1980年代の日本のシティポップが海外で再評価されていますが、多くは「海外で評価された」と喜ぶにとどまり、それを収益化する動きは、他国に比べて鈍い。文化を経済的な価値に転換する視点や仕組みが、まだ十分には育っていないと感じます。フランスのように、したたかに文化を活用する姿勢を、もう少し見習ってもいいのではないでしょうか。
日本は島国であり、「文化を海外に輸出する」という発想自体があまり根付いてこなかったのかもしれません。実際、日本から美術品などが本格的に海外に渡るようになったのは明治時代以降のことで、それも国策というより、欧米の美術商によって主導された印象があります。
— 日本のアニメ作品は、海外でも人気ですがいかがでしょう。
河島 いわゆるジャパニメーションは、日本にしかない文化といえるでしょう。最近では中国や韓国も似たものをつくっていますが、日本は歴史の深さ、幅の広さ、クオリティなどの積み重ねが突出していて、他の国が簡単に追いつけるものではないと思われます。
ただアニメの輸出が増えているとはいえ、実際にそれを制作しているスタジオの多くは零細企業です。グローバル市場を念頭に制作された作品はほとんどありません。ようやく最近になって、Netflixなどがアニメ制作に資金を出し、世界に向けてディストリビュートする動きが出てきました。そういう意味では、まだ「これから」なのではないかと感じます。
—「海外のディストリビューターが制作に関わるようになると、日本アニメ独特の文化が失われてしまうのではないか」と心配する人もいます。
河島 「日本のアニメ制作がNetflix目線になってしまうのでは」ということですね。ただ今のところ、海外のファンの嗜好が日本のアニメ制作に強く影響するということは、それほどないように感じます。もともと『ドラえもん』にしても『ちびまる子ちゃん』にしても、海外の需要などまったく考えずにつくられてきた作品です。ディズニー的なワールドワイドに通用するコンテンツとしては、日本のアニメでは今のところジブリ作品くらいしかないでしょう。人類共通の大きな問題をテーマにして作品をつくるという発想は、日本ではそれほど強くなく、多くのクリエイターはもっとニッチな志向を追求しているように思います。
— 日本独自の、海外輸出のための仕組みや制度というものはつくれないのでしょうか。
河島 以前、経産省の会議で官庁の人から「日本で国際的な供給網をつくれないのですか」というご意見が出たことがあるのですが、民間側は「あれはアメリカでしか無理です」と言っていました。私もそう思います。世界全体を見ても、インスタグラムやXといったSNSにしても、NetflixやAmazonなど国際的な配信のシステムにしても、アメリカがほぼ独占状態です。例外はTikTokくらいでしょう。
ただ、デジタル化の進展によって、日本にチャンスが巡ってきたこともあると思います。ゲームなどがそうですね。オンラインで流通するようになると、パッケージをつくる必要もなくなりますし、AIの進化により、翻訳や字幕など言葉の壁も低くなって、日本のアニメを字幕付きで見るという文化も広がってきました。
少し前まで「海外=欧米」という感覚でしたが、今では中国や東南アジア、さらにはインドやブラジルまでアニメのマーケットになっています。こうなると「どこを基準にしてつくればいいのか」というのは難しい問題で、今後は一番売れるところを狙ってつくっていく形になるのではないでしょうか。
— 河島先生は、「文化は社会のOS」と説いていらっしゃいます。経済の低成長が続く日本において、文化への関心・投資を高めるためにできることは何でしょうか。
河島 文化に投資する制度について政府が整備するという道もあると思いますが、実際には「日本には世界に認められるべき優れた文化がある」という前提に立って、「それを海外の需要に結び付けるお手伝いをします」というスタンスです。
経産省などはよく、「文化は鉄鋼、半導体を超える輸出産業になる」と言っていますが、例えば音楽産業ではデジタル化に伴ってかつて主要な収入源であったCDの販売機会が失われ、ミュージシャンが苦境に立たされていますし、アニメ産業においても低報酬に甘んじているアニメーターが多いといわれます。作品を実際に制作する現場にもっと資金を入れたり、環境を整えたりしていかないと、そのうち売れる作品自体がなくなってしまうのではないでしょうか。そういった意味では、「掛け声ばかりでお金を出さない国よりも、Netflixなどの外資企業のほうがよほどいい」と言う日本のクリエイターもいるくらいです。海外ではアーティストにベーシックインカムを支給して生活を支えようという動きも出ている中で、日本政府の姿勢が問われています。
— 広告のノウハウや知見を、文化の輸出に活かすことは可能でしょうか。
河島 文化政策を考える上で、広告やマーケティングの勉強は役に立つでしょうし、国家ブランディングにも活かせるのではないかと思いますが、現実にはまだそうした動きは出てきていません。政府のプロジェクトも、なかなか実践につながらない傾向があるように思います。インバウンドは増え、海外への文化輸出自体も増えていますが、どれも単発的で、戦略性が感じられません。
以前の報告書の中で、クリエイティブディレクターの佐藤可士和さんが「日本では強いブランドの各々がバラバラな方向を向いていて、ベクトルが揃っていない。共通となる価値を底上げするマスターブランド戦略が必要だ」という趣旨の発言をされていて、鋭い指摘だと感じました。この指摘から、日本の文化戦略はあまり進歩していないと感じます。
— 文化の維持・発展のために、特に積極的に関わってもらいたい社会的立場の方はいらっしゃいますか。
河島 私はIT関係の人が入ってくれるとよいのではないかと感じています。エンジニアというよりアントレプレナー、テクノロジストと呼ばれるような人たちが加わることで、既存の文化に新しい視点がもたらされるのではないでしょうか。
文化もインターネット中心の時代になっています。私は広告学会の中でも、デジタルシフト研究会によく出席しているのですが、多くのヒントが得られます。
— 上場企業による文化活動への投資も、近年は株主からの同意を得るのが難しくなっていて、企業が所有する美術館の売却を迫られるといった話も耳にします。
河島 実際、そういった動きは起きていますね。経済やビジネスの関係者の中には、「文化は重荷だ」と考えている人も少なくありません。ただ「ではそれを変えるためにどうすればいいのか」という明確な答えは、私も持ち合わせていません。この問題は、教育にまで遡らないといけないのかもしれません。
文化は本来、経済を含むすべての分野に共通する土台であり、地球環境と同じように捉えなければならないものだと思います。社会やまちづくりに貢献するのはもちろん、教育であれ労働政策であれ、すべての領域に文化の視点が必要です。自治体が今、文化を地域おこしに活かそうとしていますが、「そもそも経済は文化に支えられている」と考えたほうがいいのではないでしょうか。