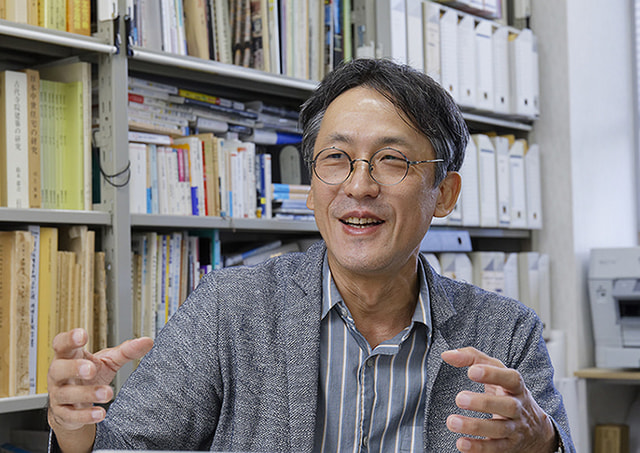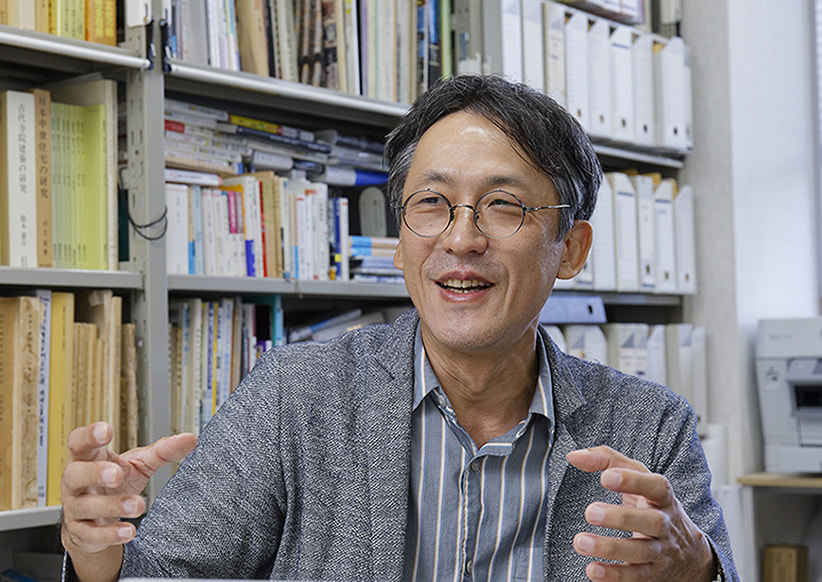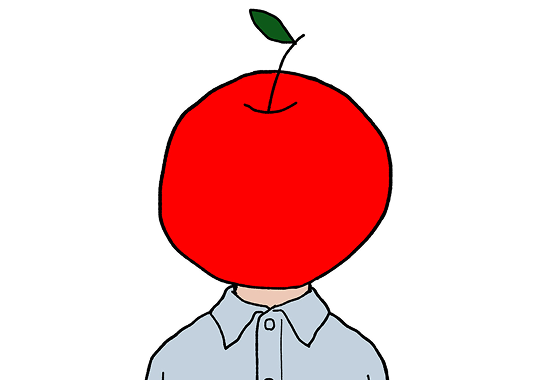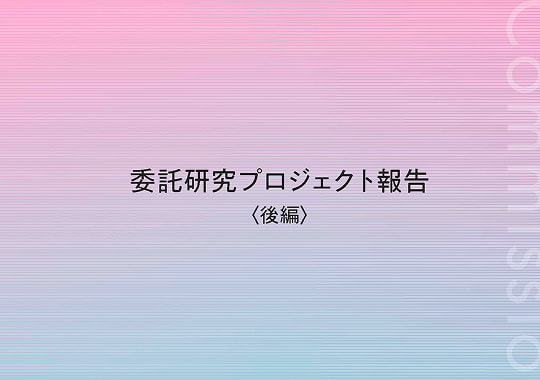異文化を学び、日本を再発見
— 青柳先生が建築学を志した背景をお聞かせください。
青柳 私の家系や親戚の中に建築をなりわいとする人はいませんが、小学生からの幼なじみの友人のお母さんが建築の仕事をしていて、子どもの頃、家に遊びに行ったとき仕事場でドラフター(製図板)を使って設計図を描いていたんです。その姿を見て「かっこいいなあ」と思ったのが、今から思えば最初のきっかけだったような気がします。
小・中学校では美術や工作が得意で、授業で制作した作品が表彰されたこともよくあって、高校生になると美術館に行って西洋の近代絵画を鑑賞するのが好きになりました。それで大学受験の際に「美術方面に進みたいな」という気持ちもありましたが、美術で生きていくのは大変です。理系の科目も嫌いではなかったので、「理系で、文化的なことに携われるような仕事はないかな」と考え、建築学科を志望しました。
入学後、「建築史」に関心を持ったのは、海外旅行の経験が大きかったと思います。大学に入学した1990年代の中頃は、円高という世界経済を背景に若者の間でバックパッカーの海外旅行がはやっていて、私もアルバイトで貯めたお金でアジアやアフリカを旅しました。大学生になってすぐの夏休みに1カ月かけてインドを一周したのですが、そこでタージ・マハルやジャンタル・マンタルを見て強い衝撃を受けました。それですっかり歴史的建築の魅力にはまってしまい、その次の春休みには1カ月間エジプトに滞在してピラミッドや神殿など多くの遺跡を見て回り、サハラ砂漠のど真ん中で野宿までして過ごしました。今でも結構そうなのですが、当時は若かったので異文化の影響をもろに受け、日本に戻ってすぐの大学の設計課題でタージ・マハルみたいな神殿風の建物を大学キャンパスに設計して教師に怒られたものです(笑)。
— 異文化体験をきっかけに日本の建築史の研究に向かわれたのですね。
青柳 一般に自国の文化への関心は、外国の文化との接触から生まれるのではないかと思います。海外旅行に出かけると必ず古い町並みや宗教建築などその国の文化的なもの、歴史的なものとたくさん出会います。私はその後も休みになれば海外に行き、大学院生のときにはアメリカに1年留学したり、オランダの建築事務所で数カ月働いたりと、外国ばかりを見ていたのですが、ふと「日本の古い建築については、自分の国にもかかわらず、何も知らないな」と気付いたのです。それで日本の建築史をちゃんと学ぼうと考えて、修士論文のテーマとして日本の文化財保存を選んだのが今に至るきっかけです。
生まれ育った東京から関西に移住して10年以上たちましたが、現在、学外で取り組んでいる活動は、関西にたくさん残っている古い建物を保存するため、一つひとつ調査して、それらの建物の特徴や歴史的価値を明確化するという地道な作業が中心です。例えば、大学のキャンパスがある滋賀県草津市や隣の湖南市の社寺建築とか、福井県の今庄宿(いまじょうじゅく)、大阪府富田林(とんだばやし)の寺内町などの町家建築などの調査です。京都の長江家住宅という幕末期の町家や、現在やっている和歌山県高山寺など単体の建物の調査を依頼されることもありますが、通称「伝建」と呼ばれる、「伝統的建造物群保存地区」という文化庁の制度があり、都市や地区の中の多数の建物やそれらがつくる町並みについての調査依頼もあります。
— そういった調査は、どんなプロセスを踏んで実施するのですか。
青柳 依頼を受けると、調査対象の町に通い、2年ぐらいかけてその地区の建物を一つひとつ調べていきます。1つの研究室では大変なので通常3、4人の研究者とチームを組んで調査を行います。調査対象となる建物は個人宅が多いため、自治体を通して「拝見させてください」と申し入れ、内部を実測したり所有者の昔話を聞いたりしながら平面図や断面図をつくります。これはなかなか大変な作業です。調査内容は「伝統的建造物群調査報告書」という書籍にまとめ、その報告を踏まえて文化庁が伝統的建造物群保存地区に選定するという流れです。こうした調査や選定後の補助事業は歴史を軸とするまちづくりの一つの方法で、われわれ学者たちは各町のまちづくりのお手伝いをしているわけです。
建物の歴史的・文化的な価値を判断するためにはさまざまな視点があります。建物を見る研究者の建物の調査方法や、「建築」についての考え方にも左右されますが、一般に、建物の姿や形だけではなく、宗教的な儀式や人々の日常生活など「その空間の中で人が何を行ってきたのか」も重要な要素です。その建物の構造や間取りが昔から続く人々の建物での振る舞い(動作や所作)や生活文化をよく表しているとき、その建物には文化的価値があると判断されます。その判断は実は研究者の目にかかっているところも大きく、一見するとただの古びた家屋として軽視されていた建物であっても、見る人によっては突然高い価値が付けられるというケースもありえます。
歴史的建物を「解釈する」とは
— それは面白いですね。先生もそういった経験をお持ちですか。
青柳 はい。それに関して印象的だったケースが「ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展」という、イタリアで開催された建築展のプロジェクトです。建築家の門脇耕三さんが日本館のキュレーターを務めた2020年の建築展に呼ばれて私も参加しました。
このときのプロジェクトでは、建築家たちとチームを組んで、世田谷区にあった高見澤邸という古い家を分解してヴェネチアまで運び、各部材を現地で作品として再構築したり、そのプロセスや建築部材自体を展示したりしました。その家は戦後に建てられた築65年の、ごく一般的な商店兼住宅の建物で、始めたときチームの建築家たちは皆「なぜこの建物をヴェネチアへ?」と思っていたようです。
私はこの建物を解体しながら建物の履歴を調査することになったのですが、それまでは一定の価値があると思われている歴史的な建築ばかりを調査してきたので、私自身もこのときはさすがに「なんの変哲もないこの家を調べてどうすんの?」とたえず自問しながら調査を行っていました。
しかし実際に調べてみると、解体中に見つかった痕跡や高見澤さんのお話などから、この家は頻繁に増改築を繰り返していたことがわかってきました。建物ができたのは高度経済成長が始まる直前の1954年ですが、その3年後には平屋だった建物の半分を2階建てにし、さらに数年後には全体を2階建てに増築し、裏側にも建物を広げました。増築した理由は、お子さんが大きくなって家が手狭になってきたからで、家族の歴史が住宅の形にリアルに反映されていたのです。
それだけでなくこの建物には、高度成長期における日本人の生活の劇的な変化が凝縮されていることもわかりました。1950年代後半から1970年代の高度成長期には、それ以前までの現場の職人さんの手作業による建設方法から、工場で生産した部材を組み立てる合理化された建設方法へと一気に移行しました。重要なことは、その結果として日本人の暮らしが大きく変わったことです。高見澤邸の建設当初と解体直前を部材レベルで比較すると、新しい建材への更新がひっきりなしに行われていたことがわかります。例えば最初は木製だった窓枠が、アルミサッシの市販開始から少し経った1978年にはすべてアルミ製へと変更されていますし、ユニットバスも後付けです。それは1964年の東京オリンピックで大量のホテル建設のために開発されたもので、ユニットバスの普及まで庶民は銭湯に行くのが一般的だったのです。
— 時代や生活が変わるたび、家も更新されてきたのですね。
青柳 そうなのです。そうした建物は東京のスクラップ・アンド・ビルドの経済活動に巻き込まれて、もうほとんど残っていませんが、たまたまこの家は2019年まで残っていた貴重な建物だったのです。私はこの調査で、埋もれていた価値をたくさん発見しました。それは私にとってとても刺激的な経験で、そこでわかったことをチームのメンバーに説明するたびに、彼らの目の色が変わっていくのが手に取るようにわかりました。
日本の美術史をひもとけば、例えば戦国時代に千利休がうち捨てられていた茶杓(ちゃしゃく)を手に取って、「これは美しい」と言うと、とたんに無価値だったものに大きな価値が出る、というようなことがあります。なかなかそういう得がたい経験はありませんが、研究者がそこに価値を見いだすことにより、まったく無価値だったものに価値が生まれ、その説明のしかた次第で、周囲における価値の認識のされ方も変わってくる、ということがあるんですね。
— 無から有が生まれるわけですね。
青柳 古い建物を調査するとき、第一に私がすることは、その建物のよさや魅力はどこにあるか、あるいは埋もれているかについて考えることです。それを私は「建物を解釈する」という言い方をしています。そして次の段階として、その解釈した「建物のよさ」を、どのように現代に残すのか、あるいはよみがえらせるのかという方針を立てます。私はそのプロセスを「文化継承行為」と呼んでいます。自らの解釈にもとづいて保存・復元するという作業は、埋もれていた建物の魅力を現代に「再現」することにほかなりません。歴史的価値の解釈は論文を書くことなどで実践できますが、建物の魅力を再現するには、現代の技術を用いてそれを復元することでしかできません。
こうした「解釈」と「再現」の2つからなる文化継承は、なにも建築だけの話ではありません。私たちは冠婚葬祭など日常的な生活文化でも、自分たちのお父さんやおじいちゃんがやってきたことを自分なりに解釈し、再現しようとしますね。その行為はまさに文化継承行為そのものです。「文化」とは、世代をまたぐ繰り返しにより、変化しながら持続的に展開していくものなのです。歌舞伎や能楽のような伝統芸能はもとより、陶芸や大工といったものづくりの伝統も、現在の担い手たちは伝えられてきたものをどう解釈し、現代にどう活かしていくべきか、皆悩みます。そして悩んだ末に、初代や先代がやってきたことを見つめ直し、それを自分流に再現して、継承の活路を見いだすのです。
— そうした文化継承行為において、既存のものに埋め込まれている先人の技術にどう向き合うべきでしょうか。
青柳 「歴史的な建物」といっても、文化財としての学術的価値が高いものと、そうではないものがあり、その2つは扱いを多少変えなくてはいけません。学術的に高い価値が認められた建物については修復を行う際、修復家の個性を強く打ち出すことはできません。それは「文化財の破壊行為」になってしまうからです。
例えば、文化財の中でも極めて価値が高いとされる法隆寺の修復は、古代の大工技術を極力再現して行われます。現代の人が飛鳥時代の建物を復元しようとするなら、自分の個性を押し殺して飛鳥時代の人になりきって取り組まなければいけません。もちろん古代の技術にはわかっていないことも多いのですが、建物の修復に没入して古代人と自分を同一化できるような人は、工事中の判断において「もし自分がその当時の大工だったらこうするはず」と考えて行動できます。法隆寺の昭和修理を担当した大工棟梁の西岡常一さんはそれができた人だったのだろうと思います。
一方、そこまでの学術的価値が認められているわけではない建物の場合は、価値を維持することよりも、どのようにそれを使い続けることができるかということに重点が置かれます。建物が壊されてしまったら元も子もないわけですから。私が今住んでいる家は、江戸時代の京都の西陣地区で建てられた「織屋建(おりやだて)」と呼ばれる織物工場を兼用した古い町家で、壊される寸前だったのですが、それを自宅として設計・改修しました。改修の前後で建物の機能がかなり変化するのですから、それに伴って当然いろいろと変える必要も出てきますし、むしろ既存のものの「よさ」に現代の住み手としての個性を上乗せすることで、建物自体が活き活きとよみがえるのだと思います。
高度成長期の文化的断絶
— 著作の中で、「伝統は持続性に裏打ちされるものであり、一度欠落してしまうと、あとで再現を望んでも、それができなくなってしまう」と書かれています。
青柳 日本の場合、高度成長期にさまざまな生活文化が断絶してしまいました。例えば、「床の間」もその一つです。高度成長期以前は、床の間は日本の家には必須のものと考えられていました。かなりの狭小住宅であった高見澤邸にも2階に奥行きの浅い床の間がありましたし、1950年代に炭鉱労働者のための住宅を建てた際、「床の間がない」と労働者たちからクレームが出たことがあったほど、日本の家には当たり前の存在になっていました。
床の間は、西暦1600年前後、安土桃山時代から江戸時代の初めにかけて、できたものと考えられているので、400年以上の歴史があります。最初は、僧侶の住まいや富裕層の家にしかありませんでしたが、次第に庶民も家に床の間を設えるようになりました。やがて日本人にとって床の間は「ちゃんとした家の証し」としての存在になっていきます。「ちゃんとした」といってもそれは単なる家の格式表現ではありません。季節に応じて花を生けたり、お客の趣味に合わせて掛け軸を替えたり、住む人が季節やイベントを楽しむために必要だったということです。
伝統的な住宅の床の間は、かつては電灯がなかったので、自然光が庭から差し込む部屋の中にあり、床に飾られた季節の花や絵画を見つつ、ふと目を少し横にずらせば、お庭にある本物の自然が目に入るようになっています。つまり本来床の間は、いわば家の内部と外の自然をつなぐ結節点のようなもので、外の自然を家の中に呼び込む装置なのです。そのようにして日本人は自然と連続した生活を営み、日常的に自然と触れ合うことを楽しんできました。ここでぜひ注意してもらいたいのは、それは文化人のような限られた人だけではなく、一般の人々がそうしたハイレベルで風流な生活を営んでいたということです。ところが、そのようにして400年間かけて培われてきた日本人の高い文化が、高度成長期のわずか20年ほどの短期間に忽然と姿を消してしまいました。それはとんでもない破壊行為で、日本人はなんと惜しいことをしたものだとつくづく思います。
— なぜ突然廃れてしまったのでしょうか。
青柳 結局のところ、それは戦後の日本社会の行きすぎた合理主義が原因なのだろうと思います。一般に「文化」的なものには、床の間のように人間の生存には必要不可欠というわけではないものが多いですが、だからこそ、そのよさが広く共有されていなければ存続しません。「これがあるといいよね」と多くの人が感じられるかどうかがポイントなのです。人々に広く共有されているからこそ、それが生きている文化なのであり、床の間は時代の大きな変化で、そういう存在ではなくなってしまったということです。結果として「こんなものは必要ない。そのスペースに箪笥(たんす)でも置いたほうが有益だ」と思う人が大多数になってしまったのです。
同様に失われていったものに、縁側があります。日本の家は「家の内と外の境界が曖昧」とよくいわれますが、縁側は内外を結ぶ緩衝空間で、この空間で室内の暑さ寒さがコントロールされていました。この空間があるから夏の日射は室内に入らず、冬の日射は逆に入射角度が低いので十分に部屋に届くわけです。冬の寒い日でも縁側のひだまりに居ると暖かくて心地よいですよね。
— 床の間、縁側のほかにも廃れてしまった日本建築のよい部分はあるでしょうか。
青柳 土でつくる壁も明治以降、日本の近代化の中で疎(うと)んじられてきました。一度塗って乾かしてからさらに塗り直すという工程を繰り返すため、手間と時間がかかり、現場も汚れやすいからです。
日本住宅の壁は、工期の短縮や、左官屋さんの技術に左右されず均一の仕上がりとなることなどを理由に、かつての塗装による湿式(しっしき)から、パネルや壁紙を貼る乾式へと変わっていきました。それでも伝統技術にプライドを持って塗り続けている職人さんは今でもいます。私の家の土壁は、京都の長江家住宅の保存工事の仕事でご一緒した京都の左官屋さんにお願いしました。その職人さんの強い勧めで、床の間の壁には京都の伏見稲荷あたりで採れる稲荷土という、少し赤みがかった艶(あで)やかな黄色の土で仕上げられています。そういう職人さんが今でもがんばっているのが京都らしいところですよね。
それまで住んでいたマンションから今の町家に移り住んで、夏における家の湿度の違いを肌で感じました。これは土壁が湿気を吸う機能を持っているからでしょう。こうした土壁の効果も古来の生活の知恵の一つですが、町家にはこうした知恵がたくさん詰まっているのです。町家には「火袋(ひぶくろ)」という天井が高くなっている吹き抜けの空間があります。これは厨房からの煙や熱気を抜くためのもので、屋根から暖気を排出するにともない、庭からは冷たい空気が入るという空気循環の仕組みになっています。今の家に住み始めたのは2021年ですが、夏季でもあまりエアコンを使わずに過ごせました。ここ数年の夏はあまりにも暑いので、けっこうエアコンを使っていますが(笑)。しかし、こうした天井が高くて気持ちのよい空間も、換気扇という機械で換気できるようになったことで戦後は次第に町家から失われていったのです。
いかに伝統をつないでいくか
— 歴史的建造物や昔からの生活文化を残すためには、何が大切だと思われますか。
青柳 伝統技術の継承には、大工や左官などの職人さんのように技を受け継ぐ人の存在が欠かせません。職人さんの存在は目立たないですが、実際に建物をつくるのは建築家ではなく職人さんです。そうした人たちがいなくなってしまうとどうしようもありません。京都でも木製建具の職人さんなどは本当に少なくなっています。そうした職人さんの仕事にもっと注目してほしいと思います。一昨年、『建築士』という雑誌の連載の仕事をしたときには、伝統的な職人さんの仕事ぶりを撮り続けている写真家の中塚雅晴さんの写真を表紙に掲載し、私がその写真の中の職人さんが使っている道具について解説を書きました。写真を見た若い人が「職人さんって、かっこいいな」と感じてくれればと思います。
— 先生がお考えになる「日本的な建築」とは何でしょうか。文化としての日本建築の魅力はどこにあるとお考えですか。
青柳 建築の「文化」というものは、実は建物の構造や構法と密接につながっています。日本の伝統建築は木造で、柱と梁をジャングルジムのように組み上げ、その間を壁や建具で埋めていくというもので、これを「木造軸組構法」と呼びます。大阪・関西万博の大屋根リングもそうした構法で、大屋根の下が夏季でも涼しかったことを経験した人も多いと思います。「日本では家の中を風が抜ける」といわれるのも、こうした構造を持つからで、日本にはそれにもとづく生活スタイルがあったのです。しかし、またしても高度経済成長が出てくるのですが、それを背景として、柱と柱の間に嵌められる建具や土壁が工業製品の硬いパネルや鍵付きのドアに変わり、日本の家から柔軟な開放性がなくなってしまいました。
障子やふすまなどの建具も、日本建築史の中で次第に進化してきたものです。ふすまはいわば仮の壁のようなもので、これも日本建築独自の構法のもとで生まれたものです。もともと古代の建具は木の板でできた重たいものでしたが、日常的に使うものなので動かしやすいように、時代とともに軽量化していき、木の骨組みの上に紙を貼る軽い構造になりました。骨組み自体も技術の進化とともにどんどん軽くなり、やがて音も立てずに動かせるようなものになったのです。
— 昔からあるものだと思っていましたが、障子もふすまも進化の末に生まれてきた発明品だったのですね。
青柳 こうした建具は紙が量産されないとつくることができません。木材に恵まれた日本の場合、古くから和紙の生産が発達してきたおかげで、このような建具が生まれたのです。建築以外の産業と建築とが両輪になって新しい技術が開発されたわけです。もともと重かった建具を動かしやすくするために板の下に車を仕込む「戸車(とぐるま)」が平安時代に発明されました。こうした工夫や発明の積み重ねが、やがて日本の和室を生むことになるのです。
建具をスライドさせるためのレールとなる敷居は、歩く人の足が引っ掛かったりしないよう2ミリほどの段差しかありません。一方、ご存じのように、上の鴨居はそれよりも深い溝になっていますが、これにより建具はちょっと上に持ち上げるだけで簡単に敷居から外れる仕組みになっているわけです。軽くスライドさせられるだけでなく、不要なときには簡単に外して片付けられるのです。これも大きな発明で、明治時代にこうした構法を見たエドワード・モースは驚愕し、興奮を交じえて本国にそれを伝える有名な本『日本人の住まい』を著しました。
私は自分の家でふすまを音もなくすっと開け閉めするたびに、一千年以上の歴史の重みを感じて、古代以来の職人さんに「ありがとう」とお礼を言いたくなるのです(笑)。軽く指をかけて引いただけで簡単に開閉できるふすまは、人の体温を感知して自動で開くドアなんかよりも、使ってみてずっと気持ちのいいものです。昔も今も人が感じる気持ちのよさは変わりません。それが生活の中に豊かさや楽しみを生むのです。
— 先生は日本近代の建築を主に研究されていますが、今は、大型建造物はRC造が主流となり、伝統的な日本建築の手法は見られなくなってしまったようにも思われます。
青柳 日本の伝統を表現した戦後の有名な建築として、世界的な建築家丹下健三が1964年の東京オリンピックのために設計した国立代々木競技場があります。これは丹下さんが過去の日本建築を解釈し、日本建築の伝統のよさが屋根の形の美しさにあると捉え、それを現代によみがえらせた建物です。その再現に使われたのは伝統的な木造技術ではなく現代のテクノロジーでしたが、それでも私は、あの体育館の設計は伝統継承行為の一つだと思います。
1950年代の日本では、西洋から輸入したモダニズム建築を日本の風土や建築文化に適合させようという試みが盛んに行われました。それは「日本的なもの」を建築家たちがそれぞれに解釈し、再現しようとした挑戦です。その後そうしたアプローチは下火になりましたが、最近の建築に一部見られるように、そうしたアプローチがまた復活すれば、日本の建築文化は継承されていくでしょう。近年の建築業界では、木造建築の復活がよく叫ばれますが、そうした動向はそれを後押しするものになると思います。
— 先生にとって、歴史的建造物の復元の意味はどこにありますか。
青柳 古い建築物を残すということ自体は、実は私にとって最も重要な目的ではないのです。私にとって一番大切なのは「文化」を残すことです。建築の形態は人々の好みや振る舞いに結び付いたものなので、古い建物を残すことはそれを使う人々の生活や文化を残すことに直接的につながります。極端な話、文化そのものが残るのであれば、モノとしての建築はなくなってもいい、とすら思います。それは一般的な建築史の研究者とは違ったスタンスであるらしく、同業者から批判されることもときどきあります(笑)。
古い建物が現代の建物とつながっていて、現代の文化ともつながっている。古い建物を通して、現代の日本人が昔の日本人の生活や文化をしっかり継承していく。そうした人間の営みを持続させるためのお手伝いを、これからも続けていきたいと思っています。